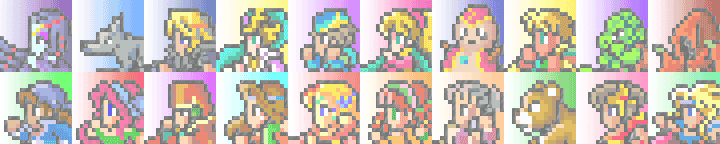
敵の逃亡条件
「王者の剣」を使用すれば敵を逃亡させることができるが、「王者の剣」を使わなくても敵が逃亡することがある。この現象は次の2つの条件を両方とも満たした時に発生する。(1)術法以外の攻撃方法を持たない。
#武器を何も装備していない。
(2)全ての系統の法力残量が0である。
よって戦闘中に逃亡することができる敵は限られる。術法しか使えない敵であっても、使用できる術法や戦闘中に使用した術法によっては法力残量が0にならない場合がある。この場合は攻撃することも逃げることもできず、ただ防御するのみとなる。味方パーティーは1ターン目から楽々と逃げることができるが、敵にとっては逃げることも一苦労のようである。
敵の幻と魔の術法
敵の使用する幻術、魔術の効果には法力が影響しない。この原因はプログラムミスだと思われるが、戦闘開始時に幻、魔の最大法力値が書き込まれていないからである。つまり現在法力値はあるが、最大法力値が無い状態になっているのである。#99/0みたいな感じ。
#他の系統は問題なく最大法力値が書き込まれる。
よって敵の使用する「幻」と「魔」の術法には知力しか影響しない。ただしサルーインは唯一の例外で、決戦の舞台効果で「幻」と「魔」の最大法力値をともに255持つ。
例1: ラルバの使用する魔術「クイック」には素早さ上昇効果がない。これはクイックの効果が法力のみに依存するから、魔の最大法力が0であるため効果が無いのである。
例2:オーガメイジのウエポンブレス(魔の法力依存)にも攻撃力強化効果はない。
敵の多重攻撃
モンスターの多重攻撃の順番はモンスターごとに決まっている。| 敵名 | 多重攻撃の順番 |
| インパラ | つの→つの |
| サーベルタイガー | 牙→牙 |
| ケルベロス | 炎→牙→炎 |
| キメラ | 炎→牙→つの |
| ツインテール | しっぽ→しっぽ |
| アクアライダー | 牙→スピア |
| アームフィッシュ | 通常→牙→通常 |
| 海の悪魔 | 触手→触手 |
| アンモナイト | 触手→触手→触手 |
| クラーケン | 触手→触手→触手 |
| ガープ | はさみ→はさみ→つの |
| ボーンゴーレム | バトルアクス→アイアンソード→スティールソード→アクス |
| トリケラトプス | つの→つの→つの |
| ジュエルビースト | 舌→体当たり |
| サイクロプス | 通常→通常 |
| ミノタウロス | つの→通常→通常 |
| 巨人 | 通常→通常 |
モンスターの実態:
・アームフィッシュは殴る、噛む、殴る。
・キメラは竜が炎を吐き、ライオンが噛み、山羊がつので突く。
・ガープは両手のはさみで切った後に、頭のつのでグサリ。
敵の技4
敵の装備武器にも武器レベルが設定されていて、味方と同様に一定の武器レベルに達すれば技を使うことができる。しかし敵の場合は武器レベルが技使用可能レベルに達していても「4つ目の技」は使うことができない。これは敵に「敵は武器レベルに関わらず4つ目の技を使用できない。その代わりに1つ後の技を使う。」という仕組みがあるからである。これにより次のような現象が起こる。(1)メデューサの「甘い香り」
まず「睨み」の技習得レベルは、以下の通りでL7で全て習得できる。
L4:麻痺睨み、L5:呪いの眼、L6:気絶睨み、L7:石化睨み
またメデューサは睨みL7なので、全ての睨み技が使えるはずである。ところが、実際はなぜか「石化睨み」を使うことは無い。そしてなぜか装備していない「香り」の技「甘い香り」を使う。これは「睨み」の5つ目の技として「甘い香り」を使用しているからである。
#技の並び順は、麻痺睨み、呪いの眼、気絶睨み、石化睨み、甘い香り・・・となっている。
(2)気付きにくい
この現象の発生は非常に気付きにくい。このイレギュラーが起こるのは「睨み」の武器Lが7以上の敵「メデューサ」と「ポイズンローズ」の2種のみである。しかしポイズンローズほうはもともと「甘い香り」を使用する。加えて特殊攻撃で技が4つあるのは「睨み」のみのため、通常範疇では同様の現象が他の技では起こりえない。よってメデューサ戦でしか気付きようがないのである。
盾装備モンスター
モンスターの中には盾を装備しているものもいる。盾を装備しているモンスターは以下の8種。スカルラミア、ウェンディゴ、コボルド、シニアコボルド、ホブゴブリン、リザードマン、スネークマン、とかげ戦士。
これらは全て「木の盾」を装備していて、片手行動をした場合は盾の効果が発揮される。
敵編成レベル
遭遇するザコ敵の敵編成には全て編成レベルが設定されている。そして編成レベルは次の2つに影響する。・味方の成長率:一般に編成レベルが高いほど、より成長しやすくなる。
・敵の行動:戦闘で使用する武器、技、術法に影響する。
■戦闘回数と敵編成L
戦闘回数に応じて、出現しうる敵編成は決まります。
| 段階 | 戦闘回数 | 出現する敵編成レベル |
| 0 | 0回~39回 | L0~L6 |
| 1 | 40回~83回 | L1~L7 |
| 2 | 84回~131回 | L2~L8 |
| 3 | 132回~183回 | L3~L9 |
| 4 | 184回~239回 | L4~L10 |
| 5 | 240回~299回 | L5~L11 |
| 6 | 300回~363回 | L6~L12 |
| 7 | 364回~431回 | L7~L13 |
| 8 | 432回~503回 | L8~L14 |
| 9 | 504回~579回 | L9~L15 |
| 10 | 580回~659回 | L10~L16 |
| 11 | 660回~743回 | L11~L17 |
| 12 | 744回~831回 | L12~L18 |
| 13 | 832回~923回 | L13~L19 |
| 14 | 924回~1019回 | L14~L20 |
| 15 | 1020回~65535回 | L15~L21 |
■段階内出現率
各段階で出現しうる編成Lの種類は7種類。それぞれの出現率について調査してみた。
#「ある編成Lと200回エンカウントするまでの戦闘回数を計測」を3セット。
(1)計664回
L0:157回(23.6%)
L1:200回(30.1%)
L2:155回(23.3%)
L3:80回(12.0%)
L4:45回(6.8%)
L5:18回(2.7%)
L6:9回(1.4%)
(2)計758回
L0:187回(24.7%)
L1:200回(26.4%)
L2:191回(25.2%)
L3:106回(14.0%)
L4:51回(6.7%)
L5:13回(1.7%)
L6:10回(1.3%)
(3)計690回
L0:165回(23.9%)
L1:200回(29.0%)
L2:149回(21.6%)
L3:111回(16.1%)
L4:44回(6.4%)
L5:16回(2.3%)
L6:5回(0.7%)
(1)~(3)をまとめて計2112回
L0:509回(24.1%)
L1:600回(28.4%)
L2:495回(23.4%)
L3:297回(14.1%)
L4:140回(6.6%)
L5:47回(2.2%)
L6:24回(1.1%)
以上の結果から出現率は弱いほうから順におよそ24%、28%、23%、14%、7%、2%、1%程度であろう。
なので、例えば敵編成が最終段階で精霊セット(L20&L21)に遭遇する率は2.2%+1.1%=3.3% 程度である。
■固定敵編成レベル
・固定敵レベルはロード後。
・ロード後にザコ敵と戦った場合は直前に戦った敵編成の編成レベルを引き継ぐ。
(情報提供:cheapさん)
■編成レベルの影響
編成レベルは次のように、装備、技、術法の使用に影響する。
(1)編成レベルと装備の使用
敵の行動に編成レベルが影響するというのはどういう意味であるか。例えばVSサンドビーストで「砂嵐」を使われたことがあるだろうか?おそらく誰も使われたことがないであろう。しかしサンドビーストは確かに「砂嵐」を装備している。そして調査の結果、以下のようになった。
・サンドビーストの「砂嵐」:L0~L9→使用する、L10~L16→使用しない、L17~L21→使用する
実際にサンドビーストと戦う場合は編成L14、15、16でしか遭遇できない。よって通常範疇では「砂嵐」を使うことがないのである。このように敵の行動には編成レベルが影響する。
(2)編成レベルと技の使用
スレイブオーガのパンチの武器Lは7であるから「クロスカウンター」を使うはずだが通常範疇では使用しない。しかし編成レベルを上げてみたら「クロスカウンター」も使い始めた。よって編成レベルは使用可能な技の制限にも影響するようである。
(3)編成レベルと術法の使用
編成レベルによって術法使用率、使用する術法も変化する。
例1:水の精霊の「毒消しの水」は編成Lが高くないとまず使わない。編成Lが低い場合は「渦潮」ラッシュである。
例2:VSサルーインで編成Lが高い場合に、ごく稀にセルフバーニングを使用する。
また、サル戦で編成Lが高いほど術法の使用率が高いような気がしたので、実際にある行動の使用回数が50回に達するまでのデータを取ってみた。
| 編成L0の場合 | 編成L21の場合 |
| ・サルーインソード:50回 ・撃剣波:21回 ・ファイアボール:4回 ・レインコール:6回 ・ダイヤモンドウエポン:8回 ・ライトニング:6回 ・ブラックファイア:7回 ・アニメート:10回 ・エナジーボルト:7回 ・幻影魅力術:6回 |
・サルーインソード:50回 ・撃剣波:21回 ・ファイアボール:31回 ・レインコール:41回 ・ダイヤモンドウエポン:18回 ・ライトニング:29回 ・ブラックファイア:30回 ・アニメート:22回 ・エナジーボルト:30回 ・幻影魅力術:26回 ・アースハンド:1回 ・イーブルスピリット:2回 |
以上のように編成Lが高いほど術法使用率が高いようである。
■知力の影響
ゾンビ系L16のサンドビースト×2、アンシリーコート×2で調査。この編成の編成Lを変えることでの行動の変化を調べてみた。
・サンドビーストの「砂嵐」:L0~L9→使用する、L10~L16→使用しない、L17~L21→使用する
・アンシリーコートの「牙」:L0~L5→使用する、L6~L16→使用しない、L17~L21→使用する
使用可能な編成Lに違いがあるが、アンシリーコートとサンドビーストの使用範囲の違いは何に依るのか?アンシリーコートは知力34、サンドビーストは知力23である。そこで編成L9のアンシリーコートの知力をサンドビーストと同じ23にしたら牙を使い始めた。
#他にもFタイラントの知力を0にしたら牙を使用した。etc
次に編成L16で両者の知力を0にしてみたら両者とも砂嵐、牙を使うことは無かった。ところが編成L10で両者の知力を0してみたら砂嵐、牙を使用した。
以上により、敵の行動の種類数は編成Lと知力の兼ね合いで決定されていると思われる。かまった感じでは、知力が低いほどより多彩で、知力が高いほど主要武器(武器欄1)を使うと思う。
■編成レベルと行動パターン
------------------------------------
cheapさんの調査結果:
レベルが上がると術の使用率が上がっていく。[(128+8*Lv)/256と予想]
レベル15でほぼ術しか使用しないようになる。
しかし、レベル16以上になると行動パターンが変わり(オーバーフロー?)、最強術以外も使用するようになったりする。
------------------------------------
上記のように、編成レベルと行動パターンの関係に最初に言及したのはcheapさんであるが、虎の巣の後の調査によると行動パターンが変わるのはレベル17以上のようであった。以下にその調査結果を示す。
敵の行動パターンは編成L0~16と編成L17~21の二つに分けられる。
(i)編成L0~16は編成Lに応じて行動が変わる。
・編成Lが高いほど術法使用率が上がる。
・編成Lが高いほど各系統におけるより高等な術法の使用率が高い。
・編成Lが高いほど防御の使用率が下がる。
・武器を使用する場合は並び順が前の武器の使用率が上がる。
(ii)編成L17~21は編成Lに応じて行動が変わらない。
・術法を使用する場合は各系統におけるより高等な術法の使用率が高い。
・知力が高いほど術法使用率が高くなり、知力が十分に高い場合はL16と同じ行動になる。
#ほとんどの敵は知力が十分に高くないので、L16で術法使用率がマックスになるが、L17~21でL16と比べて術法使用率がガクッと下がる。
#「知力が十分に高い」の「十分」はサルの知力の125くらいは必要なので、行動パターンの区切りが無いのはサルだけということになるだろう。
(1)編成レベルと知力の関係
L0~16の行動パターンは編成Lと知力に依存するが、編成Lと知力は対等なのかを調べてみた。
(L0、知力0)と(L16、知力0)の行動を20ターン分調べて、L0で知力をどれだけ上げたら(L16、知力0)と同じ行動になるのか?
結果としては、編成Lと知力は対等ではなく、(L0、知力56)で(L16、知力0)と20ターンの行動は同じになった。
56というと、モンスター各系統の最強ランクの基本値なので、納得いくというか、ありえそうな値ではある。
従って、編成L:知力=16:56とすれば、「編成Lが1増加する」のと「知力が3.5増加する」のが相等の関係になる・・・ようである。
(2)編成レベルと使用する技の関係
敵の使用する技の使用率には編成レベルは関係無いようである。
使用可能な技で最も高度なものの使用率が最も高く、それ以外の使用率はどれも同じくらいのようである。
この傾向についてのcheapさんの見解は以下の通り。
>技の使用については、
>「0から武器レベルまでの範囲の値をランダムで決め、その値を武器レベルとみなしたときに使用可能な最強の技を使う」
>のようになっていると推測できます。
>(アイアンソードL14の場合:0,1,2がアイアンソード、3,4,5が隼斬り、6,7,8,9がかまいたち、10,11,12,13,14が流星剣になり、3:3:4:5の割合になる)
(3)編成レベルと使用する術法系統
敵の使用する術法系統には編成レベルは関係ないようである。
しかしながら、竜神族は火>風、リッチは闇>魔>邪というように、編成Lに関わらず使用率に偏りがあるようである。
#系統の並び順は火水土風光闇邪気魔幻であるから、並び順が前のものを優先して使用するわけでもない。
この傾向についてのcheapさんの見解は以下の通り。
>ランダムで10系統を選んだあと、法力が0なら次の系統にスライドする(幻の場合は火へ)と説明がつくと思われます。
>龍神族の場合、光闇邪気魔幻が火、水土が風となり、比率は火:風=7:3
>リッチの場合、火水土風光幻が闇、気が魔になるので、比率は闇:魔:邪=7:2:1
(4)選択率のついての予想
BBSにいただいたcheapさんからの書き込み。
-------------------------------------
現時点(2022年1月)での推測ですが、
術と武器の両方が使える場合の術選択率
(128+編成L*7)/256
最高ランクの術を使ったり、先頭の武器が選ばれる確率
編成L16以下:(128+編成L*7+知力*2)/256
編成L17以上:(1+知力*2)/256
となっています。
-------------------------------------
(5)L17~21の行動
L17~21の行動は一般にL0~16のどれにも属していない。
もしかしたら、(L0、知力0)の行動になっているのでは?と思って調査してみたが、L0で知力0にしてもL17の行動にはほど遠かった。
■レア特殊攻撃
通常範疇でまず見ることができない敵の攻撃方法をレア特殊攻撃とよぶ。レア特殊攻撃には以下のようなものがある。
(1)シックル
装備している敵がいない。
(2)サンゴミサイル
コーラルクラブが装備しているが編成Lの影響でまず使わないと思う。
(3)砂嵐
・サンドビーストが装備しているが編成Lの影響でまず使わないと思う。
・グリフォンが装備しているが出現しない。
(4)防御
コカトリスが装備しているが編成Lの影響でまず使わないと思う。
#使ったとしても「鈍足効果」があるだけで「触ると石化」効果はない。
(5)殻に入る
アンモナイトが装備しているが編成Lの影響でまず使わないと思う。
(6)分裂
装備している敵がいない。
(7)丸太
オーガが装備しているが編成Lの影響でまず使わないと思う。
(8)ダークソード
敵の術法習得値(後述)の影響で使用する敵はいない。
(9)石化睨み
メデューサが使用可能武器Lに達しているが、敵の技4(前述)により使用できない。
(10)毒針飛ばし
マンティコアは基礎能力値は低いが針の武器Lが14で、「毒針飛ばし」を使用可能なレベルに達している唯一のモンスターである。しかしマンティコアは出現しない。
敵の習得術法
味方メンバーの習得術法は、術法習得値が255なら、255=128+64+32+16+8+4+2+1で8種全て使用できるという仕組みであるが、敵の習得術法は別の仕組みで決定されている。■敵の習得術法の仕組み
敵の習得術法は「敵の術法習得値」、「術法の消費法力」、「術法の術法習得値」で決定される。
(1)まず術法習得値に応じて最も高位の習得術法が決定される。
・術法習得値1ならば術法1を習得。
・術法習得値2~3ならば術法2を習得。
・術法習得値4~7ならば術法3を習得。
・術法習得値8~15ならば術法4を習得。
・術法習得値16~31ならば術法5を習得。
・術法習得値32~63ならば術法6を習得。
・術法習得値64~127ならば術法7を習得。
・術法習得値128~255ならば術法8を習得。
以降は、以下の規則に従って習得術法が決定される。
(2)習得した術法の消費法力によって以下のように次の習得術法が決定される。
・消費法力1ならば術法1を習得。
・消費法力2~3ならば術法2を習得。
・消費法力4~7ならば術法3を習得。
・消費法力8~15ならば術法4を習得。
・消費法力16~31ならば術法5を習得。
・消費法力32~63ならば術法6を習得。
#設定できる消費法力の最大値は63。
(3)↑で止まった場合、術法習得値<消費法力ならば術法1を習得。そうでないならば、そこで終了。
(4)術法1を習得したら終了。
■具体例
例1:火術の術法習得値128以上の場合
(1)術法習得値が128以上なので術法8の焼き尽くすを習得。
(2)焼き尽くすの消費法力は10なので術法4のファイアボールを習得。
(3)ファイアボールの消費法力は4なので術法3のセルフバーニングを習得。
(4)セルフバーニングの消費法力は4で、術法習得値4より大きくないのでここで終了。
→焼き尽くす、ファイアボール、セルフバーニング
例2:水術の術法習得値128以上の場合
(1)術法習得値が128以上なので術法8の渦潮を習得。
(2)渦潮の消費法力は9なので術法4の毒消しの水を習得。
(3)毒消しの水の消費法力は2なので術法2の力の水を習得。
(4)力の水の消費法力は1なので術法1の癒しの水を習得。
→渦潮、毒消しの水、力の水、癒しの水
例3:土術の術法習得値128以上の場合
(1)術法習得値が128以上なので術法8のストーンスタチューを習得。
(2)ストーンスタチューの消費法力は9なので術法4のダイヤモンドウエポンを習得。
(3)ダイヤモンドウエポンの消費法力は6なので術法3のアースハンドを習得。
(4)アースハンドの消費法力は4で、術法習得値4より大きくないのでここで終了。
→ストーンスタチュー、ダイヤモンドウエポン、アースハンド
例4:風術の術法習得値128以上の場合
(1)術法習得値が128以上なので術法8のシムラクラムを習得。
(2)シムラクラムの消費法力は10なので術法4のエレメンタルを習得。
(3)エレメンタルの消費法力は7なので術法3のウインドバリアを習得。
(4)ウインドバリアの消費法力は4で、術法習得値4より大きくないのでここで終了。
→シムラクラム、エレメンタル、ウインドバリア
例5:光術の術法習得値128以上の場合
(1)術法習得値が128以上なので術法8のスターソードを習得。
(2)スターソードの消費法力は10なので術法4のインビジを習得。
(3)インビジの消費法力は6なので術法3のフラッシュを習得。
(4)フラッシュの消費法力は4で、術法習得値4より大きくないのでここで終了。
→スターソード、インビジ、フラッシュ
例6:闇術の術法習得値128以上の場合
(1)術法習得値が128以上なので術法8のダークソードを習得。
(2)ダークソードの消費法力は10なので術法4のブラックファイアを習得。
(3)ブラックファイアの消費法力は4なので術法3のホラーを習得。
(4)ホラーの消費法力は3なので術法2のダークネスを習得。
(5)ダークネスの消費法力は2で、術法習得値2より大きくないのでここで終了。
→ダークソード、ブラックファイア、ホラー、ダークネス
例7:邪術の術法習得値128以上の場合
(1)術法習得値が128以上なので術法8のデスハンドを習得。
(2)デスハンドの消費法力は10なので術法4のイーブルスピリットを習得。
(3)イーブルスピリットの消費法力は7なので術法3のアゴニィを習得。
(4)アゴニィの消費法力は5で、術法習得値4より大きいので術法1のポイズンガスを習得。
→デスハンド、イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス
例8:気術の術法習得値128以上の場合
(1)術法習得値が128以上なので術法8の生気翔撃法を習得。
(2)生気翔撃法の消費法力は10なので術法4の防御法を習得。
(3)防御法の消費法力は1なので術法1の腕力を習得。
→生気翔撃法、防御法、腕力法
例9:魔術の術法習得値128以上の場合
(1)術法習得値が128以上なので術法8のエナジーストームを習得。
(2)エナジーストームの消費法力は9なので術法4のスペルエンハンスを習得。
(3)スペルエンハンスの消費法力は6なので術法3のマジックヒールを習得。
(4)マジックヒールの消費法力は5で、術法習得値4より大きいので術法1のエナジーボルトを習得。
→エナジーストーム、スペルエンハンス、マジックヒール、エナジーボルト
例10:幻術の術法習得値128以上の場合
(1)術法習得値が128以上なので術法8の竜幻術を習得。
(2)竜幻術の消費法力は10なので術法4の幻霧術を習得。
(3)幻霧術の消費法力は5なので術法3の睡夢術を習得。
(4)睡夢術の消費法力は5で、術法習得値4より大きいので術法1の火幻術を習得。
→竜幻術、幻霧術、睡夢術、火幻術
上記の規則より、敵が一つの系統において8種全ての術法を習得することは不可能である。
消費法力を書き換えたとしても最大で7種までしか習得できない。
例えば、8種の術法の消費法力を術法1から順に0、1、2、4、8、16、32、32とすれば、術法習得値128の敵は術法7を除いた7種の術法を習得する。
次に各系統ごとの術法習得値と使用可能術法を示す。
(1)火の術法
| 術法習得値 | 習得術法 |
| 1 | ヘルファイア |
| 2~3 | ファイアウエポン |
| 4~7 | セルフバーニング |
| 8~15 | ファイアボール、セルフバーニング |
| 16~31 | 火エレメンタル、セルフバーニング |
| 32~63 | ファイアウォール、ファイアボール、セルフバーニング |
| 64~127 | 火の鳥、ファイアボール、セルフバーニング |
| 128~255 | 焼き尽くす、ファイアボール、セルフバーニング |
(2)水の術法
| 術法習得値 | 習得術法 |
| 1 | 癒しの水 |
| 2~3 | 力の水、癒しの水 |
| 4~7 | レインコール、力の水、癒しの水 |
| 8~15 | 毒消しの水、力の水、癒しの水 |
| 16~31 | ウォーターガン、力の水、癒しの水 |
| 32~63 | 油地獄、レインコール、力の水、癒しの水 |
| 64~127 | 水エレメンタル、レインコール、力の水、癒しの水 |
| 128~255 | 渦潮、毒消しの水、力の水、癒しの水 |
(3)土の術法
| 術法習得値 | 習得術法 |
| 1 | ダイヤモンドスピア |
| 2~3 | カモフラージュ、ダイヤモンドスピア |
| 4~7 | アースハンド |
| 8~15 | ダイヤモンドウエポン、アースハンド |
| 16~31 | ダイヤモンドアーマー、アースハンド |
| 32~63 | アースヒール、アースハンド |
| 64~127 | 土エレメンタル、アースハンド |
| 128~255 | ストーンスタチュー、ダイヤモンドウエポン、アースハンド |
(4)風の術法
| 術法習得値 | 習得術法 |
| 1 | アイスジャベリン |
| 2~3 | コールドウエポン |
| 4~7 | ウインドバリア |
| 8~15 | 風エレメンタル、ウインドバリア |
| 16~31 | ライトニング、風エレメンタル、ウインドバリア |
| 32~63 | ブラッドフローズ、風エレメンタル、ウインドバリア |
| 64~127 | 吹雪、風エレメンタル、ウインドバリア |
| 128~255 | シムラクラム、風エレメンタル、ウインドバリア |
(5)光の術法
| 術法習得値 | 習得術法 |
| 1 | スターファイア |
| 2~3 | ライト |
| 4~7 | フラッシュ |
| 8~15 | インビジ、フラッシュ |
| 16~31 | ヒールライト、フラッシュ |
| 32~63 | スターライトウォール、インビジ、フラッシュ |
| 64~127 | スターライトウェブ、インビジ、フラッシュ |
| 128~255 | スターソード、インビジ、フラッシュ |
(6)闇の術法
| 術法習得値 | 習得術法 |
| 1 | 影縛り |
| 2~3 | ダークネス |
| 4~7 | ホラー、ダークネス |
| 8~15 | ブラックファイア、ホラー、ダークネス |
| 16~31 | ダークウォール、ブラックファイア、ホラー、ダークネス |
| 32~63 | ブラックスフィア、ブラックファイア、ホラー、ダークネス |
| 64~127 | ダークウェブ、ブラックファイア、ホラー、ダークネス |
| 128~255 | ダークソード、ブラックファイア、ホラー、ダークネス |
(7)邪の術法
| 術法習得値 | 習得術法 |
| 1 | ポイズンガス |
| 2~3 | インジャリー、ポイズンガス |
| 4~7 | アゴニィ、ポイズンガス |
| 8~15 | イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス |
| 16~31 | ライフドレイン、イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス |
| 32~63 | ウイークネス、イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス |
| 64~127 | アニメート、イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス |
| 128~255 | デスハンド、イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス |
(8)気の術法
| 術法習得値 | 習得術法 |
| 1 | 腕力法 |
| 2~3 | 夢想法、腕力法 |
| 4~7 | 精神法、腕力法 |
| 8~15 | 防御法、腕力法 |
| 16~31 | 破邪法、精神法、腕力法 |
| 32~63 | 精神波、精神法、腕力法 |
| 64~127 | 生命波、精神法、腕力法 |
| 128~255 | 生気翔撃法、防御法、腕力法 |
(9)魔の術法
| 術法習得値 | 習得術法 |
| 1 | エナジーボルト |
| 2~3 | スロウ、エナジーボルト |
| 4~7 | マジックヒール、エナジーボルト |
| 8~15 | スペルエンハンス、マジックヒール、エナジーボルト |
| 16~31 | ウエポンブレス、マジックヒール、エナジーボルト |
| 32~63 | アーマーブレス、マジックヒール、エナジーボルト |
| 64~127 | クイック、マジックヒール、エナジーボルト |
| 128~255 | エナジーストーム、スペルエンハンス、マジックヒール、エナジーボルト |
(10)幻の術法
| 術法習得値 | 習得術法 |
| 1 | 火幻術 |
| 2~3 | 破幻術、火幻術 |
| 4~7 | 睡夢術、火幻術 |
| 8~15 | 幻霧術、睡夢術、火幻術 |
| 16~31 | 幻影魅力術、睡夢術、火幻術 |
| 32~63 | 幻体戦士術、睡夢術、火幻術 |
| 64~127 | 雷幻術、幻霧術、睡夢術、火幻術 |
| 128~255 | 竜幻術、幻霧術、睡夢術、火幻術 |
以上のように、術法習得値が255でも全ての術法が使えるわけではなく、術法習得値が十分にあったとしても各系統の5~8番目の術法はいずれか1つしか使えない。
■風エレ&重複エレ
味方基準で敵の術法習得値を見てみると風エレを習得している敵は一匹もいない。しかし、上記の敵専用の術法習得システムのために風エレを使用できるようになってしまい、さらにエレはエレを使えないはずだが、この仕組みのためにエレが使えてしまい、結果、重複エレを引き起こしているわけである。
攻撃術法の対象決定
敵の攻撃術法は「味方の現在HPに基づく値」に基づいて対象決定される。味方の現在HPに基づく値P={(現在HP/5)(mod 256)+r}(mod 256) (0≦r<≦(現在HP/5)(mod 256))
敵が攻撃術法を使用する場合には、使用する敵ごとに以下の処理がなされる。
(1)仲間の人数分並び順に従って「味方の現在HPに基づく値」が算出される。
例:6人パーティーならば(1人目のP)(2人目のP)(3人目のP)(4人目のP)(5人目のP)(6人目のP)のようになる。
(2)次の手順に従って、(1)で並べられた値の並び替えがなされる。
ステップ1:データ1とデータ2の値を比較して、データ1≦データ2ならばデータ1とデータ2を入れ替える。
ステップ2:データ1とデータ3の値を比較して、データ1≦データ3ならばデータ1とデータ3を入れ替える。
・・・
ステップ5:データ1とデータ6の値を比較して、データ1≦データ6ならばデータ1とデータ6を入れ替える。
#上記は6人パーティーの場合。n人パーティーでステップ(n-1)まで行われる。
(3)上記の手順で一番左に来ている者が攻撃術法の対象になる。
攻撃術法というのは火術「ヘルファイア」のような単体攻撃術法に限らず、
・縦複数の火術「ファイアウオール」
・全体の火術「火の鳥」
・物理単体の土術「ダイヤモンドスピア」
・物理横複数の風術「ライトニング」
・即死の風術「ブラッドフローズ」
・状態異常(麻痺)の闇術「影縛り」
といった味方パーティーに直接被害を与える術法が当てはまる。
#複数、全体対象の術法も個人が狙われて、それに巻き添えになる形で被害が出る。
術法誤射(術法反射)
戦闘中に敵が状態異常にかかっているわけでもないのに、敵の術法が敵パーティーを攻撃対象とする場合がある。この現象はロマ1攻略界隈では長らく術法反射と呼ばれていたが、その仕組みを明らかにした結果、反射しているわけではなかったので、本サイトでは術法誤射と呼ぶことにする。術法誤射は以下の条件を満たしたときに発生する。
・1人パーティーである。
#召喚獣を呼んだ場合も1人パーティー扱いになる。
・主人公の「味方の現在HPに基づく値P」が乱数によって毎ターン変動する区切りのHP未満である。
#味方の現在HPに基づく値P={(現在HP/5)(mod 256)+r}(mod 256) (0≦r<≦(現在HP/5)(mod 256))
・「前ターンに敵側で行動順が2番目の敵の行動順決定のための素早さ」が上記の主人公の「味方の現在HPに基づく値P」以上である。
上記の条件による術法誤射の発生は、敵の攻撃術法の対象決定のシステムで説明することができる。
まず、「攻撃術法の攻撃対象の決定」と「敵の行動順決定」の内部数値の処理は同じ場所で行われている。
次に、敵が攻撃術法を使用する場合の処理はおそらく以下の順でなされている。
(1)味方パーティーの現在HPに基づく値をチェックする人数の確認
(2)味方パーティーの現在HPに基づく値のチェック
(3)味方パーティーの現在HPに基づく値を降順に並べ替え(→先頭が攻撃対象)
(4)敵側の行動順決定のための素早さのチェック
(5)敵側の行動順決定のための素早さを降順に並び替え(→先頭から順に行動)
そして、問題となるのは(3)のところである。(3)のところはパーティー人数分の並び替えが起こるのが通常の処理であると思われるが、1人パーティーの場合にはイレギュラー?で、おそらく2人目の部分を含めた並び替えが起こってしまう。その結果、「1人目の現在HPに基づく値」・・・即ち「{(現在HP/5)(mod 256)+r}(mod 256)」が「前ターンに敵側で行動順が2番目の敵の行動順決定のための素早さ」よりも低い場合には、並び替えにより「前ターンに敵側で行動順が2番目の敵の行動順決定のための素早さ」と「前ターンに敵側で行動順が2番目の敵」の数値が先頭になるために、術法の攻撃対象が「前ターンに敵側で行動順が2番目の敵」になってしまうのである。
■攻撃術法を使用する敵が複数いる場合
複数の敵が術法を使用できる場合は、そのターンで術法を使用する並び順が最も上位(右上から順に下へ、再下段の次は一つ後列の最上段・・・)の1体の使用する術法のみが術法誤射する。
その仕組みは、行動決定が先の敵に上記の仕組みが採用され、以降の敵の場合には「前ターンに敵側で行動順が2番目の敵の行動順決定のための素早さ」と「前ターンに敵側で行動順が2番目の敵」の数値が味方パーティー1人目の現在HPに基づく値に並べ替えられているため、対象が敵にはならないのである。
■複数人パーティーの場合
上記の仕組みに基づくと複数人パーティーでは術法誤射は発生しないことになるのであるが、複数人パーティーでも術法誤射のような現象が発生した・・・はず。こちらについてはまだ解明できていない。
