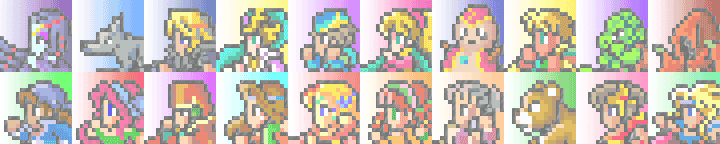
「ロマ1に対する否定的な意見」に対する反論
(2025年03月01日発表)#本稿は2023年9月から2024年にかけてBBSに断続的に書き込んでいた内容・議論を再編したものである。
はじめに
1.概説
(1)クソゲー評に欠けている二つの観点
(2)ちょっとした提言
(i)「クソゲー」ではなく「合わないゲー」
(ii)ゲームプレイの順序性
2.「分からない」の類の否定的な意見
(1)ゲームの進め方が分からない
(i)ロマ1のフリーシナリオシステム
(ii)「プレイヤーの能力」の側面
(iii)「プレイヤーの基準」の側面
(2)公表されていなかったデータや仕組み
(i)ロマ1の攻略本事情
(ii)ロマ1攻略サイト情報の弊害
3.戦闘に関する否定的な意見
(1)敵の多さに関する否定的な意見
(i)ロマ1の物語内の時間の進展システム
(ii)ロマ1のシンボルエンカウントシステム
(iii)ロマ1の敵の多さについての見解
(a)視覚的な敵の多さ
(b)エンカウント密度
(c)一戦闘ごとの面倒さ
(iv)その他の発展途上だったシステム
(2)敵の強さに関する否定的な意見
(i)特定の敵が強いのが嫌だ!
(ii)出現敵編成の進展システムが嫌だ!
4.全体的な粗さに関する否定的な意見
(1)不完全さ
(2)バグ
(3)バランスの悪さ
(4)一部の詰み
5.その他の否定的な意見
(1)武器を外す
(2)お金の上限
(3)文字の大きさ
6.私的残念ポイント
(1)背景グラフィック
(2)背景ミュージック
(3)ファミコン通信のレビュー
おわりに
はじめに:
ネットにおいて「ロマサガ1」で検索していると度々「ロマサガ1はクソゲーだ!」という否定的な意見を目にする。ロマ1発売当時のことを思い出してみても、私自身ロマ1をそのように思ったことは一度も無かったし、私の周りにもそのような意見を言う者はいなかった。
ところが、90年代末にネットを始めてからクソゲー云々という意見を目にするようになる。
取っ掛かりとしては、シュウさんの『クソゲー白書』批判。
某団体が「あなたがクソゲーだと思うゲームは?」というアンケートを取った結果、ロマ1が1位になったという。
シュウさんはこの結果を統計の題材として扱っているので量的に批判しているけれど、質的に見てもこの結果でロマ1を叩くのはどうなのか?って思ってしまう。
だって、結果の上位が
| 順位 | タイトル | 票数 |
| 1 | ロマンシングサガ1 | 14票 |
| 2 | ファイナルファンタジー7 聖剣伝説2 |
13票 |
この結果が妥当なものならばFF7や聖剣2もロマ1程度に叩かれていないとおかしいということになるけれど、実際はどうなのか?って話である。
私がこの結果を見る限りは、ロマ1はFF7や聖剣2と同様に名作の一つとして称賛されているようにしか見えないのである。
そうは言っても、ロマ1に対する否定的な意見を述べているのは上記のクソゲー白書だけではない。
ネット上には様々なロマ1に対する否定的な意見が書き連ねられている。
ただ、それらの意見を一つ一つ見てみると、果たしてそれは本当に妥当な意見なのか?と首を傾げたくなる。
つまり、私からすると、それらの意見のほとんどはただの言いがかり・不当な難癖のようにしか思えないのである。
そこで、本稿ではネット上にあるロマ1への否定的な意見に対する私の見解について述べようと思う。
1.概説
(1)クソゲー評に欠けている二つの観点
そもそもクソゲーとは何なのか?Wikipediaの「クソゲー」のページによると、
| ゲーム作品がクソゲーと呼ばれる理由はプレイヤーの事情や感性によって異なるため一概に断定することはできないが、 基本的には「プレイヤーが投じた金銭や時間に、面白さがまったく見合わないビデオゲーム」がクソゲーであるとされる。 具体例としては「難しすぎて、やる気がなくなってしまうゲーム」「ゲームシナリオや設定が悪く、一貫性に欠ける」 「安易なキャラクターゲーム」などが挙げられている。 |
これをクソゲーの定義とするならば、クソゲーとは個人の主観に基づくものであるから、その人が「クソゲーだ!」と思ったのならば「その人にとってはクソゲーである」ということを否定することはできない。
さて、上記の定義に基づけば「ロマサガ1はクソゲーだ!」と評する人がいること自体はやむを得ないし、その人の主張を否定できるものではない。
ただ、それでも私がクソゲー評を「ただの言いがかり・不当な難癖」のように思うのは、クソゲーと評する理由に引っかかる点があるからである。
つまり、ロマ1がクソゲーと評されている理由が「ゲームそのものにある」のではなく「プレイヤー側にある」にもかかわらず、それが考慮されていない意見にすぎないと思われるのである。
では、クソゲー評に欠けているプレイヤー側の観点とは何なのか?と言うと、それは以下の2点である。
◆プレイヤーの能力
クソゲー評に欠けているプレイヤー側の観点その1は「プレイヤーの能力」である。
掻い摘んで言えば、「あなたができないからクソゲーだって言うのはおかしくないですか?」ということである。
例えば、学校のテストであなたができなかったら「クソ問題」・「クソテスト」・「クソ教科」ってなりますか?
あなたができなかったのは、ただ単にあなたの能力がまだ足りていなかっただけではありませんか?
ロマ1を楽しむために必要な前提となる能力が身についていないままでロマ1をプレイして叩いている状況は、英語が読めないのに英語の本を買って「難しくて分からない!」と言っているようなものなので、滑稽としか言いようがありません。
◆プレイヤーの基準
クソゲー評に欠けているプレイヤー側の観点その2は「プレイヤーの基準」である。
掻い摘んで言えば、「比較対象がおかしくないですか?」ということである。
例えば、2010年代以降のゲームで育った人が、1990年代のゲームを2010年代以降のゲームを基準に評価するのは適切なのですか?
ゲーム発売当時のゲームの進化の時系列を分かっていますか?
今のゲームと比べて昔のゲームがダメだから「クソ」って評するのは、縄文時代にはスマホが無いから「クソ」と言っているようなもので、ナンセンスとしか言いようがありません。
ロマ1に対するクソゲー評のほとんどは上記の2観点の欠如を指摘することで棄却することができると思うが、より具体的に納得していただくために、第2章以降では代表的なクソゲー評に対して具体的に検討をしていくことにする。
(2)ちょっとした提言
第2章の前に(1)で述べたことに関わる小さな提言をしておく。(i)「クソゲー」ではなく「合わないゲー」
(1)で述べたようにクソゲーとは個人の主観の話であるから、「その人にとってはクソゲーである」ということを否定することはできないが、逆に「その人にとってはクソゲーである」ことを一般化して「そのゲームはクソゲーである」としてしまうことは明らかにおかしいであろう。また、安易に「クソゲー」と評してしまうと、そのゲームを好きな人に不快な思いをさせてしまう可能性が高いであろう。
このように「クソゲー」という蔑称には何の利点もないので、もう「クソゲー」という蔑称をやめましょう。
代わりに、「その人には合わなかったゲーム」・・・「合わないゲー」と言うのはどうでしょうか?
あなたがあるゲームを「クソだ!」と思ったのならばそれは真実ですが、実はそれはそのゲームがあなたに合わなかっただけなのです。
あなたにとってネガティブなものを何でもかんでも「クソ」と蔑称するのではなく、「合わなかった」という個人のこととして表現したほうがみんな幸せになれるでしょう。
(ii)ゲームプレイの順序性
(1)において「ゲームを楽しむためには前提となる能力が身に付いている必要がある」ということを述べたが、この主張を言い換えるならば「ゲームをプレイするにも適切な段階を踏まえる必要がある」ということである。例えば、学校の学習内容にも順序性・学習段階があるように、ゲームをプレイするためにも実はそういう順序性があるのだと思う。
具体的な事例を挙げれば、堀井氏がドラクエ初期3部作において「1」でRPGの基礎、「2」でパーティー制、「3」で職業選択を導入することで、RPGに馴染みの無かった当時のユーザーたちにRPGの遊び方を学習できるようにしたというのはゲームプレイの順序性の典型であろう。
参考:「パーティー制」「職業選択」ドラクエと「全部のせ」「毎回別システム」FF。<二大国産RPG>は何がどう違っていたのか
現在のゲームならば1本のゲームだけでそのゲームの遊び方を基礎から学べるかもしれないが、少なくとも昔のゲームはそうではない。
おそらく、ある程度基礎に位置付けられるゲームで「ゲームの遊び方」を学び、それを身に付けた上で後発のゲームをプレイしないと、プレイヤーの能力不足で門前払いになってしまうということも起こりえるのである。
#SFC版ロマ1について言えば、それ以前の代表的なRPGであるドラクエ1~4、FF1~4、GBサガ1~2のいくつかを自力で楽しめていれば、取り立てて難しいゲームということにはならないはずである。
2.「分からない」の類の否定的な意見
(1)ゲームの進め方が分からない
ロマ1に対する否定的な意見には「何をやったらいいのか分からない」、「どこに行ったらいいのか分からない」等のゲームの進め方に関するものが多い。ロマ1はフリーシナリオシステムだから「何をやったらいいのか分からない」、「どこに行ったらいいのか分からない」と思う人がいるかもしれないが、それは誤解である。
まずはこの点について説明する。
(i)ロマ1のフリーシナリオシステム
| あのサ・ガが遂に実現!! RPG究極の「フリーシナリオシステム」をひっさげスーパーファミコンで新登場!! イベントをクリアしてゲームを進めていくのではなく、すべてのイベントにどうかかわるかを決定できる、 つまり自分の意志を最大限に発揮できる、極めて自由度の高いシナリオシステムです。 |
一番のポイントは「すべてのイベントにどうかかわるかを決定できる」というところであり、この文言は「イベントで何をするか自由」という狭義の意味ではなく、「そもそもイベントに関わるかどうかも自由」という意味も含んでいるのである。
スクウェアが出した最初の説明文付き広告でそれが述べられているということは、それがロマ1の一番の売りということであり、開発者側が一番強くこだわったところである。
「ロマサガ」と言えば「フリーシナリオシステム」と思う人もいるかもしれないが、ロマ1とロマ2、3では明らかな違いがある。
と言うのは、ロマ2、3は(大まかには)最低限こなさなければならないイベントがいくつかあって、それを含めてどのような順序でイベントに関わってもいいですよ!というものであるが、一方でロマ1は上記で述べた「そもそもイベントに関わるかどうか」の判断もプレイヤーに委ねられているので、一切イベントに関与しなくても最終決戦に挑むことが可能なのである。
即ち、ロマ1のフリーシナリオシステムは「ラスボスまでのイベントをこなす順番が自由」ではなく「ラスボスまでに何をして過ごすかは自由」というシステムなのである。
#但し、以下4人の主人公は開始時に強制イベントがあるので、そのイベントには関わる必要がある。
| 強制イベント有り:アルベルト、ホーク、クローディア、シフ 強制イベント無し:ジャミル、グレイ、アイシャ、バーバラ (→途中のイベントに一切関わらないことが可能) |
(ii)「プレイヤーの能力」の側面
上述したようにロマ1のフリーシナリオシステムは「ラスボスまでに何をして過ごすかは自由」なのであり、イベントへの関わり方自体は従来のRPG(もっと言えば従来のゲーム)と何ら変わりは無い。つまり、やるべきことは従来のRPGと同様に「今行けるところに行く」、「今できることをやる」だけである。
例えば、ドラクエで船を入手したときのようなものである。
ポーンと大海原に放り出されて、移動できる場所が途端に広がるわけだけど、その際にやることは「今行けるところに行って」、「今できることをやる」のである。
そうすれば大概は新たなイベントに出会って物語が進展するのである。
ロマ1もそれと何ら変わりはありません。
従って、「何をやったらいいのか分からない」、「どこに行ったらいいのか分からない」なんて意見は、プレイヤーが従来のRPGにおいても当たり前にやるべきことをやっていないだけなのであり、「私は従来のRPGで身に付けておくべき力が身に付いていません(RPGの問題解決能力がありません)」と宣言しているにすぎないのである。
(iii)「プレイヤーの基準」の側面
「ゲームの進め方が分からない」に関わって「不親切、説明不足」と言う意見もある。しかしながら、当時のゲームはロマ1に限らずゲーム内で(説明書でも)懇切丁寧に説明されるなんてことはほとんど無かった。
つまり、「今できることをやる」、「今行けるところに行く」をやって自分で解き明かしていくのが当たり前であった。
例えば、全ての人に話しかけたり、壺などのオブジェクトを調べたりするなんてことは基本中の基本であり、さらには1マス1マス調べるとか、全ての壁にアタックする(抜け道探し)とかも当たり前のことだった。
このように昔のゲームは地道に調べるのが当たり前だったから、それが「不親切、説明不足」だと思ってしまうのは、調べるべきところが光っていたり、話すべき相手に印がついていたり、次に行くべき場所の案内が表示されていたりといったユーザーフレンドリーに改善されていったロマ1よりも後発のゲームと比較しての意見でしかないのである。
(2)公表されていなかったデータや仕組み
ロマ2やロマ3に対してはマスクデータについての否定的な意見が散見されるのであるが、ロマ1に対してはそういった意見はほとんど見られない。ロマ1も基本的にはマスクデータばかりなのであるが、この違いはどうしてなのだろうか?
おそらく、ロマ2やロマ3はゲーム内で表示される情報と後年攻略サイトで明らかになった情報との齟齬があったために「騙された!」と感じて否定的な意見に繋がったのだと思われるが、一方でロマ1の場合はそもそもゲーム内では各種データがまともに表示されていなかったので(普通に確認できるのは「防御力」のみ)、そういった否定的な意見には繋がらなかったのであろう。
さて、ロマ1に対する否定的な意見に関しては、ゲーム単独ではなく攻略本情報や攻略サイト情報を絡めてのものもあるので、それについてもまとめておく。
(i)ロマ1の攻略本事情
ロマ1発売後に順次発売された攻略本は徹底攻略編、基礎知識編、完全攻略編の3冊で、その後に集大成としての大事典が発売された。但し、大きく見れば攻略本という括りに入ると言うだけで、実際には初期の3冊はガイドブック(つまり、徹底攻略編は町やイベントの紹介、基礎知識編は登場人物、武器や技、術法、モンスターの紹介、完全攻略編はマップの紹介といったように3冊とも紹介のみ)であり、大事典は世界観についての設定資料集であった。
そのため、ゲームをクリアするための「攻略」という意味でこれらが直接的に役に立つのか?と言うと・・・初期の3冊はゲームをプレイする上での便利グッズ程度であり、大事典は攻略目的と言うよりはロマ1の世界観をより楽しむための嗜好品であった。
時が経って1997年に、ロマサガ3部作をまとめた大全集が発売された。
この書籍も攻略が目的ではなく、主としては世界観等についての設定資料集であった。
そして、一般的な意味での攻略情報がそれなりにまともに初めて記載されたのは2001年にWSC版が発売した際のファミ通WSやデスティニーガイドであった。
但し、そこに記載された内容はSFC版の攻略サイトで明らかにされてきた情報と類似したものにとどまっていた。
以上のようにロマ1の攻略本事情について簡単にまとめてみた。
わざわざこのようにまとめたのは、否定的な意見の中には「大事典にマスクデータが載っていたからクリアできた」のように勘違いをしているものもあったからである。
当時の攻略本には俗に言うマスクデータ等の普通にプレイしているだけでは分からないデータや仕組みはほとんど記載されておらず(防具の「重量」のみ)、そういった情報に初めて言及・公表したのは攻略サイトでした。
(ii)ロマ1攻略サイト情報の弊害
攻略サイトに掲載されている時間経過システムやサルーインのHPシステムを挙げて、「難しい」や「分かるわけがない」、「仕組みを知らないからできなかった」と言って非難している人もいる。これもおかしな話で、攻略サイト群は「クリアできないからそれらのシステムの解明に着手した」のではなく、「クリアはできるけれど、そのシステムが不明瞭・不可解だったから解明に着手した」のである。
つまり、それらのシステムのことなんて全く知らなくてもクリアはできるわけなので、こういったシステムを知らなかったからクリアできなかったという理屈は成り立たない。
即ち、クリアできなかったのは「プレイヤーの能力」が足りなかっただけである。
また、「戦闘回数を抑えないとイベントが見えないから・・・」云々等で「セーブ&ロードを繰り返すのが苦痛だ」というように非難する声もある。
これは明らかに「プレイヤーの基準」がおかしい意見・・・即ち、攻略サイトの情報を見てしまったがために生じてしまった否定的な意見である。
大事典のスタッフからの一言に「『3回目が一番楽しくなるように調整してある』(河津談)」と述べられているように、ロマ1は1回のプレイでは全てを楽しむことができないから、繰り返しプレイすることでその都度新たな出会い・発見のあるゲームを想定して作られているのである。
それにもかかわらず、攻略サイトで情報収集をした上で、最初のプレイから1回でいろいろなイベントを見ようとして、戦闘回数を抑えるためにセーブ&ロードを繰り返して「苦痛だ!」と言っている。
この様は私からすると、「戦闘回数を抑えて進める」という縛りプレイを(無自覚で)自らに課しておいて、それが「苦痛だ!」って言っているようにしか思えません。
例えるならば、「水中にいて呼吸ができない!苦痛だ!」って言っているようなもので、「何を言っているんだ?当たり前じゃん!」って私は思ってしまいます。
このような攻略サイトの情報ありきの否定的な意見については、攻略サイト管理者としては不本意でしかありません。
3.戦闘に関する否定的な意見
戦闘に関する否定的な意見は「敵の量」に関するものと「敵の強さ」に関するものの2群に大きくは分けられる。(1)敵の量に関する否定的な意見
俗に「握手会」と揶揄されるように、ロマ1の敵シンボルの多さに辟易したという否定的な意見は多い。ロマ1の敵の多さには「ロマ1の物語内の時間の進展システム」と「ロマ1のシンボルエンカウントシステム」が大きく関わっているので、それを踏まえた上でこの意見について検討する。
(i)ロマ1の物語内の時間の進展システム
ロマ1では「最近モンスターが増えたなー」と人々が異変を感じ始めた頃から、邪神側の暗躍により世界が混迷を極める頃までが描かれている。では、その物語内の時間の進展(即ち、「イベントの進展」と「出現敵編成の進展」)をフリーシナリオシステムでどのように表現したらいいのだろうか?
いくつかの可能性について考えてみましょう。
| (a)ゲームのプレイ時間で管理するシステム イベントA:プレイ時間0分から60分まで発生。 イベントB:プレイ時間240分から300分まで発生。 イベントC:イベントBにおいてある条件を満たした状態でプレイ時間360分から390分まで発生。 敵編成段階1:プレイ時間0分から45分までは敵編成レベル0~5が出現する。 敵編成段階2:プレイ時間45分から90分までは敵編成レベル1~6が出現する。 |
何もしなくてもその世界にいるだけで世界各地でイベントが発生・終了し、敵も勝手に強くなっていく。
| (b)歩数で管理するシステム イベントA:歩数1000歩まで発生。 イベントB:歩数800歩から歩数1500歩まで発生。 イベントC:イベントBにおいてある条件を満たした状態で歩数2400歩から歩数4000歩まで発生。 敵編成段階1:歩数0歩から1499歩までは敵編成レベル0~5が出現する。 敵編成段階2:歩数1500から2999歩までは敵編成レベル1~6が出現する。 |
動かなければ何も変わらないが、移動することで世界の状況が変わっていく。
これら(a)、(b)のようなシステムはある意味でロマ1のフリーシナリオシステムをさらに押し進めたもので、「戦闘に赴くかどうか」の判断さえもプレイヤーに委ねられる。
当然、順当に主人公らを育てていなければ敵が強くて全く歯が立たないという状況(詰みの状況)が起こりやすくなる。
#主人公を戦闘で全く育てなくてもロマ3のトレードみたいな感じで資産を増やして傭兵を雇用・育成・派遣するみたいな可能性もあるかもしれないが、当時のゲームでそこまでは無理だと思うので、そういった可能性は考慮しない。
そこで、次はイベントに着目した管理システムについて考えてみる。
| (c)イベント解禁制システム ゲーム開始時にイベントA(1)、イベントB(1)、イベントC(1)が発生。 イベントA(1)をクリアするとイベントA(2)が発生し、イベントA(2)をクリアするとイベントA(3)が発生。 イベントA(1)とイベントB(1)の両方をクリアしているとイベントD(1)が発生。 敵編成段階は各イベントで固定。 |
| (d)イベント達成数で管理するシステム ゲーム開始時にイベントA、イベントB、イベントCが発生。 イベントを1つクリアするとイベントD、イベントEが発生。 イベントCをクリアしないままで他のイベントを3つクリアするとイベントCは終了する。 敵編成段階はクリアしたイベントの数に応じて徐々に強くなっていく。 |
| (e)イベントポイントで管理するシステム ・イベントAは簡単だからイベントポイント1。 ・イベントBはちょっと厄介だからイベントポイント2。 ・イベントCは重たいからイベントポイント5。 関わって終了させたイベントのイベントポイントの累計によって、イベントの発生・終了、敵編成段階を管理する。 |
そこで、次は戦闘回数に着目した管理システムについて考えてみる。
当時の(今もそうかもしれないけれど)RPGでは戦闘をして主人公らを強化することは当たり前のことだったと思う。
戦闘をして経験値を稼いでレベルアップ(一般的なRPG)、戦闘をしてステータスアップ(FF2やGBサガのエスパー)、戦闘をして金を稼いでアイテムを購入して強化(GBサガの人間)、戦闘をして肉を食べて進化(GBサガのモンスター)等、強化の仕方は様々であるがいずれも戦闘を通してのものである。
ロマ1もその点は当たり前のこととして踏襲しているので「主人公らが戦闘をすること」は前提となる条件であったであろう。
従って、先に述べたロマ1のフリーシナリオシステムが「ラスボスまでに何をして過ごすかは自由」であることに「主人公らが戦闘をすること」も加えれば、ロマ1とは「主人公らが戦闘をした上で、ラスボスまでに何をして過ごすかは自由」というシステムのゲームということになる。
それならば、戦闘回数で物語内の時間の進展を管理するというのは理に適った方法の一つと言える。
| (f)戦闘回数で管理するシステム イベントA:戦闘回数0回から50回まで発生。 イベントB:戦闘回数100回から200回まで発生。 イベントC:イベントBにおいてある条件を満たした状態で戦闘回数300回から350回まで発生。 敵編成段階1:戦闘回数0回から50回までは敵編成レベル0~5が出現する。 敵編成段階2:戦闘回数50回から100回までは敵編成レベル1~6が出現する。 |
なぜなら、必ず戦闘をこなすことになるので、それに伴って主人公らが強化されるからである。
ただ、ロマ1では「イベントの進展」に関しては単純に戦闘回数のみで管理されているのではなく「時間経過ポイント」のチェックを通して初めて物語内の時間が進展するようになっている。
| (g)戦闘回数と時間経過ポイントで管理するシステム イベントA:戦闘回数0回で発生し、戦闘回数50回以降に時間経過チェックをすると終了。 イベントB:戦闘回数100回から199回までに時間経過チェックをすると発生し、戦闘回数200回以降に時間経過チェックをすると終了。 |
ただ、場合によっては「時間経過ポイントを踏んでいないため物語内の時間が進展しない」という状況も起こりえてしまう。
一方で、「出現敵編成の進展」は戦闘回数のみで管理されている。
つまり、戦闘回数に応じて出現しうる敵編成レベルが決まっていて、戦闘回数が増えれば出現しうる敵編成レベルも高くなるのである。
このシステムには次の二つの利点がある。
一つは、「邪神の復活が迫っている演出」効果である。
つまり、邪神の復活が迫って邪気が徐々に世界中を覆っていくことで、それに伴って徘徊するモンスターたちも強力になっていく状況を演出することに役立っている。
一方で、出現する敵編成は敵系統と戦闘回数にしか依存しないため、世界中どこでも同じモンスターが出現しうるという不自然な状況(バルハラントに寒さに弱い敵が出現して地相ダメージを受ける等)が起こってしまう。
#容量が許したならば、それぞれの場所ごとで敵編成レベルを設定するのが理想であったように思う。
もう一つは、フリーシナリオシステムの実現である。
従来のRPGでは各地に出現する敵編成が決められているため、必要に応じて戦闘回数を重ねてレベルアップをする作業が必要だった。
#そのため、イベント進行の適正レベルが記載されている攻略本もあった。
一方で、ロマ1ではどこにいっても敵の強さは戦闘回数依存の一律であるから、イベントを進めるためのレベルアップが基本的には不要である。
故に、主人公の強さと敵の強さを考慮することなく任意のイベントに関わることができるのである。
#途中に強力な敵もいるがそれを倒すかどうかは自由、倒せなくても別ルートがある、そこらのボスは弱いといった要素もあるので、常にイベントの攻略にあたることができる。
なお、eicoさん情報によるとミンサガでは以下のようなシステムにブラッシュアップされたとのことである。
| (h)戦闘勝利ポイントと時間経過ポイントで管理するシステム ・敵編成ごとに強弱に応じた戦闘勝利ポイントが設定されていて、戦闘に勝利した場合のみ戦闘勝利ポイントを獲得することができる。 ・原則的には町に入ると時間経過チェックされる。 ・戦闘勝利ポイントの累計と時間経過チェックによってイベントの発生・終了を管理する。 ・戦闘勝利ポイントの累計によって敵編成段階を管理する。 |
(ii)ロマ1のシンボルエンカウントシステム
ロマ1の「イベントの進展」は戦闘回数で管理されているので物語内の時間を進めるためには戦闘をする必要がある。故に、製作者側としてはプレイヤーに自然に戦闘回数を加算してもらう必要があった。
そこで導入されたのがロマ1のシンボルエンカウントシステムだったのだと思われる。
従来のRPGは主としてランダムエンカウントや歩数エンカウントであった。
そういったエンカウントシステムをロマ1に導入したらどうなるかと言うと、
・セーブ&ロードを駆使すればザコ戦を回避して進むことができるので、戦闘回数不足でイベントが進行しないという状況が起こりやすくなる。
・逃げても進むことができるので、主人公らが強化されないまま敵だけが強くなるという状況が起こりやすくなる。
というゲームの進行に関わる問題点が生じてしまうのである。
このような問題点を起こりにくくするために導入されたのがロマ1のシンボルエンカウントシステムだった。
つまり、
| ・回避しきれないようにある程度多くの敵シンボルを配置する。 ・戦闘から逃げた場合は敵シンボルが消えない。 |
これによりプレイヤーは普通にプレイしていたら必ずある程度の戦闘をこなすことになるし、なおかつ敵シンボルを消すために戦闘に勝利せざるをえなくなる。
即ち、ロマ1のシンボルエンカウント制は「強制的な戦闘回数の加算」と「強制的な主人公らの強化」を意図したものなのである。
なお、シンボルエンカウントと言えば、
・戦闘するかどうかも自由に選べる。
・戦闘する相手(敵系統)を自由に選べる。
といった利点を想起する人もいるであろうが、ロマ1についてはまだその域にまでは達していない。
#普通は敵シンボルを回避しきれないし、敵系統の違いによる倒しやすさの違いもほとんど無い。
そういった利点を活かせるシステムは後作のロマ2から取り入れられている。
(iii)ロマ1の敵の多さについての見解
(i)(ii)で述べたロマ1で導入された二つのシステムからすると、ロマ1のフリーシナリオシステムを機能させるためにはプレイする中で自然に戦闘回数を加算してもらう必要があったわけなので、「敵が多い」とか「シンボルエンカウントなのに避けられない」といった意見が挙がるのは当たり前と言えば当たり前のことである。つまり、製作者側としては意図的にそのように作っているのだから。
しかしながら、これでは否定的な意見に対する反論にはならないので、視点を変えて、どうして「敵の多さ」が否定的な意見に繋がっているのか?について検討してみる。
(a)視覚的な敵の多さ
「画面いっぱいに敵シンボルがいる」という視覚的な敵の多さに問題がある(受け付けられない)のだろうか?ただ、私自身は発売当時から一度もそのように思ったことは無い。
もしかしたら、私はロマ1以前に例えばボコスカウォーズのような「画面いっぱいに敵シンボルがいる」ゲームを経験していたので、敵の多さに対する耐性ができていたからなのかもしれない。
それならば視覚的な問題についても「プレイヤーの能力」(敵の多さに耐性がついている)と「プレイヤーの基準」(過去作に比べたら取り立てて多いわけではない)で片付くことになる。
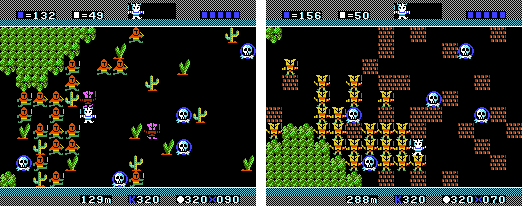
#出典:ボコスカウォーズ,アスキー.
しかしながら、私としては視覚的な問題はロマ1における「敵の多さ」に対する否定的な意見の本質ではないと思っている。
なぜならば、視覚的な敵の多さに本当に問題があるのならば、ロマ1よりも圧倒的に画面いっぱいに敵が出現するヴァンパイアサバイバーズが多くの人に受け入れられるはずがなかったと思われるからである。
では、ロマ1における「敵の多さ」の問題の本質とは何なのか?
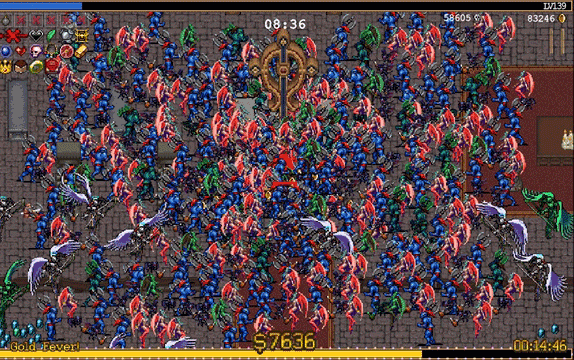
#出典:ヴァンパイアサバイバーズ,Poncle.
(b)エンカウント密度
「敵の多さ」・・・「多さ」と言うくらいだから「量」的な側面なのだとすると、その量はどのように測られるのか?ゲーム開始からエンディングまでの戦闘回数の累計だろうか。
それとも、1フロアあたりの戦闘回数だろうか。
はたまた、1時間あたりの戦闘回数だろうか。
ゲームごとに関わる要素が異なっているので一概には言えないだろうけど、ロマ1について言えば「各フロアに出現する敵シンボル数は決まっていて、それらが最初から配置されていて、敵シンボルの移動規則は基本的には主人公シンボルめがけて迫ってくる設定になっている」ので、必然的に敵シンボルが密集することになる。
それ故に、その密集した敵シンボルと戦う場合には瞬間的なエンカウント密度は高くなる。
この「瞬間的なエンカウント密度の高さ」が「敵の多さ」ならば、「ロマ1は敵が多い」はその通りなのかもしれない。
ただ、それは「各フロアに出現する敵シンボル数は決まっていて、それらが最初から配置されていて、敵シンボルの移動規則は基本的には主人公シンボルめがけて迫ってくる設定になっている」ことの一側面でしかない。
つまり、逆に言えば、その「瞬間的なエンカウント密度の高さ」を越えれば、究極的にはエンカウント可能性が0になるのである。
例えば各フロアにおいて、従来のRPGならばダンジョンで迷えば迷うほど無制限に戦闘回数が増えることになるが、ロマ1ならば迷いに迷ったとしても初期配置されている敵シンボルを全て殲滅すればその後は戦闘をすることなく探索することができる。
また、ロマ1ではフロア切り替えで敵シンボルが再配置されるのであるが、従来のRPGのようなフロア切り替えを含むような迷路はほぼほぼ無いので(ひたすら降りるか、ひたすら登る)、それが負担になるような状況はそうそう起こらない。
従って、ロマ1では瞬間的なエンカウント密度が高くなる場合はあるものの、押しなべて均してみれば、トータルでのエンカウント密度は一般的なゲームと大差は無いのではないだろうか。
#個人的には、エンカウント率の高いランダムエンカウントの方がよっぽど厄介だった印象があるので、そういう意味では「プレイヤーの基準」(過去作に比べたら取り立ててトータルでのエンカウント密度が高いわけではない)の問題と言うこともできる。
(c)一戦闘ごとの面倒さ
実のところロマ1における「敵が多い」ことの本質的な問題点・・・それは文字通り「質」的な側面にあるのではないだろうか。つまり、実利的な問題点である「1回戦闘を行うことの面倒さ」が根本の原因だと思われるのである。
具体的には、ロマ1ではパーティー人数が多いほど毎ターンの行動決定の手間が増えるし、隊列が乱れた場合には思うように行動決定をすることができずに行動変更や列移動の手間が増えるということである。
当然、その手間の分だけ戦闘時間も長くなることになる。
それを毎戦闘こなすとなると面倒だと思うのは当然であろう。
しかしながら、ロマ1はそういった面倒さを強制しているわけではない。
それを面倒だと感じたのならば、そうならないようにプレイヤーが工夫をすればいいだけのことである。
具体的に言えば、私が早くから本サイトで初心者向けに書いていた「少人数の勧め」のように一人旅にすればいいのである。
戦闘の面倒さの解消のために一人旅をしてみることで一戦闘が思いの外サクサクと消化されていくことに驚くだろうし、それ以外のメリット(船賃安い、装備の集中、成長の集中)にも自然と気付いて幸せ気分が倍増するのである。
従って、「一戦闘ごとの面倒さ」が原因で「敵が多い!」と非難している意見については、その原因を解消しようとしないで不満を言っているだけ・・・つまり、プレイヤー側の問題解決能力が無いだけなので、「プレイヤーの能力」の問題と言えるのである。
(iv)その他の発展途上だったシステム
「敵が多い」や「シンボルエンカウントなのに避けられない」という意見に関わって、「移動の速さが遅い」、「ダッシュができない」、「敵が一斉に追いかけてくる」といった否定的な意見も見られる。こういった意見は典型的な「プレイヤーの基準」の問題ではないだろうか。
◆移動の速さ
先に発売されたFF4を踏襲しているのでロマ1が特別に遅いわけではない。
徒歩は同じ速さだし、乗り物(FF4はチョコボ、ロマ1は馬や馬車)に乗ったら速くなる(倍速になる)というのも同じである。
参考:ゲームのキャラはSFC時代に加速する
◆ダッシュの有無
スクウェアの主要RPGを当時からプレイしていれば分かることだが、徒歩にダッシュ機能がついたのはロマ1の後作のFF5のアビリティー「ダッシュ」からである。
◆敵シンボルの移動規則
後作のロマ2では主人公シンボルが敵シンボルにある程度接近することで敵シンボルが動き出すという仕組みになっている。
今まで当たり前に有ったものが無くなったのならば不便に思うかもしれないが、「FF4等のロマ1より前の作品」→ロマ1というように発売時系列順にプレイしていれば、上記のようなことなど取り立てて不満に思うようなことではないと思う。
つまり、上記の点に不満があってロマ1を非難するのは、後年のより便利になったゲームを基準としての評価でしかないと思われるのである。
後年のより洗練されたシステムが実装されたゲームと比べたらロマ1に不便なところがあることを否定することはできない。
しかしながら、ゲームの進化の時系列を鑑みると、ロマ1が発売当時に取り立てて不便だったわけではないということも事実である。
(2)敵の強さに関する否定的な意見
敵の強さに関しては「一部のザコ敵が強い!」や「一部の固定敵が強い!」という特定の敵の強さに関するものと、「戦闘をしていると敵が強くなるのが嫌だ!」という出現敵編成の進展システムに関するものがある。(i)特定の敵が強いのが嫌だ!
◆一部のザコ敵が強いロマ1では序盤から終盤まで厄介なザコ敵(瞬殺してくる敵)が出現しうるのは事実である。
しかしながら、実際にプレイしていてそれがゲームを進める上で大きな障害・問題点になっているのだろうか?
と言うのは、あくまで出現しうるだけで絶対に倒さないといけない敵ではないし、どこでもセーブ&ロード機能もあることも考慮すれば、実際には取り立てて問題視するようなことでもないからである。
そもそもザコ敵として異常に強い敵が出るのはロマ1に限った話ではなく、先に発売されたGBサガ1では朱雀、GBサガ2ではハニワが唐突に出現していた。
そして、GBサガ1・2にもどこでもセーブ&ロード機能があったので、こまめにセーブをする(それこそ数歩歩いたらセーブをする、戦闘が終わったらセーブをする)のは結構当たり前のことだったと思われる。
従って、GBサガ1・2を経てのロマ1というプレイ順ならばザコ戦でも唐突に強い敵が出現しうるというのは当たり前のことだし、そういう日常茶飯事の事態に対しての保険の意味も込みでこまめにセーブをするのも当たり前のことなので、「一部のザコ敵が強いからダメ!」という意見は「実際には全く問題では無いのに、それを問題だと思い込んでしまっている意見」にすぎないのである。
#先に発売されたFF4はセーブポイント制だった。ロマ1もセーブポイント制だったら唐突に出現する一部の強いザコ敵は大きな障害・問題点となっただろう。
#また、ザコ敵が強いという話ならば、FF4やGBサガ1・2のラストダンジョンのザコ敵のほうがロマ1よりもよっぽど凶悪だと思う。
◆一部の固定的が強い
一部の強い固定敵として名前が挙がるのは序盤の恐竜(トリケラトプス)と偽テオドール(イフリート)である。
まず、序盤の恐竜(トリケラトプス)については、戦っても歯が立たないのは事実であるが、そもそも戦わなくてもいいし、避けやすいように恐竜シンボルの移動の速さは「鈍足」に設定されている。
恐竜の巣に突っ込んで恐竜シンボルに囲まれた状態でセーブをしてしまって詰んだのならば、それは容易に予想できる最悪の事態に気付かずに安易にセーブをしてしまったプレイヤーの自業自得である。
また、偽テオドール(イフリート)については「イフリートで詰んだ」という意見が散見される。
しかしながら、倒せないならば倒さなくても問題は無い。
バイゼルハイムから出ればいいだけである。
つまり、実際には詰んでいるわけではないのに詰んでいると誤解していたり、そこで諦めてしまっていたり、「倒さないと気が済まない!」という強迫性障害等だったりするのである。
ロマ1における強いザコ敵と強い固定敵・・・それらの存在がゲームを進める上での実質的な障害になっているわけではないにもかかわらず、多くの人がその強さを印象付けられているということは、それらの敵が香辛料(一味違うインパクト)としての役割を見事に果たしているということである。
決して劇物ではなく、あくまで香辛料である。
劇物の摂取はアウトであるが、香辛料の摂取は好きか嫌いかである。
従って、「敵が強いからダメ!」なのではなくて「敵が強いから私は嫌い(私には合わない)」という話になるのである。
(ii)出現敵編成の進展システムが嫌だ!
ロマ1の出現敵編成の進展システムは戦闘回数に応じて出現する敵編成レベルが高くなる(強い敵が出現する)というものである。これはロマ1の根本的なルールなので、「このシステムが嫌い!」と言うならば、それはあなたには「合っていない」というだけの話である。
従って、「このシステムが嫌いだからダメ!」というのは理屈としておかしいことになる。
一方で、「このシステムが嫌い!」という意見には「常にザコ敵が味方パーティーよりも強いから嫌だ!(味方パーティーよりも弱いザコ敵と戦いたい!)」という意味合いも込められているように思う。
仮にそうだとすると、それはおそらく「味方パーティーが戦闘回数に相応しいステータス値(装備も含む)にまで鍛えられていない」ということを意味するであろう。
そういう状況に陥りたくないのならば、ロマ1の戦闘は全て成長の場と捉えて、毎戦闘しっかりと戦って地道に鍛えていくようにすれば、自ずと戦闘回数に相応しいステータス値に育っていくだろう。
また、そういう状況に陥ってしまったとしても、強力な技を使うなり何なりで、とにかく戦闘に勝利して鍛えることを繰り返せばいい。
#味方のステータスに対して敵編成レベルが高いほど成長しやすいので、強い敵と戦っていれば戦闘回数に相応しいステータス値に追いつきやすくなる。
よって、「味方パーティーが戦闘回数に相応しいステータス値(装備も含む)にまで鍛えられていない」という状況に陥ったのならば、それはプレイヤーの戦闘のこなし方に落ち度があった・・・つまり「プレイヤーの能力」の問題ということである。
4.全体的な粗さに関する否定的な意見
ロマ1に対する否定的な意見はいろいろあるけれど、既に述べた「分からない」や戦闘関連の意見も含めてそれらを総括すると、ロマ1は「粗雑で不完全」だから否定的に捉えられているようである。・・・これは面白い事実である。
と言うのは、ロマ1好きにとっては「ロマ1は粗雑で不完全」というのは誉め言葉だからである。
但し、誤解してほしくないのは、ロマ1好きは決して単純に「粗雑で不完全」なゲームを賛美しているというわけではない。
つまり、ロマ1に関しては「粗雑で不完全」なところがロマ1の魅力と面白さに直結しているのである。
と言うことで、本章ではロマ1の「粗雑で不完全」な点が非難されるに値するのかについて検討する。
(1)不完全さ
ロマ1を「未完成」と非難する声は多い。WSC版発売の際には公式(スクウェア,2001)が「デステニィストーンを巡る8人の物語。10年の時を経て完成形へ…。」 なんて見出しを付けてしまうくらいだから、SFC版を「未完成」と言われてしまうのは仕方がないことなのかもしれない。
ただ、私としてはSFC版ロマ1に対して「未完成」という言い方をするのは違うと思っている。
なぜなら、製品として発売されていて、プレイして楽しむことができて、エンディングを迎えることができる作品に仕上がっているので、「未完成」ではなく十分に「完成している」と言えるからである。
しかしながら、私はSFC版ロマ1を「完全」だと思っているわけでもない。
つまり、私の認識としては、SFC版ロマ1は「製品としては完成しているが、内容は不完全」である。
では、私はどうして「不完全」だと思っているのか?
それは未使用キャラクター、未使用アイテム、未使用地名、未使用台詞、未使用モンスターといったプログラムのデータ上には存在するものの実際には使用されなかったものの痕跡が多数存在するからである。
「これらが実装されていたら・・・」という思いが少なからずあるので「不完全」だと思っているのである。
一方で、「未完成」だと指摘する理由には、
・攻略サイトで挙げられている上記のような未使用データのことだけでなく、プログラムミスで設定がおかしくなっていると思われる点(バグも含む)を修正してほしい。
・喋らない人や、入れない場所等(シェラハイベントを含む)のゲームをプレイしていて思わせぶりなところに内容を実装してほしい。
・プログラムのデータ上に痕跡はなくとも、開発者側が実装したかった要素(構想していたイベントや強いサルーイン等)を全て実装してほしい。
・「デステニィストーンが揃わないのはおかしい!」という開発者側の意図を覆させるような要求。
等、さらに様々な要素が理由になっているようである。
では、このように「不完全」・「未完成」とロマ1経験者に思われている点が非難されるに値するものなのだろうか?
私としては「否!」である。
なぜなら、SFC版ロマ1は確かに納期や容量の都合により開発者側としても万全の状態で「完成」として発売されたものではなかったのかもしれないが(大事典を参照)、結果として「分からない世界を自由に冒険する」というゲームの柱となるコンセプトと「不完全」・「未完成」と思われている点が奇跡的なバランスで噛み合っていて、「不完全」・「未完成」と思われている点がロマ1の「分からない世界」を押し広げ、深みを持たせるとともに、「自由に冒険する」ことに駆り立てる原動力として機能しているからである。
この効果は開発者側が意図したものではなく偶発的産物だったのかもしれないが、ロマ1の持つ「不完全さ」・「未完成さ」は間違いなくロマ1の魅力と面白さを構成する要素の一つになっているのである。
言うなれば、SFC版ロマ1の「不完全さ」は「詫びさび」である。
つまり、一部分の不完全なところだけに焦点を当てたら「ダメ!」となってしまうかもしれないが、そうではない部分に補って余りある良さ・魅力を感じているから不完全なところも受け入れられるということである。
#「不完全だからいい」のではなく「不完全でもいい」という心境である。
それ故に、私としてはSFC版ロマ1を「不完全」だと思ってはいるものの「完全」を望んでいるわけでもない。
例えば、子どもの絵は拙く、下手で、滅茶苦茶かもしれないけれど独特の良さ・面白さ・魅力があると思う。
知らない人が見たら「下手くそ!」と思って一蹴されるかもしれないけれど、その子の親にとってはかけがえのない作品かもしれない。
そんな絵に対して大人が「ここがダメだからここはこうして」、「ここはこう直して」、「ここにはこういうのを描き加えて」と干渉してしまったら、途端にその絵はもはやその子の作品ではなくなり、全く面白みの無い作品になってしまうだろう。
その作品を何も知らない人が見たら上手な作品に見えるようになったのかもしれないが、その子の親としてはそんな作品など嬉しくも何ともないのではないだろうか。
・・・言わずもがな、元の子どもの作品がSFC版ロマ1である。
完全版を目指して手を加えてしまったら、途端にSFC版ロマ1が持っていた独特の良さ・面白さ・魅力は失われてしまうのである。
#WSC版はその実例になっていると私は思っている。
(2)バグ
実際のところ、開発者側が意図していない挙動(バグ)が普通にプレイしていてもいくつも発生しうるのがロマ1である。バグと言うと一般的に欠陥であり、ネガティブに捉えられるだろうが、ロマ1については「火事と喧嘩は江戸の花」の如くで、もはや「バグと不完全はロマ1の花」と言っても過言ではないように思う。
と言うのは、ロマ1において発生するバグは発売当時からはゲーム雑誌に「裏技」として紹介されていたので、バグであってもロマ1ユーザーの間では基本テクニックとして周知されていた。
そしてネット時代に突入すると、攻略サイトを通してさらなる多くのバグ技が確立されたことでゲームの遊び方の幅がさらに広がったのである。
中でもレイディバグは「バグを攻略に利用する」というよりは「バグそのものを楽しむ」というバグ技であり、レイディバグ自体がロマ1の遊び方の一つとして今も位置付いている。
このように「嘘も貫き通せば本物になる」の如く「バグも確立されたら仕様になる」で、ロマ1のバグはもはや仕様である。
まだ未解明のバグも当然あるが、それらにも(無限の?)可能性が詰まっているのである。
故に、そういったバグを理由にロマ1を「ダメ!」と言うのは無粋であろう。
(3)バランスの悪さ
否定的な意見には「バランスの悪さ」を指摘するものがあるが、主語が書かれていないので何のバランスについてなのかは分からない。そこで、本稿では「全体的な難易度バランス」、「敵シンボル数と戦闘回数のバランス」、「サルーインHPシステムの調整バランス」等、その良し悪しを一概には言えないものについては一旦置いておくことにして、明らかに言える以下の3点についてのみ言及しておく。
◆ザコ敵とボス敵の強さのバランス
ロマ1のザコ敵は「出現敵編成の進展システム」で管理されているので戦闘回数に応じて出現する敵編成レベルが高くなる(強い敵が出現するようになる)のであるが、一方のボス敵は「固定敵編成」として個別に設定されているので時間経過によって出現する敵が変化することは無い。
その結果、ボス敵よりも道中のザコ敵の方が強いという逆転現象のような事態が往々にして起こってしまう。
これはこれで「味がある」と言えないこともないが、物語設定面ではボス敵とザコ敵の主従関係に不自然な感じがするし、実際のプレイではボス敵の弱さに肩透かしを食らったような釈然としない気持ち(物足りないような気持ち)が生じてしまう。
容量が許すならば、ボス敵もザコ敵と同様に戦闘回数に応じてより強い敵編成に変化していったほうが面白かったのかもしれない。
◆味方側と敵側での術法系攻撃ダメージの脅威度のバランス
例えばドラクエ1~4、FF1~4、GBサガ1・2、・・・これらロマ1よりも先に発売されたRPGでは味方側と敵側でHPのスケールが同じであった。
つまり、一部例外はあるにせよ、基本的には「双方ともにHPが3桁」もしくは「双方ともにHPが4桁」であった。
それに対してロマ1のHPスケールは「味方側のHPが3桁」で「敵側のHPが4桁」なのである。
ロマ1はいろいろ新規のシステムを導入して攻めていたが、味方側と敵側のHPスケールの違いでも攻めていたのである。
ロマ1ではこのようなHPスケールシステムを採用した上で、味方側と敵側で「使用する術法」と「術法系攻撃ダメージ算出式」が同じだったために、誰しもが「敵が術法で攻撃してくると味方側が壊滅的なダメージを受けて戦慄させられる一方で、味方が同じ術法で敵側を攻撃しても大してダメージを与えられずにガッカリさせられる」という経験をすることになったのである。
では、どうして物理系攻撃ではそういったバランスの悪さの印象があまり無いのかと言うと、物理系攻撃については味方側と敵側で同じ「物理系攻撃ダメージ算出式」を使用しているものの、「使用する攻撃」の多くは味方側と敵側で異なっているからである。
具体的に言うと、味方側の武器・技の攻撃力は高く(6~50)、敵の特殊攻撃の攻撃力は低く(おおよそ4~7)設定されているので、それにより味方側の物理系攻撃ダメージは大きくなって、敵側の物理系攻撃ダメージは抑えられるようになっているのである。
味方側と敵側での物理系攻撃ダメージの脅威度のバランスを「攻撃力の違い」で調整しているのだから、容量が許すならば術法系攻撃についても「攻撃力の違い」で・・・即ち、味方用術法(攻撃力が高い)と敵用術法(攻撃力が低い)を分けて設定すれば、味方側と敵側での術法系攻撃ダメージの脅威度のバランスを取ることができたであろう。
◆物理系攻撃と術法系攻撃のダメージのバランス
ロマ1では一般に物理系攻撃ダメージに対して術法系攻撃ダメージは圧倒的に低い。
ダメージだけを比べるならば、一般に「使用回数制限の有る術法攻撃のダメージ」が「使用回数制限の無い武器の通常攻撃のダメージ」に劣るので、HPを削るという観点では味方側の術法攻撃は弱いと言わざるを得ない。
この物理系攻撃と術法系攻撃のダメージのバランスの悪さについても、上記の「味方用術法(攻撃力が高い)と敵用術法(攻撃力が低い)を分けて設定する」を行えていたら、併せて改善できていたであろう。
以上のように、上記3点については「バランスが悪い」と言われても仕方が無いのかもしれない。
しかしながら、そのバランスの悪さもロマ1の不思議な魅力の一因にはなっているようにも思う。
(4)一部の詰み
ロマ1において進行不能になる場合はいくつかある。その多くはプレイヤーの自業自得や勘違い(「プレイヤーの能力」の問題)であるが、
・フリーシナリオシステムを謳っているのに時間経過の関係で進行不能になる場合がある。
・通常プレイをしていても発生するバグ(海賊のアジト入り口)で進行不能になりうる。
という2点については擁護できない問題点(ゲームの欠陥)だと思う。
5.その他の否定的な意見
(1)武器を外す
「武器を外すと武器レベルがリセットされて、覚えた技を忘れてしまう」ことに対する否定的な意見がある。このシステムについては、武器装備欄は8枠もあるわけなので、鍛えた武器を外さなければいいだけのことである。
お遣いイベント絡みで鍛えた武器を外さなければならないような場合もあるかもしれないが、敵編成レベルに応じて武器レベルの上がりやすさは変わるので、実際のところ武器レベルを上げ直すことはさほど苦にはならない。
また、プレイヤー側にとってはメリットが無いように思われるこのシステムであるが、開発者側としてはやむを得ない事情もある。
つまり、鍛えた武器レベル履歴も保存するとなると、それだけ記録容量を確保しなければならなくなるのである。
ロマ1ではゲームプレイ中のステータスにおける対の術法系統(例えば「火」と「水」)の数値は別々に管理されているのであるが、セーブする際には対の術法系統でまとめて一つの数値で管理することで、記録するデータ量のエコ化を図っている。
既に圧縮して記録容量の中に押し込んでいるのに、それに加えて鍛えた武器レベル履歴まで保存するのはさすがに厳しいであろう。
(2)お金の上限
「探索中にお金が持ちきれなくなる」や「ジュエル換金の不便さ」といった所持金システムに関する否定的な意見もある。ロマ1の所持金システムは特異であるが、わざわざ導入してあるからには何かしらの理由があるはずである。
◆やむを得ない事情?
(1)で述べた「武器を外すと武器レベルがリセットされてしまう」ことのように、開発者側のやむを得ない事情があるのだろうか?
つまり、お金の上限が9999金なのは、お金の表示上限が4桁だからなのだろうか?
試しに数値をいじってみた結果、下図のようにお金5桁は問題無く表示された。
即ち、開発者側は意図的に9999金にストッパーを設定しているということである。
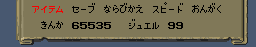
#お金は5桁表示されるが、ジュエルは2桁(99個まで)の表示上限がある。
また、所持金の内部的な仕組みとしては「XX YY ZZ」の3つの数値の内、「XX YY」で金、「ZZ」でジュエルを管理している。
3つの数値を使ってお金を管理するにしても、データ容量が厳しいならば「XX YY ZZ」で金の管理としたほうがエコなはずである。
それにもかかわらず、所持金ストッパーや両替のプログラムに容量を割いてまでも、ロマ1ではこの特異な所持金システムを実装しているということになる。
◆開発者側が表現したかったもの?
ロマ1がわざわざ特異な所持金システムを実装しているのは、それによって開発者側が表現したかったものがあるということだろうか。
そうだとすると、順当に考えれば、開発者側は
| ・財布(お金入れ)の容量上限 ・お金の両替システム |
まず「財布(お金入れ)の容量上限」については、「金貨をそんなにたくさん持ち歩けるのか?」という「リアリティーの追求」を目的にしたもののように思われるのであるが、果たして本当にそうだろうか?
仮にそうならば、「パーティー人数が多い方がより多く持てる」とか「力の強い者の方がより多く持てる」とか、そういったリアリティーは欠如しているので、中途半端と言わざるを得ない。
そこで、「リアリティーの追求」ではない別の目的の可能性について検討してみた結果・・・「旅行感の演出」を思いついた。
私の経験則に基づく事例であるが、例えばマイカーで旅行に行く場合には荷物の容量のことなど気にせず出発するのであるが、海外旅行に行く場合にはお土産を持ち帰ることを考えてキャリーバッグの中にできる限り空きスペースを作ってから出発する。
つまり、ロマ1のダンジョン探索とは言わば(海外)旅行に行くようなものなのではないだろうか。
良く言えば、「旅先に魅力的なものがいっぱいあったとしても、持てる量には限りがあるから、そういう先のことを見越した上で出発しましょう!」という旅行に関わる教訓が込められていると言えるのかもしれません。
次に「お金の両替システム」については、「量が大きくなったら上位単位に切り替える」という理念は至極もっともなことだと思う。
しかしながら、ロマ1の「お金の両替システム」は両替の方法に大きな問題があると言わざるを得ない。
一般に普及している「物」と「金」を要素とする交換の規則は以下の3つのうちのいずれかになるだろう。
| ・「物」と「物」(物々交換) ・「物」と「金」(購入と売却) ・「金」と「金」(本来の両替) |
| ・(「金」+「物」)と「金」(ロマ1の両替) |
#具体的な場面を挙げるならば、9999円とチロルチョコを1個持って店に行って、「これを1万円札と小銭に交換してくれ!」というようなものである。
以上をまとめると、ロマ1の所持金システムとは、開発者側が「財布(お金入れ)の容量上限」と「お金の両替システム」を表現したかったのかもしれないが、それならばせめて(お金の5桁表示は可能なのだから)お金の所持上限を10000金にして、その10000金を無償で1ジュエルに両替できるシステム(「金」と「金」を交換する本来の両替)にしていればまだ納得できただろが、実際にはお金の所持上限が9999金で、物を売らなければ両替できないという不便で不自然なシステムになっているので擁護のしようがないということである。
(3)文字の大きさ
「漢字だけ大きいから読みにくい」という文字の大きさに対する否定的な意見がある。この意見については、「漢字だけ大きい」という点は事実であるが、「だから読みにくい」という点に関しては疑問である。
少なくとも私はそんなことを思ったことは一度も無い。
思うに、そもそも日本語を書く時には「漢字は大きく、仮名は小さく」が基本であるから、ロマ1でも取り立てて違和感があるとは思わなかったのだと思う。
そこで、ロマ1の文字の大きさについて具体的に検討してみることにする。
◆漢字と仮名の大きさ
漢字と仮名の大きさについて、 【国語編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説(文部科学省)p.91には以下のように説明されている。
| 漢字や仮名の大きさとは、漢字と漢字、漢字と仮名、仮名と仮名との相互のつり合いから生じる相対的な大きさのことである。 画数の多い文字ほど大きく書き、画数の少ない文字ほど小さく書くと、並べたときに読みやすい文字列になる。 一般的に、仮名は漢字よりも小さく書くとよいと言われるのは、仮名が漢字よりも構成要素が少ないことによるものである。 |
また、美文字登山さんの「漢字とひらがなで字の大きさに変化をつけて、バランスの取れた綺麗な字を書く方法」によると、文字の大きさは
| 漢字:カタカナ:ひらがな=10:8:7 |
これを参考にすると、ロマ1の文字の大きさは
| ・漢字:縦11×横11 ・仮名:縦8×横7 |
従って、「漢字だけ大きい」から「読みにくい」というわけではないと思われるのである。
参考画像:

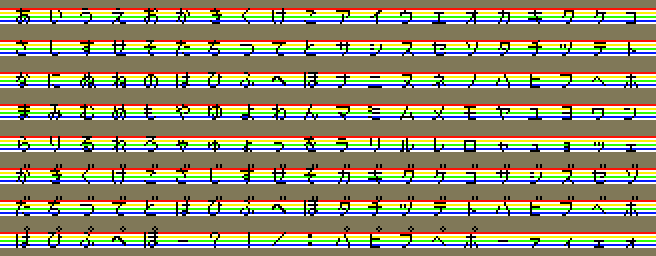
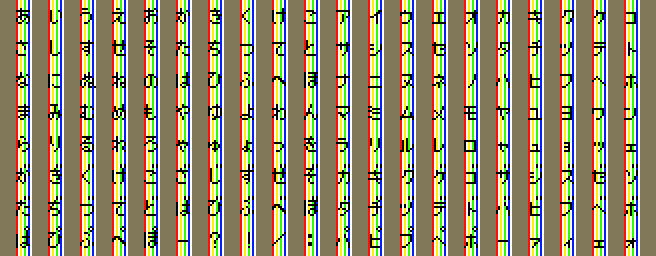
◆どうして読みにくいという意見が出るのか?
上述した私の意見を受けて、eicoさんもこの話題について検討してくださった。
以下はeicoさんのコメントの概要である。
まず、ゲームカタログ@wikiでなされている文字の大きさに対する指摘を次の2点に要約している。
・ゲームバランスの問題点の中で、フォント格差があり読みにくいと指摘。
・WSC版でのフォント格差是正を改良点と評価。
次に、「フォントバランスが悪いのかどうか?」について検討するために、
ロマサガ1、 ロマサガ2、 聖剣2、 クロノトリガー、 タクティクスオウガ、 FF7
上記の7タイトルにおける文字を見比べて、
・仮名より漢字フォントの方が大きいことは共通。フォント格差はまちまち。
・縦の列が揃っているもの(ロマサガ2、聖剣2、クロノトリガー、Tオウガ)と、揃ってないもの(ロマサガ1、FF7)がある。
という違いがあったことを指摘している。
さらに、上記の2点目について、美文字登山さんの「漢字とひらがなで字の大きさに変化をつけて、バランスの取れた綺麗な字を書く方法」の「4.小さくした字の前後はスペースを詰める」で述べられている「原稿用紙に書いたイメージと平仮名を少し詰めたイメージの対比」を視点として、さらに以下のように分類を行っている。
・縦の列が揃っている(原稿用紙に書いたイメージ):ロマサガ2、聖剣2、クロノトリガー、Tオウガ
・縦の列が揃ってなくて、平仮名を少し詰めたイメージ:FF7
・縦の列が揃ってなくて、詰め方がまちまち:ロマサガ1
このeicoさんの考察は、「ロマ1の文字が読みにくいと言われてしまう原因が『漢字だけ大きい』ということではないならば、何が原因で読みにくいと言われてしまうのか?」ということに関するものである。
先に引用した【国語編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説(文部科学省)p.91の「漢字や仮名の大きさ」についての説明の続きは以下のようになっている。
| 配列に注意してとは、行の中心や行と行との間、文字と文字との間がそろっているかなど文字列及び複数の文字列に注意してということである。 読みやすい文や文章を書くには、一文字一文字を整えることに加え、文字の集まりという面から整えることが重要である。 したがって、書き出しの位置を決めること、行の中心に文字の中心をそろえるように書くことなどが求められる。 字間、行間、行の中心を扱う配列の学習において、児童は、文や文章など文字数の多い教材で学習することになるため、 毛筆を使用する場合は、小筆の使用にも配慮する必要がある。 |
そして、上記の記述を観点としてeicoさんの議論を補足すると、
・「行間」については、ロマ1は問題無いと言ってよいだろう。
・「行の中心」については、eicoさんが挙げてくれたタイトルだとロマ1とクロノが下揃え、他が中央揃え。
こういった要素も読みやすさに関係すると思われる。
◆WSC版は読みやすい?
私はSFC版しか関心が無いから気に止めていなかったけれど、ゲームカタログ@wikiによるとWSC版の改良点として「文字サイズが漢字もそれ以外も同じ大きさに統一され、読みやすくなった。」とのことである。
これは本当だろうか?
論より証拠で、実際にSFC版とWSC版を比較してみましょう。
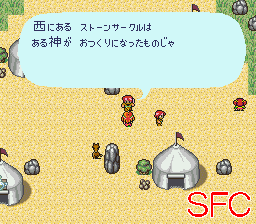
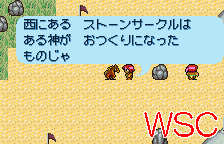
私見ですが、WSC版が見やすいという意見・・・もしかしたら文字の大きさの違い云々ではなくて、単純に「画面サイズに対して文字が大きいから読みやすい」ってだけなのかもしれません。
念のために、「文字の大きさと字間」という観点でWSC版を見ると、
・WSC版は漢字も仮名も同じサイズのようであるから、読みやすさのルールとしてはアウトである。
・WSC版は漢字と仮名の字間が狭すぎる場合があり(参考画像のように「に」の縦線が前の漢字の「西」と近すぎる)これは読みにくいように思う。
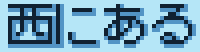
上記の「読みにくい」という指摘は、WSC版には文字に影がついているので、そのせいで読みにくいのかもしれない。
そこで、参考のために影無しバージョンも作ってみた。
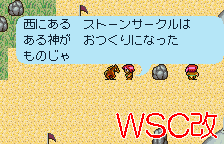
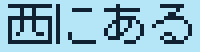
もしかしたら、WSC版は文字に影がついていない方が読みやすいのかもしれない。
◆まとめ
以上のような議論を通しての結論をまとめると、
・漢字と仮名の文字の大きさだけでは「読みやすさ」を判定することはできない。
・「読みやすさ」の行きつくところは国語の慣習・ルールを越えた美術・デザインの範疇だと思われる。
ということである。
6.私的残念ポイント
最後に、発売当時にロマ1をプレイして私が残念に思った点を挙げておく。それは「背景グラフィック」と「背景ミュージック」である。
私が残念だと思った理由はおそらく「先に発売されていたFF4よりも劣化した」と感じたからだと思う。
#FF4はロマ1の半年前(1991年7月19日)に発売している。
(1)背景グラフィック
直接見て比較していただければ何となく察していただけるように思うので、FF4とロマ1の参考画像を以下に示す。【移動時】
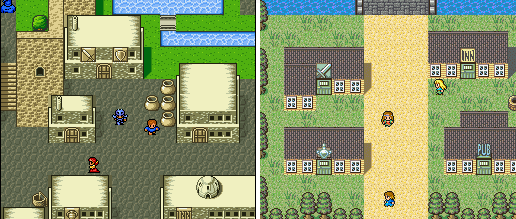
【戦闘時】
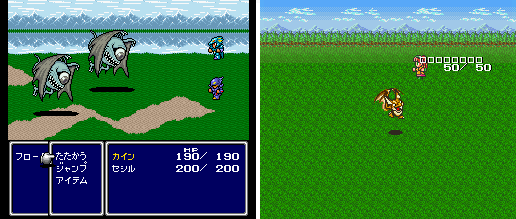
発売当時にロマ1をプレイして背景グラフィックに残念な気持ちを抱かされたことは覚えている。
しかしながら、今改めてロマ1の画面を見てみても、見慣れすぎてしまったために何が残念だったのか判断に困った。
そこで、当時の気持ちを思い出すためにFF4の画面を見てみたら「あー」と察したのである。
当時も事細かに比較して残念だと思ったわけではなく、FF4の背景グラフィックと比較すると全体的に「んー・・・」という残念な気持ちになるのである。
(2)背景ミュージック
| 参考BGM: ・【Video Soundtrack】ファイナルファンタジーIV ・【Video Soundtrack】ロマンシング サ・ガ |
ロマ1に対する否定的な意見の中には「ロマ1はクソゲーだけど音楽だけはいい!」というようにBGMだけを称賛する声がある。
面白いことに、上記のような感想は私とは真逆なのである。
つまり、私はロマ1を楽しんでいるけど、ロマ1の音楽をそこまでいいとは思っていないのである。
この点については「私とロマ1」においても以下のように述懐している。
「ロマ1の印象深い音楽は?」と言われたら、これまた人それぞれいろいろと思い起こすでしょうが、実のところ私はロマ1の音楽にそこまで思い入れがありません。
ロマ1をプレイした際のロマ1の音楽に対する私の印象は「何かぼんやりしているなー」でした。
これはおそらく先に発売しているFF4の音楽が極めて透明感を感じる物であったため、その対比もあってロマ1の音楽はぼんやりしていると感じたのだと思います。
一方で、効果音は印象深いものがいくつもありました。
さて、私がロマ1のBGMで感じた第一印象である「ぼんやりしている」・・・この要因はFF4との「音の違い」にあると思う。
FF4での「音のこだわり」については、「植松伸夫氏トークステージにて、『FF』オーケストラコンサート年末公演の日程が発表!【FF展リポート】」において以下のように述べられている。
| 『FFIV』から、ハードはスーパーファミコンに移り、音楽もより幅広い表現ができるようになった。これも有名な話だが、『FFIV』開発中、『アクトレイザー』の古代祐三氏が手掛けた音楽を聴き、植松氏はかなりショックを受けたという。「この音には勝てない」と、すでにできあがっていた曲をサンプリングし直したそうだ。 |
植松氏が敗北感を乗り越えて、こだわりにこだわり抜いた音で奏でられるFF4のBGMは、私にショックを与え、新時代(FCからSFCになってこんなにも透明感・臨場感のある音楽を奏でられるのか!!)を感じさせるには十分すぎた。
そんな洗練されたFF4の透明感・臨場感のあるBGMを満喫した後にロマ1のBGMを聴いてしまったために・・・ぼんやりと・・・霞んでしまい・・・物足りなく・・・残念な気持ちになったように思われる。
また、ロマ1の音楽を残念だと感じた要因は「音の違い」の他にももう一つあると思っている。
それは「使用される場面と合っていない」ことである。
ロマ1ではBGMが個別に設定されていない場面においては各主人公のテーマ曲が流れるのであるが、その違和感がどうしても気になってしまうのである。
以下にいくつか実例を挙げる。
◆ホーク
初回プレイはホークだった。開始早々違和感があった。ホークのテーマは重すぎない?
ホークは一隻の船に乗っているだけなのに、ホークのテーマからは何十隻もの海賊艦隊のような重厚感を感じられた。
◆アルベルト
アルベルトのテーマは箱入り息子的な感じがするので開始時は特に気にならなかったけれど、イスマス崩壊後は凄い違和感があった。
悲しみを背負っている感じが全くしないのである。能天気すぎる。
同じような境遇のドラクエ4勇者のフィールドBGMが「たった一人残されて物悲しいテーマ(勇者の故郷)」から「仲間が終結して魔王討伐に臨む勇ましいテーマ(馬車のマーチ)」に変化して痺れた経験をしていたこともあって、アルベルトでもそういう演出をやってくれていたら・・・という物足りなさを感じた。
◆ジャミル、アイシャ、クローディア
戦いに赴くようなBGMではないので、戦闘シーンを伴うような場面での違和感が凄い。
この点については、伊藤氏もクローディアのテーマについて「でも、重い場面でかかると合わないですね(笑)。」(大事典)と語っている。
◆シフ
格好いい!とても格好いい!!・・・のだけど、スタイリッシュすぎる。蛮族感を感じられない。
こういった話は個人の感性に依るものなのかもしれないので、上記の事例では納得していただけないかもしれない。
しかしながら、広く一般に「合っていない」と思われているロマ1のBGMも存在する。
それは「世界一格好いい下水道」とネットでもてはやされている「下水道のテーマ」である。
その賛辞の言葉が既に「合っていない」と言っているようなものではないだろうか。
そんな「下水道のテーマ」について伊藤氏は
| もともと『Rサ・ガ』って主人公がフィールドを歩くシーンがないでしょう。でも、それをまだ聞かされていないときに自分で勝手にアルベルトが歩いている、そういう感じで作った曲なんです。(大事典) |
伊藤氏が意図したように「下水道のテーマ」はたった一人残された悲しみを背負ったアルベルトがフィールドを進むときにこそふさわしいと思う。
私はロマ1のBGMの全部が全部「合っていない」と思っているわけではない。
ダンジョン系や「ラストダンジョン~邪神復活~決戦!サルーイン」の流れは凄く合っていると思う。
しかしながら、一部の「合っていない」が凄く気になってしまうのである。
ストーリー重視のFF4では当たり前のように場面とBGMを巧みに合致させて、場面を盛り上げ、プレイヤーの感情を揺さぶってきた。
そういった「合っている」BGMと比較すると、どうしてもロマ1のBGMは「合っていない」印象が強くなって、否が応でも見劣り(聴き劣り)してしまうのである。
念のために述べておくが、これは楽曲の良し悪し、好き嫌いの話ではなく、「合っているかどうか?」の話である。
私とてロマ1の楽曲は単独で聴く分には好きな部類である。
ただ、実際のプレイにおける場面とセットで考えると・・・という話なのである。
このような私の思いから推察すると、「ロマ1はクソゲーだけど音楽だけはいい」という感想と私の感想が真逆なのは、
・ロマ1を楽しんでロマ1の世界にどっぷりと浸れる人にとっては一部の音楽が使用場面と合っていないので手放しで褒められない。
・ロマ1を楽しめずロマ1の世界に浸れない人にとっては音楽そのものの評価になるので「音楽だけはいい」という感想になる。
ということなのではないだろうか。
なお、後年に伊藤氏は「『サガ』は自分にとっての学校。『SAGA2015(仮題)』は学びを経て挑む集大成――伊藤賢治氏インタビュー」において、ロマ1のBGMを振り返って以下のように語っている。
| ・開発が終わる4ヵ月くらい前にはほとんどの曲を納品していたんですが、河津さんの中にずっと引っかかるものがあったんでしょうね。そのタイミングで、「イトケン、もしかすると曲を全部作り変えさせるかもしれんぞ」と言われて。 ・河津さんを含めて、社内ではあまりいい評価はいただけなかったんですね。 ・きっと河津さんの耳にも届いたんでしょうね。あとで、「社内よりも外のほうが評価いいね。ただ、もうちょっと社内でも評価を得られるようにがんばりなよ」という言葉をもらいました。 |
(3)ファミコン通信のレビュー
本章の最後に、WEEKLYファミコン通信(1992.2.7)に掲載されたロマ1発売当時のレビューを付しておく。| 紹介文:プレーヤーの行動によって、異なった話の展開が楽しめるという自由度の高いRPG。武器を使い込むと必殺技を覚えるなど、斬新なシステムが盛りだくさん。 浜村通信(9点):グラフィック、シナリオのデキは、「FF」のほうが数段上。でも、ゲームという、おもちゃの1ジャンルとして評価するなら、こっちのほうが勝つと思う。「FF」が守りのゲームなら、「ロマンシング」は攻めのゲーム。面倒くさいけどいろいろやれた「FFⅡ」が好きだった人にお奨め。 アルツ鈴木(8点):スタート時に選ぶキャラクターによって、ゲームの展開が変わってくるので、何回でも遊べてしまうのだ。いやなイベントに出くわしたら、やめちゃってもいい!なんてところもイカす。BGMは「FF」シリーズのほうがよかったような気がするけど、及第点はいってると思う。 渡辺美紀(8点):キャラが8人いて、さらにストーリーにいくつも分岐点がある。つまり、プレーする人、ひとりひとりが違うゲームになるわけで(目的は同じでも)、それってスゴイよね。まだひとりのキャラでしか遊んでないから、的確な評価も感想も言えないけど、この新しさはいいみたい。 TACOX(6点):「FF」の臭いがみっちり染み着いてて、私はどうしても馴染めそうもない。複数分岐のシナリオシステム自体はそれほど目新しいものではないけど、でもまあよくめげずにやったなあと感心。惜しむらくはなんだかいい加減な戦闘シーンとビジュアル。「FF」よりもクオリティーが低い。 |
おわりに:
ロマ1を「クソゲーだ!」と評する意見には様々なものがある。それらのほとんどは、やはりただの言いがかり・不当な難癖だと改めて思ったのであるが、その一方で、
・フリーシナリオシステムを謳っているにも関わらず、通常プレイの範疇で詰みうる。
・不便で不自然なだけの所持金(上限と両替方法)システム。
上記の2点については擁護のしようが無かった。
救える方がいらっしゃったら、よろしくお願いします。
補足:発売当時の一般的な評価
ネットにおいてロマ1が「発売当時からクソゲー扱いだった」という意見を見かける。
果たしてそれは本当だろうか?
WEEKLYファミコン通信(1993.1.1)の「読者が選ぶTOP20」(アンケートはがきによる読者投票で高評価されたゲーム)には以下のように1992年の累計が示されている。
| 順位 | ゲームタイトル | 機種 | 発売日 | 得点 |
| 1 | ファイナルファンタジー4 | SFC | 1991.7.19 | 52406 |
| 2 | ストリートファイター2 | SFC | 1992.6.10 | 48405 |
| 3 | 天外魔境2 卍MARU | PCE-CD | 1992.3.26 | 34005 |
| 4 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | SFC | 1991.11.21 | 33340 |
| 5 | ロマンシングサ・ガ | SFC | 1992.1.28 | 29543 |
| 6 | ドラゴンクエスト5 天空の花嫁 | SFC | 1992.9.27 | 23504 |
| 7 | ソニックザヘッジホッグ | MD | 1991.7.26 | 23349 |
| 8 | シャイニングフォース 神々の遺産 | MD | 1992.3.20 | 15404 |
| 9 | ドラゴンクエスト4 導かれし者たち | FC | 1990.2.11 | 12927 |
| 10 | イース1・2 | PCE-CD | 1989.12.21 | 12334 |
上記のように、ロマ1は名立たるタイトルと並んで多くの方から高評価を受けている。
この結果からすれば、「発売当時からクソゲー扱いだった」という意見が一般的な評価だったなんてことはありえない。
このように多くの方から高評価を受けていたロマ1を「クソゲー」だと思ったのならば、本稿で述べたように「プレイヤー側」の問題点をまず疑うべきであろう。
