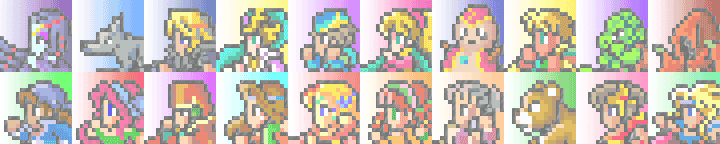
私とロマ1
(2022年01月28日発表)はじめに
1.【第一期】浪漫の大海原へ!
(1)発売前に思いを馳せる
(2)大航海時代の匂いを感じた
(3)ゲームとしても楽しんだ
2.【第二期】解明の大海原へ!
(1)大航海時代の再来
(2)Romancing虎の巣による開拓
3.【第三期】解析の大海原へ!
4.【第四期】物語の大海原へ!
5.まとめ
6.私にとってのファミ通WS事件
おわりに
はじめに:
「ロマサガ1は面白い!」、「ロマサガ1はクソゲーだ!」・・・ロマサガ1に対する感想は人それぞれだと思います。この度、ロマ1が発売から30年経つということで、ロマ1攻略サイト「Romancing虎の巣」を2000年1月1日に開設して22年運営してきた私(管理者とら)の場合は、ロマ1に対してどのような思いを抱いているのかについて、良い機会なのでまとめておこうと思います。
ということで、ロマ1発売30周年特別企画、ロマ1論番外編「私とロマ1」始まります。
1.【第一期】浪漫の大海原へ!
(1)発売前に思いを馳せる
ロマ1に対する思いというものを表現しようとする際には、ロマ1単独で語ることはできず、ロマ1が発売するそれ以前の当時の状況についてまずは押さえておかなければいけません。1989年12月、魔界塔士サガ発売。
1990年12月、サガ2秘宝伝説発売。
1991年7月、ファイナルファンタジー4発売。
このような大変魅力的なタイトルが発売した状況で、これらに続くタイトルとして発売されたのがロマンシングサガ1なのです。
GBサガ1、2はゲームボーイソフトでありながら、そこには魅力的な世界が詰まっていました。
人間、エスパー、魔物に機械、そして神、それらが同居する雑多で荒廃的な世界は独特な異世界感を醸し出していました。
また、FF4はファイナルファンタジーの世界がSFC(スーパーファミコン)の力で圧倒的に美しく描き出されていました。
これらのタイトルは本っ当に面白かった!
そんな面白いタイトルに続くのがロマ1だったのです。
期待しかない!
ロマ1の発売予定を知ったのはファミマガ(ファミリーコンピューターマガジン)の広告でした。
そこに描かれた小林画伯による主人公8人のイラストを見て、もの凄く驚いたとともに、期待が高まったことを覚えています。
何をそんなに驚いたのかと言うと、サガシリーズにもかかわらずそれらは美しかったのです。
GBサガと言えば私にとっては雑居ビルのイメージがありました。
それに対して小林画伯のイメージイラストからは、これまでのサガが放っていた雑居感は微塵も感じられず、純中世風?な主人公達が美麗で妖艶に描かれていたのです。
雑居な世界観のサガが純中世風?な世界観になって、FF4で見せつけたSFCの圧倒的な力で描き出される!
サガは一体どうなってしまうんだ!?
ロマ1の事前情報を紙面上で見るたびに、楽しみだ!待ちきれない!早く遊びたい!そんな気持ちでいっぱいだったように思います。
歳を重ねた今では「待ち遠しい」なんて気持ちを感じることは全く無くなってしまいましたが、当時はまだ若かったので待ち遠しいことばかりでした。
週刊少年ジャンプを読んだら、読み終わったその瞬間に次号が待ちきれなくなってしまうくらいに待ち遠しい気持ちでいっぱいでした。
そんな私にとって当時のスクウェアの戦略は私の待ち遠しさを増幅させるものでした。
割と知らない方も多いと思うのですが、当時のスクウェアはタイトルによってはゲームソフトの発売日前にゲームの音楽CD(オリジナル・サウンド・ヴァージョン)を発売していたのです。
具体的にはFF4、ロマサガ2、FF6はソフトの発売日前に音楽CDが発売されていました。
発売日前にゲームの音楽を聴くと、「この音楽はどんなところで流れるのかな?」、「これはボス戦だな!」、「この音楽が流れるところで何が起こっているの?」等々、発売する前から想像や妄想が膨らみまくって、待ち遠しさが加速するわけです。
#ロマサガ3については主人公8人のテーマのみが発売日前に聴けたけど(ロマンシングサガ3プロローグ)、あれだけでは物足りなかったですね。
そして、発売日前に聴いてその世界に想像を膨らませた曲は今でも印象深く心に残っています。
ロマ2の「通常バトルはこの曲だったの?」という意外性、FF6の「おそらくこれがラスボスの曲っぽいけど、これでどんな戦闘をするの?」と疑問に思いつつ実際に戦ってみての「こう来たかー!」感、中でも一番印象深いのはFF4の赤い翼からフィールド、そして戦闘への一連の流れは私にとっての至高です。
そのように思うからこそ、ロマ1の場合はソフトの発売日前に音楽CDが発売されなかったので、それは残念だったように思います。
音楽CDが先に発売していたら、ロマ1の音楽に対する私の印象もおそらく今のものとは別のものになっていたはず。
ということで、ロマ1については発売日前にゲームの音楽を聴いて想像と妄想を膨らませることはできなかったけれど、その分、小林画伯のイラストで想像と妄想を膨らませたのでした。
「この海賊のおっさん、どんな冒険をするのだろう?」と。
(2)大航海時代の匂いを感じた
そんな期待で膨らみ切った1992年1月28日に満を持してロマ1は発売されました。#当時の私はおもちゃ屋さんと懇意にしていたので、新作や新ハードは発売日前日の夕方に購入できていました。
そしてプレイ開始。
発売日前に想像と妄想を膨らませる中で私がロマ1に感じていたのは大航海時代の匂いでした。
私は幼い頃から未確認生物が好きだったのですが、それ系の書籍には大航海時代の頃の古地図が掲載されていることがありました。
例えば、コルネリス・デ・ジョードが1593年に描いた北米大陸西海岸の図のようなものです。
#エドワード・ブルック=ヒッチング著、関谷冬華訳『世界をまどわせた地図』日経ナショナルジオグラフィック社.p.16より抜粋.
見ていただければ分かる通り、大海原には未知なる巨大な海獣の姿が描かれており、未知なる世界に対しての畏怖の念とそれ以上の好奇心が込み上げてきます。
現代ならば「こんなものはいない!」と一蹴されてしまうでしょうが、おそらく大航海時代当時はこれを誰もが真実だと(真実かもしれないと)捉えてしまうような夢と希望に満ち溢れた時代だったのではないでしょうか。
そんな大航海時代の匂いを私はロマ1から感じていたので、その匂いを色濃く醸し出している海賊キャプテンホークを迷わず主人公として選択しました。
そして私は冒険者になりました。
「ゲームをしている」という感覚ではなく、ロマ1の世界・・・つまりマルディアスのAS1001年の世界に私はキャプテンホークとして大海原に漕ぎ出していたのです。
どうしてそんな感覚になったのでしょうか?
その要因はおそらくロマ1のさりげないリアリティー(現実感)にあったように思います。
ロマ1のさりげないリアリティー要素の一つ目は敵モンスターです。
「ロマ1の印象深い敵は?」と言われたら、人それぞれいろいろと思い起こす敵がいるでしょうが、私が真っ先に思い起こすのは(意外に思うかもしれませんが)「キャンサー」なのです。
サンゴ海を漕ぎ出した私がおそらく最初に対峙したのが水棲生物系のキャンサーだったのです。
魚系編成L1でピラニアのお供として出てきたのでしょう。
ピラニアのほうは全く印象に残っていませんが、キャンサーは強烈に印象に残っています。
私の自宅のそばには小さな沢があり、幼少期の夏はそこでサワガニを捕るのが日課でした。
そんな身近な生き物であったカニが妙にリアルに描かれて目の前に現れたために、自分の実体験とリンクしてロマ1にリアリティーを感じたのだと思います。
#カニと言えばドラクエ3の軍隊ガニがいますが、あちらはモンスターで、こちらはただのカニ・・・という印象です。
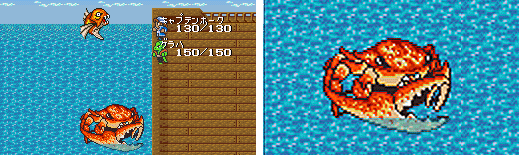
そして、もう一つのロマ1のさりげないリアリティー要素は音です。
「ロマ1の印象深い音楽は?」と言われたら、これまた人それぞれいろいろと思い起こすでしょうが、実のところ私はロマ1の音楽にそこまで思い入れがありません。
ロマ1をプレイした際のロマ1の音楽に対する私の印象は「何かぼんやりしているなー」でした。
これはおそらく先に発売しているFF4の音楽が極めて透明感を感じる物であったため、その対比もあってロマ1の音楽はぼんやりしていると感じたのだと思います。
一方で、効果音は印象深いものがいくつもありました。
特に、粘液やレインコールといった水っぽい音が妙に生々しくて、初プレイ時は感嘆の声が漏れたものです。
思うに現実の世界には(街中でなければ)BGMなどなく、聴こえてくるのは鳥の声、川の音、風の音、車の音といった様々な音ばかりです。
つまり、ロマ1の「BGMはぼんやりとしているが効果音は生々しくはっきりと聴こえる」という点が現実の世界と類似していたために、私はロマ1に対してリアリティーを感じたのだと思うわけです。
このような理由から私はロマ1にリアリティーを感じ、その世界にどっぷりと浸ることができました。
そして、冒険を進める中で、発売日前にロマ1に対して感じていた大航海時代の匂いをよりいっそう強く感じていました。
このように感じた理由はおそらくロマ1のシステムにあったのだと思います。
ロマ1のシステムは斬新でした。
謳い文句であるフリーシナリオシステムを筆頭に、選べる8人の主人公、レベルを廃止して個別のステータスアップ、細分化された装備箇所、フィールド移動を廃止した地図上での移動、隊列、シンボルエンカウント、世界中のモンスターが徐々に強化、武器ごとのウインドウ、換金・・・等々、ロマ1は従来のメジャータイトルには無い斬新なシステムばかりでした。
そして、ロマ1は未知であり、かつ自由でした。
新しいタイトルを遊ぶ際は当然ゲームの展開は未知なのですが、決まったストーリーを進める従来のタイトルとは違い、ロマ1の場合はフリーシナリオシステムだったため、自分の意思で選んだ未知の場所に進んでいくことになるのです。
これが「自分で冒険をしている感」につながったように思います。
このように今までにない未知のシステムによって自分の意思で冒険を進めている感じが、私のイメージする大航海時代の感じ・・・即ち、未知で未開の世界に冒険に繰り出している感じに合致したわけです。
こう振り返ってみると、当時の私はロマ1のゲームの内容そのもの(ストーリーや戦闘)を楽しんだというよりは、「大航海時代を冒険している感」を楽しんでいたように思います。
もちろんその感覚は当時の時代背景や私の年齢も影響しているでしょうが、他にロマ1ほど大航海時代の匂いを感じられるゲームには未だに出会えていません。
#ゲームそのものからは感じませんが、「ソウルエッジのOPムービー」はロマ1と同じ匂いがするので大好きです。
#そんなわけで、裏話としてはMMD(ミクミクダンス)全盛の頃にロマ1のキャラでソウルエッジOPのパロディームービーを作りたいなーっていう展望がありました。もちろん、ソフィーティアの入浴シーンはアイシャの「見ちゃダメ!」です。
(3)ゲームとしても楽しんだ
私の感じている発売当時のロマ1の魅力については(2)で十分に語ったのですが、やはり慣れてくるとロマ1の魅力である冒険感は無くなってしまうので、その後はゲームとして楽しむようになっていきました。ある日、私の兄がロマ1のプレイを開始していました。
兄は初回プレイからバーバラ一人旅をしていたのです。
衝撃的でした。
「6人パーティーを組めるのだから6人パーティーでなければならない!」という私の固定観念を粉々に砕いてくださいました。
当時はネットもなく、縛りプレイという言葉も聞いたことのない頃だったけれど、私の兄はファミコン時代から縛りプレイをやっているような人でした。
他にもFCドラクエ3で勇者1人旅とか。
そんな兄に感化されて、私もいろいろなタイトルで縛りプレイを楽しむようになっていました。
ロマ1はもちろんだけど、印象深いのはFF5(SFC)のジョブチェンジ禁止プレイ・・・制限があると試行錯誤できて面白かったなーってしみじみと当時を懐かしめます。
そんな風に縛りプレイもしながらゲームとしてもロマ1を楽しんでいました。
2.【第二期】解明の大海原へ!
(1)大航海時代の再来
時は流れ、1999年7月。「これからはパソコンが必須の時代になる!」と祖父に頼み込んで、パソコンを買ってもらってネットデビュー。
そして、私は出会いました。
当時の私にとってもロマ1は思い入れのあるゲームだったようで、当たり前のように「ロマンシングサガ」で検索し、ロマ1攻略サイトの始祖「のりおすくりゅう~」に足を踏み入れたのです。
・・・衝撃的でした。
時間経過?、善行・悪行?、最大HP65534?、等々・・・これは私の知っているロマ1の話をしているのか!?と疑いたくなるほど、全く知らない情報ばかり。
自分ではけっこうロマ1をやり込んだし、攻略本も読み込んでいたので、ロマ1のことは人並み以上に詳しいつもりだったけれど、全く知らないことばかりで井の中の蛙を痛感しました。
例えるならば、FF3で浮遊大陸の外にまだ外の世界が広がっているということ知ったような、ハンターハンターで自分達にとっての全てであった世界の外には遥かに広大で未知の暗黒大陸が広がっていたという事実を知ったような、そんな衝撃を受けました。
そして、そんな未知の存在のロマ1について、のりおすくりゅう~の掲示板では盛んに情報のやりとりがなされていました。
ディアナと再会できた、ナイトハルトが襲ってきた、シェリルやデスが仲間になった、ダイヤモンドを入手できた、アサシンを召喚できた、ジュエルビーストを召喚できた、グリフォンやマンティコアといったレアモンスターに遭った、海でリバイアサンが出てきた、闇術・邪術を覚えられた、サルーインがダークソードを使った、等々・・・のりおすくりゅう~の掲示板には自分がロマ1では目にしたことのないような情報で溢れていたのです。
この雰囲気は・・・まさに大航海時代の酒場のようではないですか!!!
大航海時代、航海を終えた船乗り達は酒場で旅先で目にしたもの、体験したことを雄弁に語りました。
それらの話には誤認や誇張、ホラ話もあっただけでなく、その話が広まるにつれてどんどん尾ひれはひれがついていく。
象をも持ち上げる巨大な鳥「ロック鳥」なんかは、そんな話の一例ですね。
嘘か真実か・・・ロマ1には攻略本に掲載されていなくても実際には発生するイベントがあったし、攻略本では語られていないことも多くありました。
さらには、常識の壁をさらっとぶち破ったレイディバグが発見されていたこともあって、一見嘘のような情報でも実際に再現できてしまった事例もあったのです。
そんなわけで、当時ののりおすくりゅう~掲示板は、真偽が入り乱れて混在し、ロマ1では何が起こっても不思議ではないという夢と希望で満ち溢れ、誰もがロマ1に無限の可能性を感じていたように思います。
未知なるロマ1の世界に一獲千金を夢見て皆が漕ぎ出していく・・・ネットで出会ったのりおすくりゅう~のおかげで、私はロマ1に対して再び大航海時代の匂いを感じていました。
(2)Romancing虎の巣による開拓
ネットデビューすることで、もう一つの出会いがありました。当時はネットの常時接続は決して当たり前のことではなく、私の場合は専ら夜11時から朝8時まで限定で定額使い放題のテレホーダイタイムが私のネット満喫タイムでした。
12月初旬、私はサガシリーズのファンが集ったサガリングチャットに迷い込み、そこで常連の皆さんとまったりわちゃわちゃと朝まで語り合う日々が始まっていました。
サガリングチャットの常連の皆さんと仲良くなったそんなある日(12月20日頃)、常連の皆さんそれぞれが各自のホームページを持っていたこともあって、私もホームページを作ったらどう?という話になりました。
そんな言葉に背中を押されて、2000年1月1日にうっかりと開設してしまったのが本サイトです。
#開設当時はロマ1専門ではなく、サイト名も「Romancing虎の巣」ではありませんでしたが、諸事情により早い段階からロマ1専門に移行し、それに伴いサイト名称も「Romancing虎の巣」と改めました。
本サイトを開設して最初に何をやっていたのかというと、仮開設状態の1999年末に「獣狩り」と称して、マンティコアとグリフォンを捜索していました。
当時のロマ1界隈掲示板では、「マンティコアとグリフォンに普通に遭えた」という情報がまことしやかに語られていました。
しかしながら、私はそれらに一度も遭ったことが無かったので、遭えるものなら遭ってみたいという思いで、いろいろと条件を変えて敵の出現率のデータを取ったり、特定の条件の下でしか出現しないのでは?と仮説を立てて検証したりするも、結局遭えずじまいでした。
#後のデータ解析により、これらの敵には通常では遭遇できないことが確認されています。つまり、遭えたという情報は誤認、勘違い、ホラ話ということになります。まさに大航海時代の酒場の如しです。
そして本開設の際には「最大ダメージ考察」というテーマを取り上げていました。
当時の掲載内容によると、シュウさんのホームページ(現Library Xiu)でロマ1の最大ダメージの話題が出ていて、それに感化されて自分でも取り組んでみようという流れだったようです。
#ロマ1で5桁ダメージが出るということ自体は、ネットデビュー以前から私は自分でやっていましたが、最大値がいくつか?という点については考えたことが無かったので、それに興味を惹かれたのだと思います。
最大ダメージという話題は私にピッタリでした。
私は数学を専攻していたということもあって、開設当初からダメージ算出式についての考察を行っていました。
そしてそれに伴い、ダメージ算出式についてしっかりと解明しなければ最大ダメージについての結論を出すことはできないと判断して、ダメージ算出式研究が始まったのです。
多くのデータが必要だったので、中古屋巡りをしてロマ1のソフトをいくつも掻き集めたものでした。
その後、各種算出式について考察することを通して、研究対象はロマ1の戦闘に関すること全般にまで広がっていき、程なくして虎の巣はのりおすくりゅう~、シュウのホームページに次ぐ第三のロマ1攻略サイトの地位を確立するに至ったのでした。
ですが、その成功は決して私一人の力によるものではなく、虎の巣に集ってくださった研究協力者の皆様方の支援があってのものです。
本当にありがとうございました。
参考までに、当時の調査資料(シュウさんと共同で解明したサルーインのHPの仕組みについての調査)の一部です。
・シュウさんからダメージデータをメールでいただいて手計算。
・怪しい図で表現して検討していたようです。
虎の巣を開設したことで、私にとってのロマ1は遊ぶ対象から、研究の対象になりました。
そして、虎の巣を開設してロマ1研究を行ったことで、ロマ1の魅力であった未知・未開の部分が徐々に失われていきました。
当然、ネットデビュー当時に再度感じることができたロマ1が醸し出す夢と希望にあふれた大航海時代の匂いも徐々に感じられなくなっていったのでした。
3.【第三期】解析の大海原へ!
数年間ロマ1から引退し、虎の巣も半ば放置状態でしたが、2005年11月頃からBBSへのスパム投稿(プログラムによる迷惑書き込み)が始まりました。そして、その対策をしているうちに、虎の巣の内容にもミスがいろいろあることに気付き、それを修正するために虎の巣の管理に復帰しました。
その際に、虎の巣のレイアウトを現在のものにリニューアルしました。
意図としては、当時はネットも十分に普及し、ブログのようなサービスを使うことで誰でも簡単に整ったサイトを作ることができるようになっていたので、旧態依然としたネット黎明期のようなサイトのままでは誰にも利用されなくなってしまうこと危惧して、スタイリッシュさと使いやすさを追求した決果、現在のレイアウトに落ち着いたのです。
そして、2006年の12月に虎の巣は新たな段階に進むことを決心しました。
以下は、当時のBBSへの私の書き込みです。
| とら - 2006/12/13(Wed) 19:46 No.2552 ■今後の方針 ロマ1に携わって長い時間が経ちました。 その間に戦闘に関する様々な事象について解明してきたわけですが、さらなる高嶺を目指そうと思うとさすがに限界を感じます。 限界を感じる反面、やれることは十二分にやったという納得の気持ちもあります。 んでHPを作ってからそろそろ7年満了を向かえるので、ここらで区切りをつけたいと思います。 ということで、今までは実機調査、実機での再現性にこだわってきましたが、今後は基データ解析も手掛けることにします。 ロマ1の根底の仕組みの解明のため、かつ今までの調査の答え合わせのため、ということでご理解いただきたい。 |
ロマ1攻略サイト界隈では暗黙の了解として実機でのプレイが大前提としてありました。
しかしながら、真理を追究しようと思うと、実機ではどうしても限界がありました。
また、裏事情としては、今後確実に解析データを扱うサイトが登場してくるだろうから、そうなった時に今のままではロマ1攻略サイト群は駆逐されてしまうという危機感を感じていました。
このような理由から、ロマ1攻略サイト界隈の禁を破ってデータ解析をやることを明言し、ロマ1に対する主たる研究方法をデータ解析に切り替えて、その成果を公表していくことにしたのです。
データ解析というと「そんなのずるい!」と思われるかもしれませんが、データ解析って決して簡単ではないのです。
私の場合は、例えば、
5F 43 B2 78 AD 04 9C 64 1E 18 70 3A E4 26 BD 68
のような16進数で表示された莫大な数の数値の羅列を眺めて、そこから目的の情報(例えば武器データとか台詞のデータとか)が格納されている場所を特定して、そこに示されている数値がそれぞれ何を意味するのかを読解していくわけです。
このデータ解析は私にとっての新たなゲームの楽しみ方になりました。
莫大な数の数値の中からお宝となる情報を発掘して解き明かしていくというのは、大冒険時代に未開の地を切り開いていく感じと類似しているように思います。
#さすがにやっていることがデジタル過ぎて、大航海時代の匂いを感じることはありませんでしたが。
こうして虎の巣ではデータ解析という手法により、戦闘関連に限らずイベント関連も含めてさらなるロマ1の解明が進んだのでした。
参考までに、研究資料の一部を紹介します。
#未公表の情報もあるので、あくまで部分的にです。
・イベントフラグについては行動毎でのフラグの数値の変動が一覧にしてあります。
データ解析によってロマ1の未知なる謎の真相がいろいろと解明されました。
それぞれの仕事に思い入れがありますが、特に思い入れがあるのはロマ1ではなくクロノトリガーの「コオルギイボイス」の使用条件の解明です。
おそらく「コオルギイボイス」の使用条件の第一発見者は私です。
当時、クロノトリガーの敵の行動規則をデータ解析で調査していたら、アトロポス45という敵が何やら見慣れぬ攻撃方法「コオルギイボイス」を使用することが発覚しました。
ところがその使用条件は他のどの敵の行動規則における使用条件とも類似していないアトロポス45固有の条件となっていて、その読解は難航しました。
以下は、当時のBBSへの私の書き込みです。
| とら - 2008/03/24(Mon) 20:06 No.3298 アトロポス145が「コオルギイボイス/眠り」を反撃で使うはずだが使用条件が分からず。 とら - 2008/03/27(Thu) 01:28 No.3301 やっと「アトロポス145」の「コオロギイボイス」の使用条件が分かった。 アトロポス145の初期体力は10で、ロボがロケットパンチで攻撃するたびに体力が+1される。 で、ロケットパンチで4回攻撃すると体力14になるが、この時に何かしらの攻撃を受けると反撃で「コオロギイボイス」を使用する。 使用後にアトロポス145の体力は0になる。 #正しくはコオ「ル」ギイボイスですが、この書き込みの際は普通に間違えてコオロギになっています。 |
当時は2008年なので当然クロノトリガーの攻略サイトはいくつもありました。
しかしながら、それらのどのサイトにもコオルギイボイスの情報は無かったので、時間をかけて試行錯誤をしながら読解に励んだ結果が上記の書き込みなのです。
アトロポス145戦はゲーム終盤のため、ロケットパンチよりも強力な攻撃方法があるので普通はロケットパンチを使用しませんし、仮にロケットパンチを使用してもアトロポス145の体力が+1されるなんてことは表示されませんから、意図的に狙わない限りは普通はアトロポス145戦でロケットパンチを4回使用するなんてことは無いのです。
そんな特殊な使用条件だったため、もしもデータ解析をしていなかったら、アトロポス145のコオルギイボイスは未だに誰にも知られることなくデータの海に埋もれていたのかもしれません。
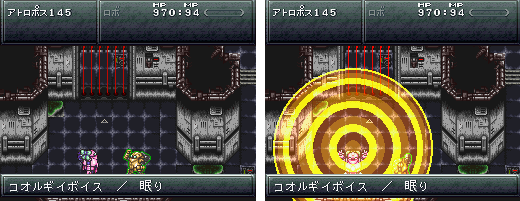
ということで、データ解析に着手したことで、ロマ1に限らず、他のゲームの解析も試み始めました。
本サイトにある「各種データ」はその仕事の成果です。
4.【第四期】物語の大海原へ!
それからまた十年近くの時が流れました。ロマ1から引退し、虎の巣も完全放置状態でしたが、プロバイダがCGIサーバを変更したことによって虎の巣のCGI(BBSやアクセスカウンタ等)が機能していない状態が気になりだしたことをきっかけに、2020年7月に虎の巣の管理に再び復帰しました。
しかしながら、ロマ1をかまわない日々が長すぎたため、もはや私にはロマ1研究を進めるほどの知識がありませんでした。
それに、ロマ1攻略サイト界隈の様子も当然変わっていました。
かつての研究協力者の皆様方もロマ1を引退されたようで、その姿はもうありませんでした。
そんな状況において私が虎の巣に新たに掲載したのがロマ1論の「ウェイ=クビン論」でした。
以下は発表当時に私がBBSに書き込んだものです。
| とら - 2020/08/31(Mon) 21:42 No.5049 10年くらい前に考えたのだけど、妄想に過ぎないのでBBSにも書いてなかったのですが、折角なので今回編集してUPしました。 妄想なんだけど・・・できるかぎり根拠になるようになるものを探して、何とかそれなりの筋は通して論の体裁にはしたつもりです。 気持ちとしては「読むロマ1」です。 私も今回HP管理に復帰するまで正直10年くらいロマ1をかまっていませんでした。 おそらく私と同時代にロマ1をかまっていた方々も、もうロマ1をプレイしていないのではないでしょうか。 だからこその「読むロマ1」。 プレイしているだけでは見えてこない事柄について、何かしらの根拠をもって語れたら、実際にロマ1を今プレイしていなくても、また新たなロマ1の面白さを感じることができるかもしれない。 そんな気持ちで書きました。 ともかく、楽しんでいただければ幸いです。 |
このように現在も続稿を執筆し続けているロマ1論の物語考察は、ロマ1を引退してもはやロマ1のことなどすっかり忘れてしまった方々が気の迷いでフラッと虎の巣を覗いたときに、プレイするのではなく読むことでロマ1を再び楽しんでもらうことを意図したものです。
さて、そんなロマ1の物語考察ですが、上記の書き込みに関して補足をしておきます。
書き込みにもありますが、物語考察の原型のようなものは2010年頃には既に考えてありました。
とは言っても、「~論」といったまとまった形にはなっておらず、個別の謎について考察したものがメモ帳にズラッと書いてあった程度です。
例えば、ウェイ=クビン論の発端になったのは、「大全集のクジャル族の項目には『タルミッタのセケト宮殿にみられる八角形の城塞建築と根強い水竜信仰にクジャル族固有の文化を垣間見ることができる。』という記述があるから魔の島の塔はどうやらクジャル族が造ったっぽい。それならば、どうしてクジャル族の作った塔にウェイ=クビンはいるのか?」という問いです。
このような問いについての自分なりの推察や、納得のいく答えの出ていない問いがズラッと列記してありました。
そして、2020年の夏にたまたまYouTubeでゲームの物語についての考察動画を目にして、こういう考察を発表するのも悪くないと思い、過去の記録を掘り起こし、一つのテーマを定めてそれに関連する話題を編集して「~論」の形にまとめたわけです。
ロマ1の物語考察をロマ1論として執筆するにあたって留意していることが二つあります。
一つは、自分が納得できる物語の展開を根拠を持って語ることです。
物語考察は大きな括りで言えば私の妄想にすぎませんが、ゲーム内で起こった事柄や関連文献の記述を根拠とすることで、それが真実である可能性を少しは高くすることができます。
そこで、散らばっているゲーム内で起こった事柄や関連文献の記述の一つ一つの行間を読んで、それらを繋げて、それが筋道立てられた物語として私が納得のいくものになって初めて発表しているのです。
#「行間を読む」とは一般には「文章には直接表現されていない筆者の真意を汲み取る」という意味ですが、私は「二つの事柄の関係を明らかにする」という数学界隈用語としての意味で用いています。
私の物語考察ではゲーム内でのバグと思われる事象についても考察が及んでいるので、読者によっては「バグを根拠にするのはおかしい!」と思う方もいるかもしれません。
しかしながら、私から言わせていただくと、そのような指摘はナンセンスで科学的ではありません。
現実世界で起こっていることが一番の真実であり、それを解明することが科学なのです。
つまり、ロマ1の物語考察においては、ゲーム内で起こっていることがロマ1の現実世界で起こっている真実であり、最も優先して考慮すべきことなのです。
従って、例えば、ゲーム内で起こった事柄と関連文献に記載されている記述に違いがあるならば、ゲーム内で起こった事柄を真実と判断し、関連文献の記述を誤りだと判断するわけです。
#実際、ロマ1の関連文献には多くの誤りがあることが知られています。
よって、ゲーム内で発生するならばバグもロマ1の世界における真実であるため、十分に根拠になりえるのです。
そして、もう一つの留意していることは、できる限り虎の巣らしさを取り入れることです。
言い換えれば、できる限り虎の巣における研究成果を根拠として考察するということです。
これは虎の巣ならではの独自性を出すために留意していることです。
つまり、文献に基づく考察だけならば他者と類似したものになってしまう可能性がありますが、虎の巣で積み上げられてきた研究成果も考慮すれば確実に虎の巣ならではの独自性のある考察になるのです。
従って、本サイトに掲載されているロマ1論の物語考察は他所にはない独自性、新規性、意外性のある考察を楽しんでもらえると思っています。
このように現在の私はロマ1の語られない物語の背景について自分の納得いくような筋を通すことを楽しんでいるのでした。
5.まとめ
以上で述べてきたように、私とロマ1の関わりを振り返ってみると、その関係は四つの期間に分けられて、それぞれの期間で別の冒険の仕方でロマ1を楽しんできました。即ち、
発売当時は自分自身が大航海時代を冒険するかのように楽しみ、
虎の巣を開設してからはロマ1の仕組みを解明することを楽しみ、
データ解析をするようになってからはプログラムを探索・読解することを楽しみ、
そして現在はゲーム内で起こる事柄や関連文献をもとにロマ1の物語の背景を筋道立てて説明することを楽しんでいるわけです。
このように4通りの方法でロマ1を楽しんできたわけですが、これらに一貫しているのは「私はいつもロマ1の未知なる領域に挑むことを楽しんでいた」ということです。
これが私とロマ1についての結論です。
6.私にとってのファミ通WS事件
私とロマ1についての話は以上なのですが、私とロマ1の関係の3/4は虎の巣を運営していたからこその話なので、それに関わってもう1点触れておきたいことがあります。それは2001年12月に起こったファミ通WS事件のことです。
#事件の概要については本サイトの「ファミ通WS事件」を参照してください。
この一件は、傍から見ると「ファミ通が無断転載した!ひどい!許せない!信用ならない!」みたいにファミ通を悪だと捉えるように考えてしまうかもしれませんが、当事者である私自身はそんなふうには思っていません。
というのは、本サイトの「ファミ通WS事件」には「よく言えば、名誉な災い」という副題がついているように、無断転載自体は当然悪いことですが、私にとっては名誉だと思う気持ちもあったのです。
そして、その名誉に思った気持ちが、私に新しい一歩を踏み出させたのです。
当時の私はちゃらんぽらんに生きていました。
幼少期には漠然と研究が好きだという気持ちはありましたが、何やかんやで流れに身を任せていたら、研究ではない世界で社会人1年目を迎えていました。
そんな時にファミ通WS事件が起こったのです。
あの時に私が思ったことは、・・・私の突き詰める力は全国規模の雑誌にも通用するんだ・・・ってことだったのです。
私はそんなに賢くなかったので研究の世界に進んでも自分が通用するのか自信が無く、その世界に進むことを躊躇していました。
そんな私の背中を押したのが、あの一件だったのです。
私の突き詰める力は研究の世界でもきっと通用する・・・と。
こうして私は学術研究の世界に進む決意をし、大学院に進学して、研究の世界で生きることになったのでした。
そんなわけで、私にとってのファミ通WS事件とは、私の研究能力の萌芽が認められたと実感することができた名誉な一件なのです。
おわりに:
ロマ1発売30周年記念ということで「私とロマ1」というテーマで執筆してみましたが、いろいろと感慨深いものがありました。ロマ1攻略には全く関係ないですが、ところによってはロマ1界の狂人と呼ばれている私がロマ1をどのように思っているのかについて、なかなか面白い話としてまとめられたと思います。
本稿を執筆している途中で過去の虎の巣を見直してみると、全く記憶になかったのですが、2000年の開設当時にも「私とロマ1」という見出しで私の思いを書いていました。
それが以下のものです。
| ここに来訪した方なら周知の事と存じますがロマ1には未だに明かされぬ謎が多いのです。 そんな未開の地に足を踏み入れてみようじゃないですか! そんなワケで、ロマ1の知られざる謎の解明に尽力したいと思います。 |
たった3行と短いですが、ロマ1研究に対する前向きな気持ちが感じられます。
そして、それから22年経って「私とロマ1」はこんなにもいっぱいのエピソードを語れるほどに膨れ上がっていました。
でも、これで終わりではありません。
私とロマ1のロマンシングな物語はまだまだ続くのでした。
