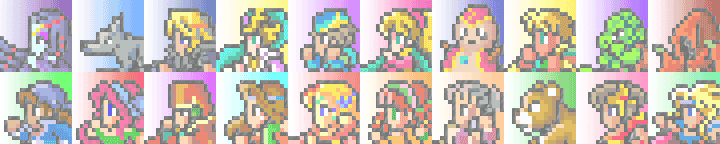
ミニオン論Ⅱ -ヘイトによる南部方面侵略作戦-
(2021年8月27日「1.騎士団領侵略作戦」を発表)(2021年9月03日「2.バルハラント侵略作戦」を発表)
はじめに
1.騎士団領侵略作戦
(1)ヘイトに目をつけられた人物
(2)操られたテオドール
(3)騎士団領侵略作戦、前夜
(4)「騎士団の誇り」の真相
(5)「コンスタンツ誘拐」の真相
(6)「テオドール豹変」の真相
(7)まとめ
2.バルハラント侵略作戦
(1)凍結湖の真相
(2)オブシダンソードの真相
(3)ヘイトの振る舞いの真相
(4)語られぬヘイトのバルハラント侵略作戦
(5)神に選ばれし者
おわりに
はじめに:
サルーインのミニオンの一人、「憎悪」のヘイト。彼が侵略を担当するのはマルディアスの南部方面・・・即ち、騎士団領とバルハラントである。
本稿では、ヘイトによる南部方面侵略作戦の語られぬ背景について言及する。
1.騎士団領侵略作戦
(1)ヘイトに目をつけられた人物
世界各地で暗躍するミニオン達の一番の目的は封印された邪神サルーインの復活である。そのために、サルーインを封印した宝石であるデステニィストーンの入手・破壊を目論んでいる。
そして、ヘイトの侵略担当地域の一つである騎士団領には火のルビーがあり、それは魔術師フラーマによって守られている。
単純に考えれば、直接行って奪い取るのが手っ取り早いのであるが、フラーマが住むバイゼルハイムの塔にはおそらく聖なる結界のようなものが張ってあるために邪悪なミニオンは侵入できず、またフラーマは騎士団領専属術法顧問、兼名誉議会員(大事典)という立場のため外出時にはおそらく騎士の護衛をつけていたために襲撃することも難しかったのでしょう。
#バイゼルハイムの塔にある宝箱は最初は「鍵がかかっていて開かない」のであるが、フラーマが「この塔の中の物は好きなように使ってかまいません。」と言うと開くようになる。
#おそらく、物理的に鍵がかかっていて開かなかったのではなく、術法で開かないようにしてあったのである。
#つまり、「開かない」→「それなら、きっと鍵がかかっているんだ」という思考の結果として「鍵がかかっていて開かない」と表示されたのである。
#そして、この宝箱にかけられた術法であるが、宝箱に「外部からの侵入を防ぐ結界が張られている」と見ることもできる。
#従って、この術法に類似した原理で何やかんやすることで、フラーマは塔に「外部からの邪悪なものの侵入を防ぐ結界を張る」術法を使用することができたのでしょう。
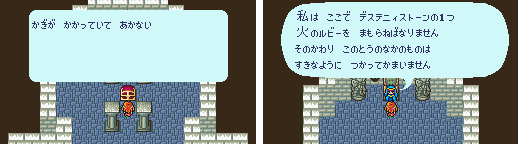
そこで、ヘイトは騎士団領のある人物を利用してフラーマから火のルビーを奪うことを目論んだ。
ロマ1の物語の舞台で行われたミニオンによる侵略作戦を概観してみると、バファル帝国のコルネリオ、クジャラートのハルーンのように、権力があり、かつ野望を持っている人物がミニオンと結託していることが分かる。
騎士団領においても同様に、権力があり、かつ野望を持っている人物がヘイトのセンサーに引っかかった。
そう、それが「騎士団の剣」と称されるミルザブール城主のテオドールである。
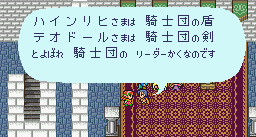
「権力があることは分かるが、野望を持っているとはどういうことか?」と思われる読者の方も多いでしょう。
テオドールの持つ野望とは、ゲーム内でテオドールの口から直接語られることはないものの、テオドールの親友ハインリヒの口から「最近では騎士団の精神も失われてしまった」、「これで他の騎士たちも目を覚ましてくれればよいのだが」と語っていることから分かるように、それはズバリ「騎士団領において騎士団精神を復活させる」ことである。
基礎知識編に、騎士団領では騎士のモラルの低下、騎士の誇りの喪失が深刻であり、テオドールは「失われつつある騎士道精神を何とか復活させようと、親友であるオイゲン公ハインリヒとともに心を砕いていた」と解説されていることからも分かります。
つまり、騎士団精神を精神を受け継ぐテオドールの野望は騎士道精神を受け継ぐが故の野望なのである。
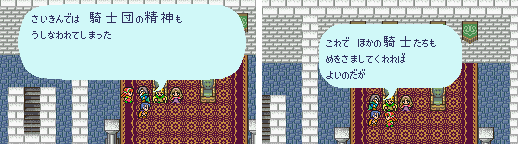
ヘイトに目をつけられたテオドール・・・この視点で騎士団領における一連のイベントを見直すと、ゲームをプレイしているだけでは気づかなかったヘイトによる騎士団領侵略作戦の真相が見えてくるのです。
次節より、それについて順に説明する。
(2)操られたテオドール
テオドールを中心に据えて騎士団領侵略作戦を読み解くために、まず一つの前提について整理しておく必要がある。「ラファエルを牢屋に入れたあたりから、私はサルーインの手下に操られていたようだ。それが正気に返ったために、ここに捕らえられたわけだ。」
この台詞は、イベント「テオドール豹変」時にテオドールから聞くことのできるものである。
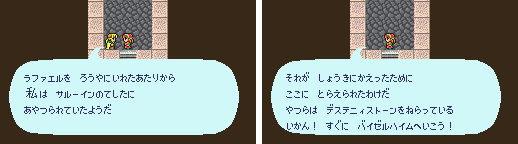
さて、皆さんはこの台詞における「私はサルーインの手下に操られていた」をどのように捉えているだろうか?
術法や薬物によって意思を奪われ、催眠状態のようにされて、モンスター側の指示に従って活動していた・・・と捉えている方も多いのではないだろうか。
筆者はそうではないと考えている。
その理由としては、ロマ1の物語で明らかに術法や薬物によって操られてしまった人物であるダウド及びファラの母親との違いを挙げることができる。
ダウドはアサシンギルドの尖兵として「死ね!」と冒険者を襲撃してくるが、返り討ちにあい、「・・・ギルド・・・万歳・・・痛いよ、死にたくないよ!・・・タルミッタの・・・西に・・・。」と呟いて絶命する。
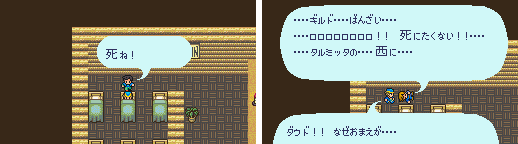
また、ファラの母親も「死ね、死ね、死ね!!」と襲い掛かってくるが、一発かまされると「・・・ギルド万歳・・・。・・・うーん、ここは・・・あたしゃ一体何を・・・。」、「おお、ファラ・・・。ってことは、ここはエスタミル・・・。あたしゃタルミッタの西のほうにいたはずなのに・・・。夢でも見てたのかね・・・。」と呟いて正気を取り戻す。

これらの台詞から、ダウドやファラの母親が「死ね!」や「ギルド万歳」と言っているときは本人の意思が全くない洗脳状態のようである。
そして、外部からのダメージにより正気を取り戻すことができるが、洗脳されていた時の記憶は残っていないようなのである。
一方で、テオドールはどうなのかというと、テオドールが操られていたというラファエルを牢屋に入れた頃、つまりコンスタンツが誘拐されている頃のテオドールの言動を見てみると、騎士道に反したラファエルが許せない!騎士道に反するからモンスターとの取引などできない!と明らかに本人の意思で行動しているのである。
それに、仮に術法や薬物によって操っていたのなら、効果が切れて正気に戻ったとしても、正気に戻ったテオドールを洞窟に監禁する必要はなく、再び術法や薬物で操り直せばいいだけのことでしょう。
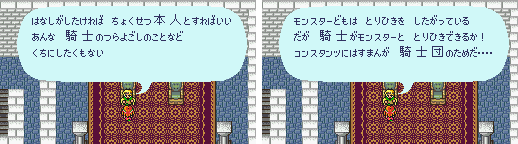
では、テオドールが術法や薬物によって操られていたのではないのなら、テオドールの言う「操られていた」というのはどういうことなのかというと、それは彼の性格が利用されたのである。
以下に文献からテオドールについての解説を抜粋して示す。
「騎士団領で生まれ育っただけに、誇り高い騎士でもある。ハインリヒに比べ熱血漢で、国民からは騎士団の剣とも呼ばれている。物事を常に大局的に考える卓抜な政治力で騎士団領を平和に保つ。」(基礎知識編)
「統率力と行動力の高さから騎士団の剣と呼ばれ、ハインリヒとは最上のコンビである。かつてならした剣の腕前はまだまだ現役だが、やや激昂しやすい性格をサルーインの手下に利用され、オイゲンシュタット南西の洞窟に監禁されてしまった。」(時織人)
このような記述から分かるように、テオドールは直情的な性格の人物である。
よく言えば「裏表がなくて素直」なのであるが、悪く言えば「思考が分かりやすい」ということである。
つまり、ある事柄が起こったときに、それに対してテオドールがとるであろう行動が容易に予想できるということである。
故に、テオドールのとるであろう行動を予想して事件を起こせば、予想通りにテオドールは動いてしまうのである。
従って、テオドールの言う「私はサルーインの手下に操られていた」とは術法や薬物によって洗脳されていたということではなく、単純に直情的な性格を利用されてモンスター軍の手のひらで踊らされていたという意味であると考える。
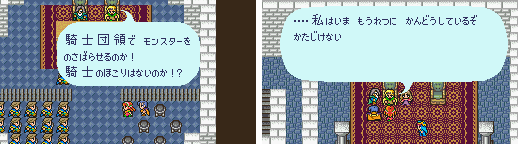
以下では、上記の意味での「操られていた」ということを前提として推察を進める。
(3)騎士団領侵略作戦、前夜
騎士団領侵略作戦を進めるにあたってヘイトは権力と野望を持つテオドールに目を付けた。そして、彼に接触し、彼の「騎士団領において騎士団精神を復活させる」という野望に協力すると持ち掛ける。
しかし、テオドールは歴戦の戦士、ヘイトの邪悪な気配に気づいているので、その申し出を拒否し、ヘイトを追い払う。
そのわずかなやり取りを通して、ヘイトはテオドールの直情的な性格を察した。
「利用できそうだな・・・。」
最終的にヘイトが火のルビーを奪取した場合に、ヘイトが「火のデステニィストーンであるルビーを手に入れて騎士団作戦の指揮官である私の面目も立ったというものだ。」と言うので誤解されそうであるが、大事典によると騎士団領における一連の侵略作戦を計画したのはヘイトではない。
大事典に「モンスター軍団の中で最前線に赴き指揮を取っているドラゴン。彼がバイゼルハイムのフラーマから火のルビーを奪おうと、あれこれ計略を練っている張本人だ。」と解説されているように、一連の侵略作戦を計画したのは「テオドール」の洞窟にいるレッドドラゴン(L)なのである。
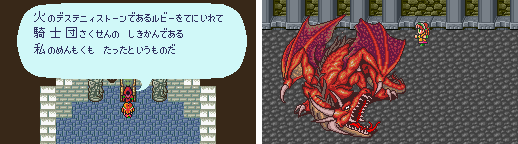
ヘイトはテオドールが利用できそうなことをレッドドラゴン(L)に伝えると、騎士団領の侵略はレッドドラゴン(L)に任せて、オブシダンソードの眠る極寒の地バルハラントに赴くのでした。
(4)「騎士団の誇り」の真相
操られていたテオドールという視点でロマ1の物語の騎士団領における第一のイベントである「騎士団の誇り」を見てみると、このイベントは山中にモンスターが自然発生したということではなくて、騎士団領侵略作戦を指揮するレッドドラゴン(L)の意図があったと考えられる。おそらくヘイトからテオドールの情報を得たレッドドラゴン(L)はすぐさまイフリートに命令し、騎士に変装させてミルザブールに潜入させ、テオドールを観察させることを通して、テオドールの人物像や騎士団領の現在の状況についての詳細な情報を入手させたのである。
・テオドールは確かに熱血漢で直情的な性格である。
・テオドールは騎士道精神を非常に大切にしていて、騎士団領にモンスターが蔓延ることを許せない。
・テオドールの望む騎士団の精神を持つ者はもはやほとんどいない。故に、テオドールに同調する者もほとんどいない。
・テオドールの盟友である「騎士団の盾」ハインリヒは沈着冷静(大事典)故に即座に突っ込んで来るようなことはしない。
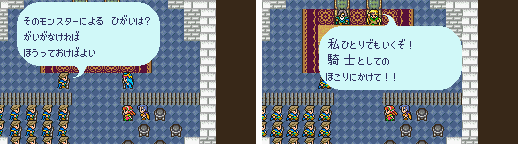
・・・こういった情報をもとにレッドドラゴン(L)は考えた。
「このような状況ならば、モンスターが発生したとしても、テオドールが単独で突っ込んでくることになるだろう。」
そこで、レッドドラゴン(L)は「モンスター」の洞窟のスネークマンを先発隊長に任命し、騎士たちを牽制させた。(大事典)
つまり、「騎士団の誇り」におけるモンスターの発生とは、レッドドラゴン(L)が自分の思い描いた通りにテオドールが実際に行動するのかを確認することを目的とした、言わば実証的な調査だったのである。
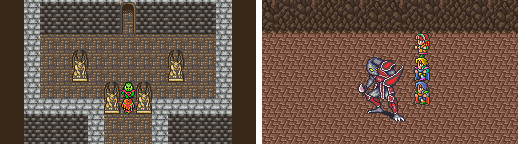
「騎士団の誇り」のイベントは、
・冒険者がテオドールに協力して解決する。
・冒険者がテオドールの面子を潰して解決する。
・冒険者が解決しなかった場合には(時間経過により)テオドールとラファエルが解決する。
の3通りの可能性があるが、いずれのルートにおいても騎士団からはテオドールとラファエルの2人が討伐に赴いているので、いずれのルートを辿ったとしてもレッドドラゴン(L)はテオドールは予想通りに動くという確証と、テオドールに同調する若い騎士(見習い)がいるという新たな情報を得ることになる。
なお、「騎士団の誇り」のどのルートを進んだとしても、その後にラファエルは騎士見習いから騎士に昇格しているようである。
テオドールに協力した場合には、ハインリヒが「これでラファエルを騎士に推薦できる」というので分かりやすいが、面子を潰した場合には騎士昇格をほのめかす台詞は一切無い。
しかし、面子を潰した場合でも「コンスタンツ誘拐」を解決した場合にはテオドールが「わが娘コンスタンツと騎士ラファエルが、その人生の重荷を二人で分かち合いたいと言ってきた。私はそれを許そうと思う。」というので、確かにラファエルは騎士になっているようである。
おそらく、テオドールに協力した場合には「敢闘賞」、面子を潰した場合は「がんばったで賞」で推薦されたのでしょう。
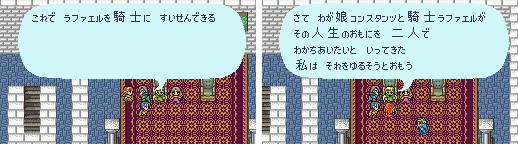
(5)「コンスタンツ誘拐」の真相
「騎士団の誇り」におけるモンスターの発生で得られた成果をもとに、レッドドラゴン(L)は火のルビーを奪取する計画を作成した。その第一段階が「コンスタンツ誘拐」である。
・テオドールは騎士道精神を非常に大切にしていて、騎士道精神に反することは絶対にしない。
・テオドールにはコンスタンツという娘がいる。
・コンスタンツと恋仲なのは、先のモンスターでテオドールに同調していた若い騎士である。
・コンスタンツは夜にこっそりと城を抜け出して、その若い騎士と密会をしている。
#この情報がオイゲンシュタットの娘たちの間で噂されるようになるのは「テオドール豹変」が発生してからである。
#つまり、レッドドラゴン(L)一派はこの内密情報を早期からつかんでいたことになる。
・騎士団において背中の傷は死罪に値する。(ゲーム内におけるハインリヒの台詞)
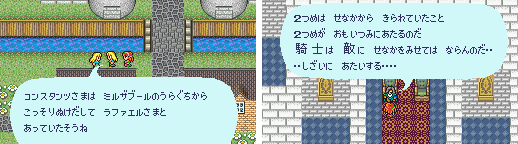
・・・こういった情報をもとにレッドドラゴン(L)は考えた。
「コンスタンツと若い騎士の密会中を狙って2人を襲撃し、若い騎士の背中に傷を負わせた上で、コンスタンツを誘拐する。」
「そして、テオドールに火のルビーと交換でコンスタンツを返すという取引を持ち掛ける。」
「そうすれば、テオドールに同調する若い騎士を死罪により排除でき、テオドールは騎士団精神によって苦しむことになる。」
このように思考を巡らせて作戦を考えるレッドドラゴン(L)は、そこらの騎士たちよりもはるかにテオドールが望む騎士団精神を学び、理解していた。
そもそもテオドールの望む騎士団精神とはどんなものなのかというと、騎士団領及びミルザ教の経典「銀の誓書」に記述された一文「正義のために戦った戦士ミルザの精神に学び、全世界の民を未曾有の邪悪なるものから守り、己の信念の為には死をも辞さない。」(大事典)を根本の理念として、その上で「開拓と自己の鍛錬を続け、ミルザの後継者として恥ずかしくない礼節と武勇を何よりも重んじる」(基礎知識編)というものである。
騎士団における「背中の傷は死罪に値する」というのは、「武勇を重んじる」と「己の信念の為には死をも辞さない」が合わさり、「敵に背を向けるという武勇に反する行動をとった者は死で償う」というように曲解された結果であろう。
そして、コンスタンツ誘拐計画は実行された。
主犯は「邪神復活計画に加わり、人間社会を混乱に陥れ、その隙にデステニィストーンを手に入れようとしている」オアンネスである。(大事典)
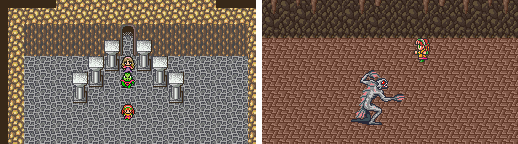
予想通り、若い騎士ラファエルは投獄され、身動きができなくなった。
投獄されたラファエルについて、テオドールは言う。
「話がしたければ直接本人とすればいい。あんな騎士の面汚しのことなど口にしたくもない。」
この台詞も、ラファエルを牢屋に入れたことも、決してテオドールが洗脳されたからのものではない。
あくまで騎士道精神が絶対であり、最優先すべきことというテオドールの信念に基づいたものなのである。
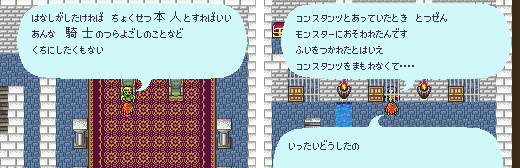
続けて、テオドールは言う。
「モンスターどもは取引をしたがっている。だが、騎士がモンスターと取引できるか!コンスタンツにはすまんが、騎士団のためだ。」
テオドールは取引の要求に応じないだけでなく、コンスタンツの救出を諦めているのである。
テオドールがこのような判断をしたことは、まさにレッドドラゴン(L)が予想した通りであった。
つまり、
取引を持ち掛けることで対等な舞台に乗せる。
→対等な舞台に乗ったからには、その舞台のルールに従う。
相手がモンスターであっても、そのルールを破ることは礼節と武勇を何よりも重んじるという騎士団精神に反する。
→一方で、火のルビーを渡すことはできないし、騎士たるものモンスターの要求を飲むことなど絶対にできない。
→従って、この取引のもとではコンスタンツを助ける方法はない。
というようにテオドールの判断を予想したのである。
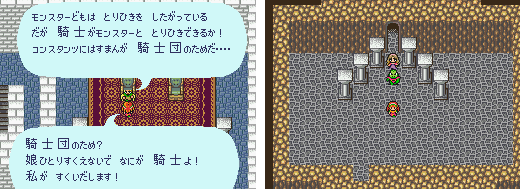
レッドドラゴン(L)の計画にはさらに先があった。
ある程度の時間を過ぎたらコンスタンツの命を奪い、それをテオドールに伝える。
テオドールがコンスタンツの亡骸を回収しに来たところに、それらしく数枚の書類を準備しておく。
それは魔術師フラーマの筆跡を真似て捏造したフラーマとモンスター軍の密書である。
そこには先のモンスターの発生や今回のコンスタンツ誘拐の手引きが記されていた。
つまり、テオドールに一連の事件の黒幕がフラーマであると思い込ませるためである。
騎士道精神と家族の命の狭間で葛藤し、最終的に家族の命を奪われ、その黒幕が身内であると分かったときにテオドールがどう行動するか・・・溜まりに溜まった業火の復讐心が黒幕討伐に向かわせるのは明らかである。
そして、フラーマの死亡によりバイゼルハイムの結界は解けたら火のルビーを奪取してミッションコンプリート!
・・・という展開である。
#上記における「黒幕フラーマ」というでっち上げは、結局は後の「テオドール豹変」において偽テオドールが打倒フラーマを掲げて騎士たちを煽動する際に使われることになる。
従って、レッドドラゴン(L)は最初からコンスタンツと交換で火のルビーを入手できるとは考えておらず、予想に反して交換に応じたら、それはそれで手間が省けてラッキーだった程度にしか思っていなかったであろう。
「コンスタンツ誘拐」には二つの結末がある。
一つは冒険者が介入して、コンスタンツを救出した場合である。
この場合の(物語を読み解くうえで)最も大きな要点は、テオドール流に言うと「テオドールが正気に返る」こと・・・分かりやすく言うと「テオドールが騎士団精神の本来の意味に気づく」ということである。
冒険者がコンスタンツを救出した姿を見てテオドールは言う。
「君のおかげで娘も騎士団もラファエルも救われた。私は大きな間違いを犯すところだった。名誉なきところに騎士の生きる場所はないと思っていた。だが 違うのだ。騎士が生き続ける場所に名誉が生まれるのだ。死して英雄になることより、生き続けて人生の重みに耐えることのほうが騎士としての名誉に適うのだ・・・。」
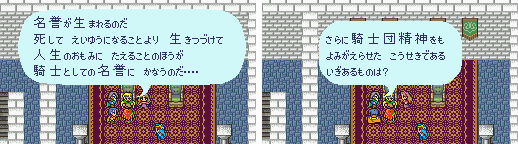
掻い摘んで言えば、テオドールは自分の理想としていた騎士団精神の捉え方は誤りであったと認めているのである。
銀の誓書に記された「正義のために戦った戦士ミルザの精神に学び、全世界の民を未曾有の邪悪なるものから守り、己の信念の為には死をも辞さない。」において一番重要な部分は「全世界の民を未曾有の邪悪なるものから守り」なのである。
かっこ悪くても、背中に傷を負ったとしても、それでも戦い続けて、全世界の民を邪神一派から守るということが一番大事なのである。
礼節と武勇を重んじるとか言って、娘を見殺しにするようなことがあってはならないのである。
つまり、テオドールは騎士団精神において大切にすべきことの優先順位を間違えていたわけである。
こうしたことに気づかされ、今までの自分の間違いを反省した結果が「正気に返った」という表現になったのである。
そして、このように騎士団精神の正しい解釈に気づかせてくれたことと、その解釈を実行して敵を倒してコンスタンツを救出した功績により、冒険者は名誉騎士の称号を受けることになる。
このように「コンスタンツ誘拐」において騎士団精神の正しい解釈がなされたという視点で改めて先の「騎士団の誇り」を見直してみると、テオドール達は確かに騎士団精神が全く分かっていない言動をとっているのである。
テオドールに協力して解決した場合においては、テオドール達にとって大切なことは「騎士が勇敢に戦って武勇を立てた」という事実であり、それにより「他の騎士も見習え!」と言いたいだけであった。
また、テオドールに協力しないで解決した場合においては、「先を越されて恥をさらしてしまった」から「他の騎士に『見習え!』と言えない」という面子を気にしているだけなのである。
「コンスタンツ誘拐」で気付く騎士団精神の本当の意味を分かっていたのならば、武勇を立てるとか、面子を気にするとか、そういう言葉は出てこなかったはずである。
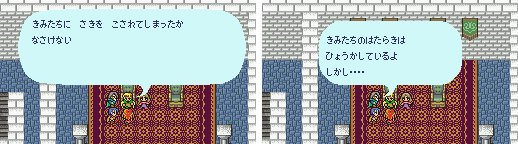
そして、「コンスタンツ誘拐」のもう一つの結末は、冒険者がコンスタンツを救出しなかった場合である。
この場合には、時間経過でコンスタンツとラファエルが無事生還しており、「コンスタンツ」の洞窟のオアンネスがいなくなることから、おそらく誰かがコンスタンツの救出に向かったと思われる。
ラファエルは牢屋の中、テオドールは誤った騎士団精神によりコンスタンツの救出を諦めている・・・となると、残るは「騎士団の盾」ハインリヒしかいないでしょう。
冷静な判断力を持つハインリヒであるが、だからと言って裏で画策するレッドドラゴン(L)の存在とその思惑にまでは考えが及ばなかったであろうから、単純にもう時間が無いと判断して、テオドールに内緒で救出に向かい、無事にコンスタンツを連れて帰還したのである。
そして、コンスタンツによりラファエルが敵に背を向けて逃げていないことが証言されて、ラファエルも無事に釈放された。
しかしながら、おそらく今までも突っ走るテオドールの尻拭いをハインリヒが務めてきたため、今回の一件についてもテオドールがハインリヒに「手間をかけさせたな。」と言う程度で終わってしまったのでしょう。
つまり、騎士団精神の真の意味に気づかないままなので、テオドールの騎士団精神に対する考え方は全く変わっていないのである。
テオドール流に言えば、この場合は「正気に返っていない」ということである。
なお、どちらの結末をたどった押しても「コンスタンツ誘拐」後にラファエルとコンスタンツは結婚したようである。
それは「テオドール豹変」におけるハインリヒの「コンスタンツとラファエルが結婚してからテオドールがおかしくなり始めた。」という台詞から分かる。
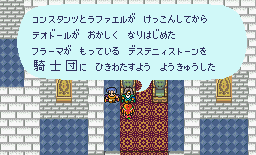
しかしながら、冒険者がコンスタンツを救出した場合とそうしなかった場合では、コンスタンツの結婚に対する心情がどうやら異なっているようなのである。
冒険者がコンスタンツを救出した場合にはコンスタンツから「父が変わってしまったのは私たちの結婚式の直後でした。」や「騎士の娘、騎士の妻として恥ずかしい。」のような自ら結婚を匂わせる台詞を聞くことができるのであるが、一方で冒険者がコンスタンツを救出しなかった場合にはコンスタンツからそのような結婚を匂わせる台詞を一切聞くことができなくなるのである。
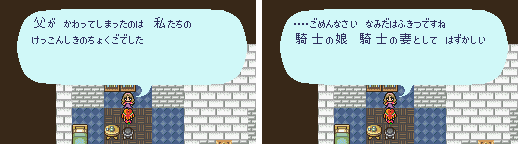
この理由は明らかである。
冒険者がコンスタンツを救出した場合には、テオドールの考え方が改められたため、寛大な気持ちでラファエルが認められたうえで、2人の結婚が許されたのに対して、冒険者がコンスタンツを救出しなかった場合には、テオドールの考え方は変わっていないため、ラファエルに対する評価は「背中は見せていなくても情けない奴」くらいで、しぶしぶ結婚を許したからである。
つまり、前者の場合はテオドールに祝福されているからコンスタンツは自信をもって結婚のことを口にできるのに対して、後者の場合はテオドールが本当は祝福してくれていないことを察しているためにコンスタンツは負い目のようなものを感じて結婚のことを口にすることが憚られているのである。
(6)「テオドール豹変」の真相
「コンスタンツ誘拐」においてコンスタンツが救出されてしまったために、レッドドラゴン(L)の計画は少し狂ってしまった。つまり、当初はテオドールにコンスタンツの亡骸を見せて、冷静さを失ったところに偽造した黒幕フラーマとモンスターの密書を見せることで、フラーマの討伐に向かわせる計画であったが、コンスタンツが救出されてしまったためにテオドールに密書を見せる機会が無くなってしまったのである。
そこで、レッドドラゴン(L)は作戦を少し変更したのである。
今までミルザブールに騎士に化けて潜入させていたイフリートに次はテオドールに化けさせて、「コンスタンツが誘拐されていた洞窟でフラーマとモンスターの結託していた証拠を見つけた!」、「今までの事件の首謀者は魔術師フラーマだった!」、「騎士団を欺いた魔女を打ち取って、騎士団の栄光を取り戻せ!」と他の騎士たちを煽動して、フラーマ討伐に向かわせるのである。
つまり、バイゼルハイムの塔には結界が張ってあるため偽テオドールであるイフリートは侵入できないから、同行した騎士たちに塔に侵入させてフラーマの命を奪わせるためである。
そのためには、まず本物のテオドールを排除する必要がある。
「やや激昂しやすい性格をサルーインの手下に利用され、オイゲンシュタット南西の洞窟に監禁されてしまった。」とあるように、その性格を利用してテオドールを「テオドール」の洞窟に誘い出したのである。
例えば「コンスタンツをまた誘拐した。最後の決着をつけよう。一対一の決闘でお前が勝利出来たら無事にコンスタンツを返してやる。誰にも言わずに一人でここに来い!」と地図に記して送るつけたとする。
この要求はコンスタンツの命を賭けたモンスターとの取引であるから、騎士団精神の正しい解釈に気づく以前ならば「モンスターとの取引はできない!」となってしまう。
しかし、テオドールが騎士団精神の正しい解釈に気づいた場合ならば「もう迷わない。同じ過ちはしない。全身全霊で娘を救出する!」とコンスタンツの救出を決意するだろう。
また、テオドールが騎士団精神の正しい解釈に気づかなかった場合であっても、決闘の申し出を受け入れないことは礼節と武勇を重んじる騎士団精神に反することになるから、モンスターとの決闘を決意するだろう。
そして、直情的な性格のテオドールはコンスタンツの嫁ぎ先のオイゲンシュタットに確認することなく勢い勇んで「テオドール」の洞窟に飛び込んで行き、そこでレッドドラゴン(L)と遭遇して、まんまと洞窟の最奥に幽閉されてしまったのである。
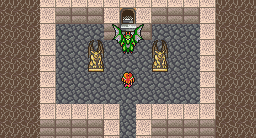
その頃、城主のいなくなったミルザブール城では偽テオドールとして入れ替わったイフリートが行動を起こす。
偽造したフラーマとモンスターの密書を掲げ、騎士たちに魔女討伐の煽動を開始したのである。
そして、フラーマに火のルビーを引き渡すように要求し、騎士たちを引き連れてバイゼルハイムに攻め入った。
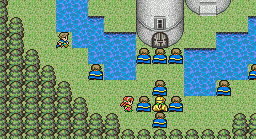
先の「騎士団の誇り」においては騎士たちがテオドールに同調しなかったにもかかわらず、今回はどうしてテオドールに同調したのか?
その答えはおそらくイフリートの話術にある。
大事典のイフリートの解説には「自分を神と偽って、人間を悪の道に引きずり込む。」と記述されている。
今回の場合ならば、巧みな話術で「騎士は正義!魔女は騎士を騙した絶対なる悪!」、「魔女を倒して騎士団の栄光を取り戻せ!」を騎士たちに刷り込むことで、同調させたのであろう。
長い期間、ミルザブールに潜入してテオドールを観察してきたイフリートは、その姿形だけでなく、立ち振る舞いもほぼほぼ完璧に真似することができたため、(話術が飛躍的に向上していたものの)誰もテオドールが入れ替わったことに気がつくことはなかった。
ただ一人、テオドールの娘コンスタンツを除いては。
コンスタンツは言う。
「以前から厳しい人でしたが今は残酷なだけです。行動で手本を示す人でしたが、今は言葉で人を操っています。そして・・・優しい父だったのに・・・今は・・・。」
やはり、話術の向上は気になるようである。
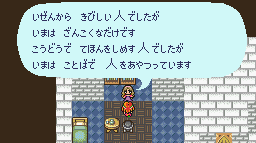
さらにコンスタンツは続けて言う。
「これはラファエルにも話していないのですが、あれは父ではないと思っています。」
「気持ちの問題ではなくて、今ミルザブールを治めているのは父ではなく別のものだと思うのです。話をしても、傍にいても、父の感じとは違うのです。どんなに人が変わっても間違えるはずがありません!」
姿形、立ち振る舞いは真似できても、家族だから分かるその人の雰囲気のようなものまではイフリートも真似できないようである。
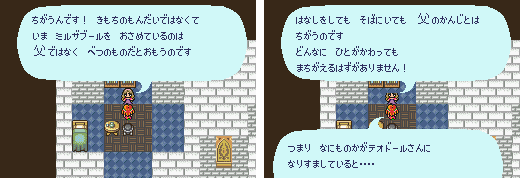
再びテオドールに話を戻す。
騎士団領侵略作戦ももう最終段階である。
イフリートがテオドールと入れ替わって偽テオドールとしてフラーマ討伐に動き出した今、もはや本物のテオドールを生かしておく必要はないのではないだろうか?
どうしてわざわざ生かして幽閉しているのだろうか?
この答えの手がかりが実はクジャラートにあるのである。
クジャラートで本物と入れ替わっている人物と言えば・・・そう、ハルーンの影武者・・・バックベアードである。
彼の変身も極めて精度が高く、その正体が分かった後に側近たちが「ハルーン様の影武者がモンスターだったとは・・・。」と呟くように、側近にさえモンスターの気配を感じさせることはなかったようである。
そんなハルーンの影武者バックベアードであるが、ハルーンが死ぬと影武者も姿を消すのである。
おそらく、変身を保つためには「真似た本体が生きていること」という条件があるため、ハルーンが死んだことで変身が解除されてしまい、バックベアードは去っていったのでしょう。
偽テオドールについても同様で、テオドールの姿を保つためには本体が生きている必要があったため、わざわざ生かして幽閉しているのである。
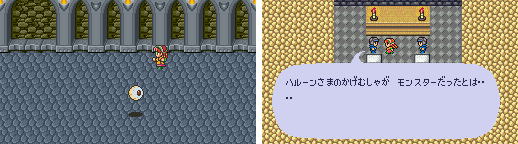
そして、この幽閉されている際のテオドールの行動にも、騎士団精神の正しい解釈に気づいたかどうかが影響するのである。
「コンスタンツの誘拐」の一件で騎士団精神の正しい解釈に気づいた場合には、「騎士道は死ぬことと見つけたり」ではなく「生きて助ける」であるから、強大なレッドドラゴン(L)に無謀にも挑んで死ぬようなことはしない。
それ故に、大人しく捕まって、脱出のチャンスを見計らっているのである。
そして、幽閉されながらも今までのことを振り返ることで「ラファエルを牢屋に入れたあたりから、私はサルーインの手下に操られていたようだ。それが正気に返ったために、ここに捕らえられたわけだ。」と、今までの一連の事件のつながりに気づくに至ったのである。
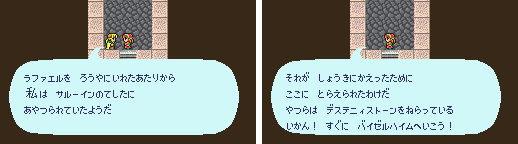
一方で、「コンスタンツの誘拐」の一件で騎士団精神の正しい解釈に気づかなかった場合には、「モンスターに騙されて幽閉されているなんて騎士としてありえない!」という考えからレッドドラゴン(L)に無謀にも挑んでしまうのであった。
レッドドラゴン(L)がその気になればあっさりと焼殺できるのであるが、そうするとイフリートの変身が解けてしまう。
そこで、何度も挑んでくるテオドールが鬱陶しいから、術法か薬品によってテオドールの正気を失わせることにしたのである。
その結果、テオドールは正気を失って「ねー、そういえばミルザブールのお城に入れなくなったわよね。」、「コンスタンツ様が裏口のカギを持ってたりして!」と1人2役の狂言を口走り始めるのであった。
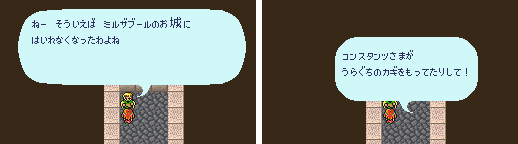
「テオドール豹変」には三つの結末がある。
第一の結末は、冒険者の介入によりレッドドラゴン(L)の侵略作戦が失敗に終わる場合である。
この場合には、テオドールとフラーマは無事生存し、レッドドラゴン(L)と偽テオドールであるイフリートは死亡する。
言わば、騎士団領編のハッピーエンドである。
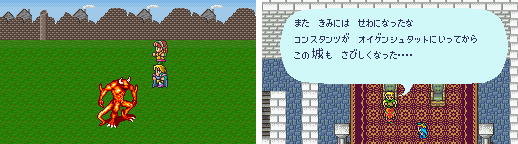
第二の結末は、冒険者が介入したものの冒険者がテオドールを見捨てたためにレッドドラゴン(L)の侵略作戦が完遂される場合である。
冒険者に救出されたものの、最後の最後で「何だこいつ、助けてやったのに!もう知らねー。」と見捨てられたテオドールは一人でフラーマの救出に向かう。
そこでテオドールは偽テオドールと対面する。
この時、偽テオドールであるイフリートはどういう行動をとるだろうか?
テオドールが冒険者を同伴させてやって来た場合には、「さあ、年貢の納め時だ!」と言う冒険者に対して「なんの、まだまだ!」とすんなりと正体を現して襲ってくる。
よくよく考えてみると、まだこの時点では騎士たちはフラーマを討伐できていないので、正体を現したら仮に冒険者たちを返り討ちにできたとしても、もはや騎士たちは従わなくなるので、火のルビーを奪取することができなくなってしまうのではないだろうか?
騎士たちを脅して無理やりやらせたり、術法や薬物によって操ったりするつもりなのだろうか?
いや、それが可能ならば、最初からそうすればいいわけであるが、そうしないで綿密な計画を進めてきたということは、無理やりや操るという方法では上手くいかないと考えていたのであろう。
ではなぜすんなりとイフリートは正体を現したのか?
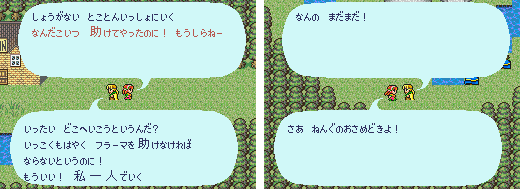
イフリートは下級神並の知能を持つ賢いモンスターである。(大事典)
おそらく、テオドールが名誉騎士である冒険者とともに現れたことで瞬時に察したのである。
「名誉騎士という説得力のある存在がいるから、自分の卓越した話術で向こうが偽物だと主張しても、遅かれ早かれ何やかんやで自分が偽物だということはバレるだろう。」
「それに、名誉騎士がテオドールを連れて来たということは、上司であるレッドドラゴン(L)が倒されたということだろう。」
「ならば、火のルビーを奪取できなくても上司のレッドドラゴン(L)に責められることはないから、もうこの作戦は失敗でもいいや。」
・・・その結果、「(作戦は失敗でもいいけど、)なんの、まだまだ!(私は死なないよ!)」と言う意味での「なんの、まだまだ!」を言って、正体を現して襲ってきたのである。
#レッドドラゴン(L)とイフリートが戦った場合、イフリートがレッドドラゴン(L)にダメージを与える手段はセルフバーニングによるカウンターしかないため、セルフバーニングを使い果たすまでの持久戦に持ち込むことでレッドドラゴン(L)が確実に勝利する。
#故にイフリートはレッドドラゴン(L)には逆らえない。
一方で、冒険者がテオドールを見捨てた場合にはテオドールは一人でやって来る。
#ラファエルが仲間にいたとしても、この場合にはテオドールについていかず、冒険者とともに見捨てる。
・・・名誉騎士が同伴していないのである。
イフリートは瞬時に考えた。
「テオドールが二人いることに騎士たちは戸惑うが、自分の卓越した話術があれば本物のほうを偽物だと偽ることは可能だろう。」
「テオドールが単独で上司のレッドドラゴン(L)を倒せるとは考えにくい。何かあったのか?」
「上司のレッドドラゴン(L)の生死は不明であるが・・・このまま上手くいけば、手柄が全て自分のものになる・・・かもしれない!」
・・・その結果、イフリートはすんなりと正体を現すことはなく偽テオドールのふりを続けて、後から現れたテオドールが偽物であると卓越した話術で騎士たちを説き伏せたのである。
その後、どうなったのか?
イフリートの狙いは塔の中に騎士たちを突入させて、フラーマの命を奪うことで、塔に張られた聖なる結界を解除し、自ら火のルビーを奪取することである。
故に、少なくとも結界が解除されるまでは自分の正体を騎士たちに知られてはいけない。
そして、実際に最終的な結末がどうなったのかというと、ヘイトが火のルビーを奪取した状況でも、塔を取り囲んだ騎士たちはフラーマ討伐を叫んでいるのである。
これらのことから、偽テオドールは正体を現すことなく、本物のテオドールを生かしたまま無事に塔に侵入することができたのだと推察できる。
なぜなら、
・テオドールの攻撃に対して迎え撃つために正体を現したら、周りにいる騎士たちにバレてしまう。
・テオドールの攻撃を受けて、偽テオドールのまま絶命したら、変身の術法も解けて正体を知られてしまう。
#モンスターは正体を現さないと本来の力を発揮できないので、偽テオドールのままならテオドールに倒される可能性もあった。
・テオドールを殺してしまったら、本体の死亡により変身の術法が解けて正体を知られてしまう。
というようになるのであるが、実際の最終的な結末において塔を囲んだ騎士たちに正体をバレていないということは、上記のいずれの場合でもないからである。
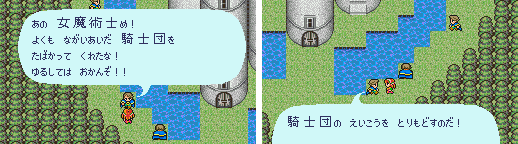
従って、テオドールが一人で偽テオドールと対面して、偽テオドールが騎士たちに後から現れたテオドールが偽物であると吹き込んだ後の展開はおおよそ次のようであったと推察される。
多勢に無勢でテオドールは騎士たちに取り押さえられた。
#もしかしたら、テオドールが偽テオドールに捨て身の特攻をしたかもしれないが、失敗に終わる。
騎士たちが塔の入口の鍵を破壊して、塔の中に突入する。
襲い掛かってくる騎士たちにフラーマも抵抗したが、騎士たちの波状攻撃の前に命を落とす。
偽テオドールは結界が消えたのを確認すると、塔の取り囲んだ騎士たちに待機命令を出して、テオドールを連れて塔内に侵入する。
そして、塔内で変身を解除し、テオドールと塔内にいた騎士たちを焼殺する。
#結界が消えた時点で正体を現しても問題なかったが、面倒を避けるために塔内で変身を解除した。
こうしてイフリートは無事に火のルビーの奪取に成功し、見事に騎士団侵略作戦は完遂されたのである。
これが「テオドール豹変」の第二の結末である。
そして、最後に第三の結末は、「テオドール豹変」を終わらせずに放置した場合である。
具体的にいうと、解決せずに戦闘回数9999回の時間経過をした場合である。
この場合、テオドールとフラーマは死亡しているので、おそらく騎士団領侵略作戦は計画通りに完遂している。
特筆すべき点は、「テオドール豹変」で冒険者にレッドドラゴン(L)が倒されていないならば、レッドドラゴン(L)が生存していることである。
つまり、この場合がレッドドラゴン(L)にとっては一番のハッピーエンドになるのである。
そして、もう一点触れておかなければいけないことがある。
それは、この場合にはハインリヒも死亡するということである。
「テオドール豹変」の発生当初からハインリヒは「これからテオドールと一戦交えに行く」と息巻いていた。
しかしながら、実際には冒険者が介入できる段階では全く行動に移さないのである。
その結果、下手に冒険者が介入した場合には、ハインリヒが行動に移す前にテオドールとフラーマの命と火のルビーが奪われてしまうのである。
沈着冷静とは言うが、あまりにも慎重すぎると言わざるをえないように思う。

思い起こせば「コンスタンツ誘拐」の時も、ハインリヒは誰もコンスタンツの救出に行かないということが分かると、最後の最後に重い腰を上げて救出に向かっていた。
今回についても同様で、最後の最後に重い腰を上げたのである。
そして、偽テオドールと一戦交えて玉砕してしまったのでした。
これらの事実から言えることは、おそらくハインリヒは夏休みの宿題を最終日の夜に徹夜でやるタイプであったということである。
#なお、ラファエルとコンスタンツもオイゲンシュタット城からいなくなるが、その後の時間経過で生存を確認することができる。
(7)まとめ
本章では、騎士団領侵略作戦は「テオドールの直情的な性格を利用する」ことが根幹にあったことについて述べた。騎士団領侵略作戦におけるMVPが、長い期間騎士団に潜入し続けて情報収集をし、さらに急な作戦変更に対応して見事に偽テオドールを演じり、見事に火のルビーを奪取したイフリートさんであることに異論はないであろうが、その背後には一連の作戦を計画したレッドドラゴン(L)さんという影の功労者がいたことを私たちは忘れてはいけません。
2.バルハラント侵略作戦
(1)凍結湖の真相
騎士団領侵略作戦をレッドドラゴン(L)に任せたヘイトはバルハラントの凍結湖に訪れていた。湖は凍りつき、邪のオブシダンが眠るという凍った城の入り口も分厚い氷の下に埋もれているようである。
・・・しばらくして、ヘイトはあることに気がついて呟いた。
「これは・・・もしや・・・。」
さて、バルハラントの凍結湖と言えば、初期は氷が張っていて、後期になると氷が溶けて湖底の城に侵入できるようになる場所である。
では、皆さんはこの氷が溶けた原因をどのように捉えているでしょうか?
ガトの村の湖大好きな女性が「こうあったかいと、南の湖の氷も溶けちまうかも。」と言っているように、気候が暖かくなってきて温度上昇により溶けたのでしょうか?
確かに大事典には次のような記述があり、温暖化しているのは確かなようである。
「最近気候が暖かくなってきたせいか、洞窟内に潜んでいたモンスターがフィールド内に出現。」(大事典、覇の章)
また、大事典の「凍結湖の城」の解説には次のような記述もある。
「氷の融けた理由としては、異常気象という説が有力。入口にいる赤魔法使いが自ら火の術法で融かした、とも言われている。」(大事典、用語辞典)
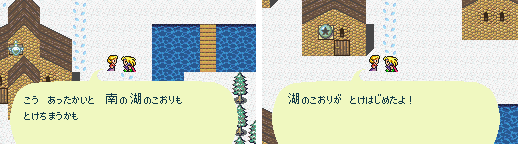
「最近気候が暖かくなってきた」、「異常気象」・・・ロマ1の物語の開始直前頃というと、ミニオンの暗躍が始まった頃でもある。
バルハラント担当のヘイトの配下には騎士団領管轄のレッドドラゴン(L)がいるが、その解説には次のように記述されている。
「地上に降り立つと、干ばつを起こすほどの炎を持つ。」
もしかしたら異常気象の原因はレッドドラゴン(L)が関わっているのかもしれない。
しかし・・・である。
バルハラントが暖かくなってきたというのは確かなようではあるが、それが凍結湖の氷が溶けた原因ではないのではないだろうか?
その理由の一つは、バルハラントの地相属性である。
バルハラントの地相属性は(さらに言えば騎士団領の地相属性も)「冷」属性である。
バルハラントの雪原は氷の洞窟である西の洞窟や南の洞窟と同じ「冷」属性である。
つまり、バルハラントは十分寒いのである。
従って、凍結湖の氷があれほど大規模に溶けるとは考えられないのである。
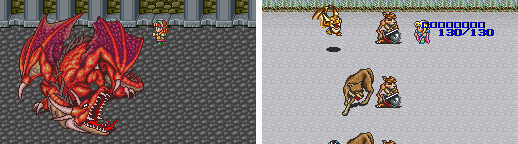
では、ガトの村の「最近暖かくなってきた」という情報は何なのかと言うと・・・これは本州の人間が北海道で過ごしたときに道民と会話して唖然とする話と同様なのであるが、道民の「暖かい」は本州人の「暖かい」とは違うということである。
つまり、-15℃が当たり前の環境ならば-5℃でも(いつもに比べたら)「暖かい」になってしまうのである。
#ドラクエ風に言えば「輝く息」に比べたら「凍える吹雪」はまだ易しいということである。
では、ミニオンが溶かしたのだろうか?
ヘイトが変身した赤魔法使いは確かに火術を使用することができるが、凍結湖の大量の氷を溶かすほどの火力があるとは到底考えられない。
それに、そこまでの火力が無いからこそ、ピンポイントで城の入り口付近だけ氷を溶かせばいいはずであるが、実際には凍結湖の氷は全体的に万遍なく溶かされているのである。
赤魔法使いが正体を現してヘイトになり闇術ブラックファイアを用いたとしても、もしくは火術使いのストライフをバファルから招聘したとしても、同様の理由で凍結湖の氷を溶かせるとは到底思えない。
それでは、凍結湖の氷はどうして溶けたのか?
その真相に迫るために、凍結湖の全景を改めて見ていただきたい。
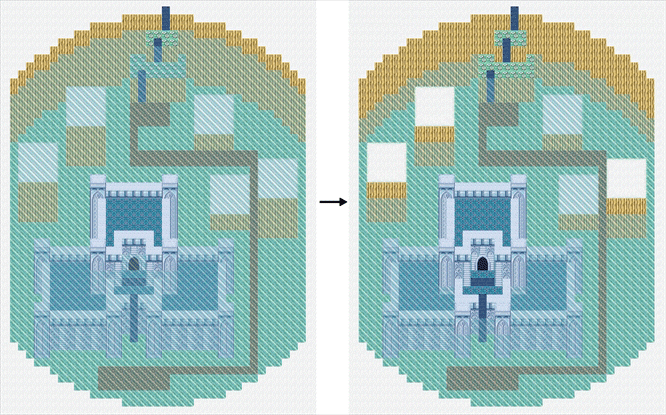
氷が溶ける前をもとにして溶けた後を見てみると、不自然であることに気づいたでしょうか?
氷が溶けたらどうなるか・・・そう、溶けたら水になるはずである。
では溶けた水はどこに行ったのか?
凍結湖の城は大きな窪地の底に建築されている。
その窪地に水が溜まって、それが凍ったらから凍った湖になっているわけであるから、水はけ(吸水性)がいいわけではないだろう。
加えて、水が抜け出ていくような部分も見当たらない。
従って、氷が溶けたのならば本来はプール状態になるはずなのである。
しかし、実際にはそうなってはいない。
これはどういうことなのか?
その答えは凍結湖の氷が溶けるタイミングにある。
凍結湖の氷は戦闘回数880回の時間経過で溶ける・・・が、それだけでなく、デスから情報を聞くことによっても溶けるのである。
つまり、凍結湖の氷・・・少なくとも表層部の氷はデスに依拠するものと考えたほうが筋が通るのである。
おそらく、凍結湖の表層部の氷はデスが氷を模して術法で作った結界・障壁のようなものである。
故に、凍結湖の表層部の氷は水から作られたものではないので、デスが解除することで水になることなく氷が消え去るのである。
では、どうしてデスは凍結湖に氷の障壁を作ったのか?
それは当然、邪のオブシダンが埋め込まれたオブシダンソードを封印するためで間違いないだろう。
それならば、どうしてデスはオブシダンソードを封印する場所を凍結湖の城にしたのか?
デスと凍結湖の城の関係はどうなっているのか?
凍結湖の城の建築様式を見れば明らかであるが、これはオールドキャッスルや砂漠の地下の伝説の湖の遺跡と同じであるから、古代神時代(創造神マルダーや破壊女神サイヴァのいた頃)の建物である。
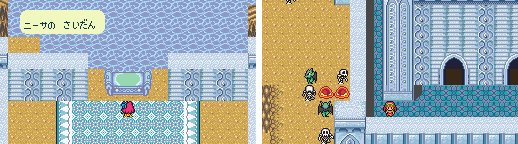
そして、凍結湖の内部に配置されている石像を見てみると神をかたどった像と竜の像が配置されているのであるが、一方で冥府のデスの傍らには悪魔の像が配置されていることと併せて考えると、この城はデスの居城やデスを祀った城というわけでもないようである。
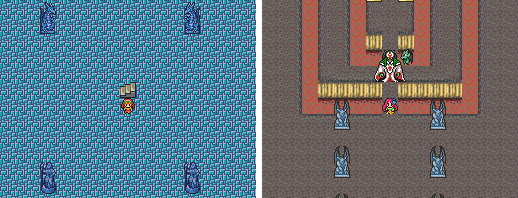
それなのに、どうしてデスは凍結湖の城にオブシダンソードを封印したのか?
推察ではあるが、凍結湖の城はかつての邪神封印戦争の際にデスが攻め落として、地上での侵略の拠点にした場所である。
さらに推察を重ねるが、おそらく当時は・・・デスが侵略してくるまでは、バルハラント一帯はまだ温暖な地域で、凍結湖の城の周辺にも人々が住んでいたと思われる。
しかし、デスが侵略してきてバルハラントは戦場になった。
そして、その戦いの中でデスはバルハラント一帯の生気を吸いとったのである。
大事典の邪術「デスハンド」の解説は次のように記述されている。
「冥界の力を借り、死の使いの手を相手の頭上に出現させる。その凄まじい重量と生気を吸い取る冷気によって、相手を一瞬で倒すのだ。」(輝の章、邪のオブシダン)
そう、デスの生気を吸い取る攻撃は冷気であり、冷気は熱を奪うのである。
かつての大戦において力を奪われたため、ロマ1の物語の舞台で戦うデスにはそれほどの脅威を感じないかもしれない。
しかしながら、エロールが「かつて神同士の戦いがあった。その時、この世界は一度死んだ。それほど神の力は激しいのだ。」と語るように、神々の秘めたる本当の力はあまりに強大なのである。
大戦時、封印される前のデスは死の神の力をいかんなく発揮して、とてつもない災害のような冷気でバルハラント一帯を覆って生気を吸い取ったのである。
その結果、強大な神の力は温暖だったバルハラントの気候も変えてしまい、それ以降バルハラントは氷と雪に覆われた極寒の地になってしまったのである。
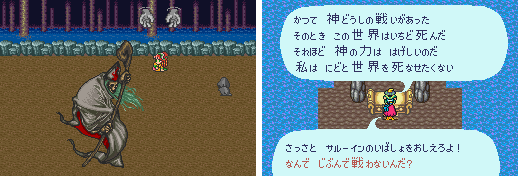
こうして、人々が死滅した凍結湖の城をデスは地上での侵略の拠点としたのである。
そして、この地から死者軍団を出撃させ、人間たちを蹂躙したのである。
#余談であるが、「バルハラ」というと北欧神話のオーディンの居城バルハラ宮殿を想起させられる。
#オーディンとバルハラ宮殿はGBサガ2にも登場していて、バルハラ宮殿は戦死した主人公が訪れる場所であり、そこでオーディンの力により生き返ることができる。
#意図してかどうかは定かではないが、バルハラントのデスとバルハラ宮殿のオーディンの関係は死者の再起という点で類似しているのである。
(2)オブシダンソードの真相
(1)では凍結湖とデスの関係について言及した。続いて、凍結湖の城に封印されているオブシダンソードとデスの関係について推察を進める。
オブシダンソードは死の剣とともに基礎知識編では特殊剣に分類され、特殊剣については次のように説明されている。
「剣の中でどの部類にも属さない、明らかに人間以外の手によって作られた剣もマルディアスには実在する。」(武器データ)
そして、死の剣については大事典には次のように説明されている。
「新しき神々との戦いにおいてデスが自分の骨髄から作ったと言われる剣。」(輝の章、マルディアスの神々、デス)
従って、死の剣はデスに作られたものであると分かる。
一方でオブシダンソードについては、その効力に関する説明はあるものの、その製造にかかわる記述はロマ1の文献には見当たらない。
そこで、推察するのであるが、基礎知識編には「明らかに人間以外以外の手によって作られた」という記述はあるのではあるが、実際にはオブシダンソードは人の手によって作られたのではないだろうか。
理由の一つとしては、モンスター軍にオブシダンソードを加工して作れる職人・技術者のような存在がいた痕跡が皆無だからである。
仮にそのような存在がいたのなら、もっとモンスター軍由来のオブシダンソード並みに高度な武器が現存していてもいいように思う。
また、別の理由としては、オブシダンソードが欠陥品であるということを挙げることもできる。
文献におけるオブシダンソードの効果についての解説は主に次のようなものである。
「邪の力によって強力なエネルギーの嵐を起こすことができるが、邪神には効力が薄い。」(基礎知識編、武器データ)
「邪のマイナスパワーによって、強力なエネルギー嵐を起こせる。」(大全集、アイテム総覧)
このように文献では邪剣波が使用できるということについては言及されているものの、オブシダンソードの持つ最大の効果については全く触れられていないのである。
・・・オブシダンソードの持つの最大の効果・・・そう、オブシダン譲渡による邪神の錯乱である。
どうしてオブシダンソードを手にしたサルーインは錯乱してしまうのか?
当然、そんな効果を意図してオブシダンソードが作られたわけではないことは確かである。
つまり、ある特殊な条件下において本来発揮されるはずの効果ではないイレギュラーな効果が発揮されてしまったのである。
・・・ロマ1においてイレギュラーな効果が発揮されるものと言えば・・・そう、呪われた靴である。
呪われた靴はウェイ=クビンが魔術アーマーブレスの効果を靴に永続化させることに成功したものの、副作用で以下のようにあらゆる属性が弱点になってしまった防具である。(本サイトの「ウェイ=クビン論」参照)
| 名称 | 装 | 防 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 呪われた靴 | 足 | 10 | 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ところが、弱点だらけなので本来は術法系属性ダメージを精神無視で食らってしまうようになるはずが、回復術法と併せることでダメージが1になるという反転現象のイレギュラーが起こってしまうのである。
#どうして回復術法と併せることでイレギュラーが起こるのか?・・・世の中、人知を超えた何やかんやで起こる現象もあるのです。
そして、このような人知を超えたイレギュラーが、サルーインがオブシダンソードを使用した際にも起こってしまったと考えられるのである。
オブシダンソードの性質について大事典には次のような記述がある。
「剣は邪気を伝導する金属で作られており、その切れ味はまさに魔剣と呼ぶにふさわしい。」(輝の章、邪のオブシダン)
「禍々しい妖気をブレードに備える。」(勇の章、アイテム図鑑)
また、オブシダンが本来持っていた耐性効果は以下の通りである。
| 名称 | 装 | 防 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| オブシダン | 頭 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
#誤解している人もいるが、ミルザがサルーインと戦ったときにはデステニィストーンは全て宝石そのままだったため、装備箇所云々は関係なかった。
#実際、大事典には「火の象徴である火のルビーは、ミルザ死後その崇拝者に受け継がれた。指輪にはめ込まれて聖宝とされ、~」(輝の章、火のルビー)というように大戦後に加工されたという記述がある。
#おそらく、オブシダンも最初は髪飾り(頭防具)に加工されたが、その後にオブシダンソードに加工され直されたと思われる。
これらのことから推察すると、オブシダンソードはおそらく邪のオブシダンから邪気を抽出して、それを刀身に伝導させて邪気を放つ剣である。
そして、サルーインが使用した際にはサルーインの強大な邪気に反応してサルーイン自身からも邪気を抽出し始めてしまった。
しかし、その強大な邪気を受けきることができず、暴発・・・イレギュラーな事態が起こったのである。
それが、呪われた靴と同様の反転現象のイレギュラーである。
オブシダンのもともと状態異常属性に対して耐性があったが、それ故に反転現象によってサルーインの精神状態を狂わせてしまったわけである。
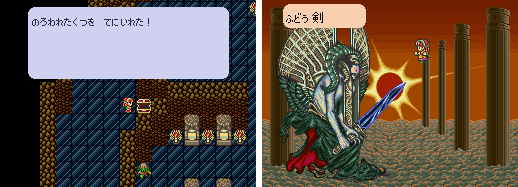
このようにオブシダンソードは呪われた靴と同様に本来の性能とは異なるイレギュラーが生じる欠陥品なのである。
なぜ欠陥品なのか?
・・・それは人が作ったからであろう。
永遠の物や邪気を纏う物など人間には扱えるわけがなく完璧な形に仕上げることができなかったのである。
それならば、オブシダンソードを作った人間とはどのような人物なのか?
それはおそらく邪神封印戦争において荒ぶるデスの雄姿を見たデスを崇拝する者・・・デス教の信者である。
邪神封印戦争後のデス教は教義の違いにより大きく二つに分かれている。
一つはデスはもう邪神ではないとする既成デス教であり、もう一つはデスは今でも地上制覇を狙っているとする「冥府を説く」である。(大事典、輝の章、マルディアスの神々、デス)
そして、その人物は後者の「冥府を説く」に属していた。
そんなある日、邪のオブシダンが「冥府を説く」の手に渡った。
「冥府を説く」はデスの復活を願う教団であるから、邪のオブシダンの力でデスを復活させようとした。
どうしたらデスを蘇らせることができるのか?
そう考えたときに、かつての大戦時のデスの雄姿が思い出された。
そう、死の剣を振り回すデスの姿である。
大事典には死の剣について次のように説明されている。
「大気中に散らばる邪悪な念動波を集める機能があるとされている。」(輝の章、マルディアスの神々、デス)
「得体の知れない黒色のブレードからは禍々しい邪気が放出されている。」(勇の章、アイテム図鑑)
おそらく死の剣は外部から邪気を吸収して、それを刀身に纏わせて邪気を放つ剣である。
お気づきでしょうか?、先に示したオブシダンソード・・・「邪のオブシダンから邪気を抽出して、それを刀身に伝導させて邪気を放つ剣」と見た目の特徴が類似しているのである。
おそらくその人物は「デスがかつての大戦のときのような強力な武器を再び手にしたら、再び地上の制圧に乗り出すのではないか」と考えたのである。
そこで、かつての大戦でデスが手にしていた武器を邪のオブシダンを使って再現しようと試みたのである。
その人物はウェイ=クビンレベルの天才だった。
見事に死の剣を模した剣・・・オブシダンソードを完成させたのである。
そして、冥府に入り、デスと謁見してオブシダンソードを献上したのである。
#大事典によると「冥府を説く」の信者はトマエ火山から冥府に自由に出入りすることができた。(輝の章、マルディアスの神々、デス)
#おそらく、エロールが「デスはもう戦う意思は無い」と判断して、フレイムタイラントに「デスを信仰する者が冥府に行くことを望むのなら通してよい」と伝えたからだと思われる。
デスは自分が作った死の剣と同等の剣を人間が作ったことに驚くとともに、その剣の持つただならぬ危険性を感じ取ったが、それ以上に邪のオブシダンが自分の手元に届いてしまったことに焦りを感じた。
つまり、邪気を司る神が邪のオブシダンを所持していたら、それで力を増強して再び戦いを仕掛けるのではないかとエロールに誤解されかねないからである。
#厳密には、オブシダンソードは死の剣にはない「物理ダメージ半減」効果と「邪術成長促進」効果を持つので上位互換である。
そこで、デスは自分の配下の一人フルフルにオブシダンソードを渡し、冥府の入口のあるリガウ島から遠く離れた、かつての大戦で攻め落とした凍結湖の城でそれを守るように命じたのである。
つまり、邪のオブシダンを使う意思は無いということをエロールに示すため、そして強力であり、かつ危険性を秘めた武器が世に放たれないためにオブシダンソードを凍結湖の城に封印することにしたのである。
こうして、デスの勅命を受けたフルフルは凍結湖の城でオブシダンソードの守護者となり、凍結湖はデスの術法により氷を模した障壁に覆われて、凍結湖の城には誰も侵入することができなくなったのである。
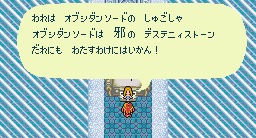
(3)ヘイトの振る舞いの真相
デスが凍結湖の障壁を解除したことにより、凍結湖の城への侵入が可能になった。冒険者が凍結湖の城に入ると、そこにはヘイトが化けた赤魔法使いがいて、「私はこの城に財宝を探しに来たんです。一緒に行きませんか?」と同行を持ち掛けてくる。
そして、赤魔法使いと同行しようがしまいが、いずれの場合も冒険者がオブシダンソードを手にしたところで正体を現して奪おうとしてくる。
・・・このイベントもよくよく考えてみると疑問が生じるだろう。
つまり、「どうしてヘイトは自分でオブシダンソードを取りにいかなかったのか?」、「どうして冒険者に同行する必要があったのか?」ということである。
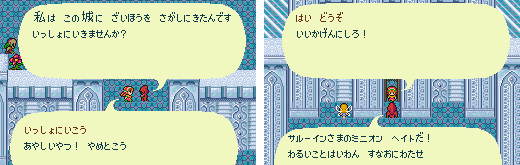
まず整理しておかなければいけないこととしては、モンスター達にもいろいろな派閥があるということである。
これはゲームをプレイしていても分かることであるが、世界中全てのモンスター達が全て邪神サルーインの配下というわけではなく、中にはフレイムタイラント一派もいれば、タイニィフェザー一派もいるし、ただあるがままに生きている野良モンスターもいるのである。
そして、凍結湖の城は(1)(2)で述べたようにデスの縁の地であり、そこの守護者はデスの勅命を受けたフルフルである。
故にヘイトとフルフル、ともにモンスターだからといって、「オブシダンソードをフルフルから譲ってもらえばいいのでは?」というのは派閥が違うためすんなりとはいかないのである。
それならば、欲しいものは「殺してでも奪い取る」でいいのではないか?
まず守護者フルフルのステータスは以下の通りである。
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 |  |
||
| 3608/3636 | 46 | 52 | 46 | 61 | 56 | 61 | 66 | 0 | 66 | 68 | - | - | × | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 1:つの14 2:アイアンソード14(隼斬り、鎌いたち、流星剣) 3:キック14 |
||||||||||||||||
| 風:61/61/117(吹雪、エレメンタル、ウインドバリア) | ||||||||||||||||
次に挑戦者ヘイトのステータスは以下の通りである。
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 |  |
||
| 7301/7373 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 84 | 4 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | - | - | - | - | - | × | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 1:通常攻撃14 | ||||||||||||||||
| 闇:50/50/61(ブラックスフィア、ブラックファイア、ホラー、ダークネス) | ||||||||||||||||
ステータスを見ただけでも明らかであるが、圧倒的にヘイトのほうが強いのである。
実際に凍結湖の城のフルフルにヘイト単独で挑んでみたところ、闇術ブラックスフィア一撃で勝利。
フルフルの攻撃にも相当耐えることができるので、(重複エレメンタルをされない限りは)まず間違いなくヘイトが勝つだろう。
それにも関わらず、ヘイトが単独でオブシダンソードの奪取に行かなかったのはなぜなのか?
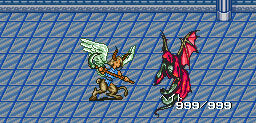
それはやはりデスと敵対したくなかったからであろう。
デスの配下のフルフルに手を出すということは、ある意味でデスに喧嘩を売るということである。
下手なことをしてデスに敵対の意思があると捉えられてしまっては、デスの存在が今後の大きな障害になりうる可能性もあるのである。
そこで赤魔法使いとして人間に扮してフルフルを始末し、フルフルからデスにテレパシーのようなもので自分の存在が伝えられないようにした後で、オブシダンソードを奪取することにしたのである。
仮にその後、ヘイトがオブシダンソードを入手したことがデスに伝わったとしても、フルフルを襲撃した冒険者から奪ったということで押し切れると考えたのであろう。
なお、赤魔法使いとして人間に扮して冒険者とともにフルフルと戦っても、赤魔法使いの正体がヘイトであるということがフルフルにバレないのならば、赤魔法使い単独でフルフルに挑むという選択肢もありえることになる。
赤魔法使いのステータスは以下の通りである。
| HP | 父親 | 母親 | 性別 | 利き腕 | 技回数 | 防御 | 重量 |  |
||||||||
| 500 | 魔術師 | 占い師 | 男 | 右 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 腕+ | 体+ | 器+ | 早+ | 知+ | 精+ | 愛+ | 魅+ | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 54 | 52 | 75 | 68 | 1 | 10 | |
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 武器:なし | ||||||||||||||||
| 防具:なし | ||||||||||||||||
| 火:50/50/15 (ヘルファイア、ファイアウエポン、セルフバーニング、ファイアボール) 風:50/50/23 (アイスジャベリン、コールドウエポン、ウインドバリア、ライトニング) 闇:50/50/31 (影縛り、ダークネス、ホラー、ブラックファイア、ダークウォール) 邪:50/50/31 (ポイズンガス、インジャリー、アゴニィ、イーブルスピリット、ライフドレイン) 魔:50/50/27 (エナジーボルト、スロウ、スペルエンハンス、ウエポンブレス) |
||||||||||||||||
実際に赤魔法使い単独でフルフルに挑んでみると、つのは一撃耐えられるものの、吹雪を受けたら即死。
ホラーとイーブルスピリットはそこそこ効くものの、効いても吹雪の対象から逃れられず、意味なし。
影縛りは麻痺耐性があるため効かない。
セルフバーニングで吹雪を無効にできるものの、つので押し切られる。
このような理由から、赤魔法使い単独ではフルフルに全く勝てないのでした。

赤魔法使いで勝てないのならば、配下のサルーイン教の神官に挑ませてみたらどうだろうか?
例えば、物語中に登場するサルーイン教に属する人間で最もステータスの高いマックス(サルーインの神官)だったらフルフルに勝てるのだろうか?
マックスのステータスは以下の通りである。
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 |  |
||
| 766/773 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 4 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:ガーラルフレイル11(スタンニングブロウ、ダブルヒット、三力破) | ||||||||||||||||
| 闇:50/50/63(ブラックスフィア、ブラックファイア、ホラー、ダークネス) 邪:50/50/63(ウイークネス、イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス) |
||||||||||||||||
マックスはヘイトと同様にブラックスフィアを使うことができるし、吹雪を1回耐えることができるため楽勝かと思われたが、実際にやってみると何度試してもブラックスフィアがフルフルに全く効かず。
どうやらマックスの魔力ではフルフルを即死できるほどのブラックスフィアを使用することができないようである。
また、麻痺耐性を持つのでスタンニングブロウで麻痺にもできず。
可能性はあるように思われたが、HPの低さもあって、マックスでも全く勝てないのであった。

このように、仮にサルーイン教に属する人間を呼び寄せたとしてもフルフルに勝てる見込みが全く無かったため、ヘイトはフルフルに勝てる人間が現れるの待たざるをえなかったわけである。
(4)語られぬヘイトのバルハラント侵略作戦
(3)では冒険者の目に見える範囲でのヘイトによるバルハラント侵略作戦について言及した。本節では、冒険者の目に見えない範囲でヘイトが行っていたバルハラント侵略作戦について言及する。
話を本章の最初に戻す。
・・・
騎士団領侵略作戦をレッドドラゴン(L)に任せたヘイトはバルハラントの凍結湖に訪れていた。
湖は凍りつき、邪のオブシダンが眠るという凍った城の入り口も分厚い氷の下に埋もれているようである。
・・・しばらくして、ヘイトはあることに気がついて呟いた。
「これは・・・もしや・・・。この氷・・・デス様か・・・。」
ヘイトは凍結湖を覆う氷から漂う気配を感じ取り、それがデスによって作られた結界であると察した。
邪神から生まれたミニオンとはいえ、さすがに死の神の作った結界を破るほどの力は持ち合わせていない。
凍結湖の城に眠る邪のオブシダンを回収するには、まずデスの作った氷壁を何とかしなければならなかった。
ゲームをプレイしていると、バルハラントにおいてヘイトのしたことは凍結湖の城で冒険者からオブシダンソードを奪おうとすることだけのように思いがちであるが、決してそうではない。
つまり、凍結湖の氷が温暖化等で溶けたのではなくデスが術法を解除することによって消え去ったのならば、冒険者がデスに情報を聞かなかった場合に戦闘回数880回の時間経過で凍結湖の氷が無くなっているのは、ヘイトが何かしらの行動をとった結果であると考えるのが妥当だからである。
そう、冒険者の目に見えない範囲でのヘイトによるバルハラント侵略作戦とは「ヘイトがどのようにして凍結湖の氷をデスに解除させたのか?」という話である。
デスはもはや地上の支配に未練はないらしい。(時織人)
実際、それを目論んでいるとエロールに誤解されないようにデスは細心の注意を払っていた。
例えば、(2)で述べたように邪のオブシダンが自分の手元にあることは反逆の意思表示になりかねないので、あえて遠方の凍結湖に封印することでそうではないことをエロールにアピールしている。
また、デスは死の剣と死の鎧だけでなく、「装備した者を光と気の術法から完全に守る力を持っている」という死の兜と死の小手も持っているのであるが(大事典、勇の章、アイテム図鑑)、以下に示すデスのステータスから分かるようにそれらを装備することなく、弱点をそのままにすることで、エロールに戦う意思が無いことをアピールしているのである。
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | 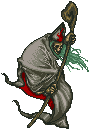 |
||
| 9922/10000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 4 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | - | - | - | - | - | × | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 1:死の剣14 | ||||||||||||||||
| 邪:99/99/255(デスハンド、イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス) | ||||||||||||||||
このようなデスの努力の積み重ねにより、「デスは善神ではないが、もはや邪神でもない。」とエロールに評されるようになっている(大事典、輝の章、マルディアスの神々、デス)。
そのようなデスにミニオンが凍結湖の結界を消してほしいと頼んだとしたら、その願いを聞き入れてもらえるだろうか?
デスがサルーイン一派と接触などしたらエロールに確実に疑念を持たれてしまうので、協力なんてとんでもない・・・おそらくデスはミニオンと会うことすらも拒むであろう。
#大事典にはデスについて「最近では弟のやっていることを静観中といったところ。凍結湖の存在を教えてくれるが、別にミニオンと結託しているわけではない。」(用語辞典)という記述もある。
それ以前に、デスに謁見するためにはトマエ火山のフレイムタイラントに冥府への道を通してもらわないといけないが、エロール側のフレイムタイラントがサルーインと同じ邪気を放つヘイトを通してくれるとは考えにくい。
それならば、ヘイトがフレイムタイラントに無謀にも戦いを挑んだらどうなるのか?
以下にフレイムタイラントのステータスを示す。
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | 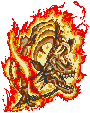 |
||
| 9825/9902 | 74 | 101 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 74 | 4 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| ○ | - | - | - | × | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 1:炎14(炎(全)) 2:牙14(毒牙、麻痺牙) |
||||||||||||||||
| 火:99/99/0(なし) | ||||||||||||||||
上記のようにフレイムタイラントは即死耐性を持つためヘイトの攻撃の要であるブラックスフィアが効かない。
そのため、地道にダメージを削るしか手段はなくなるのであるが、そうなるとHPと攻撃力でフレイムタイラントが勝るため、確実にヘイトは削り負けてしまうのである。
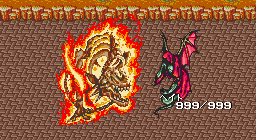
このように、デスの現状と自分とフレイムタイラントの力の差から、ヘイトは自分でデスに頼みに行くという方法は諦めて、別の手段を検討することにしたのである。
さて、ヘイトが凍結湖の氷を消すために画策する一方で、冒険者がデスから情報を聞く場合には意図せずして凍結湖の城への道が開く。
つまり、デスにガラハドを生き返らせるように要求すると、「つまらんことのためにきたなー。わざわざここまで来たのだ。手ぶらで帰すわけにもいくまい。願いは叶えてやるが代償はいただくぞ。それでもいいか?貴様なら絶対後悔するような代償だが。」と問われ、この問いに「かまわん!やれ。」と答えることで、「これでやつは生き返ったぞ。・・・。バルハラントに凍りついた城がある。そこに強力な武器がある。行ってみろ!」といった展開である。
このように冒険者がガラハドを生き返らせることでデスは凍結湖の氷を消し去り、冒険者を邪のオブシダンソードに導いてくれる。
さて、気になるのは、「どうしてガラハドを生き返らせるとデスは凍結湖の氷を消してくれるのか?」、「どうしてわざわざ封印した邪のオブシダンソードへの道を開放してくれるのか?」ということである。
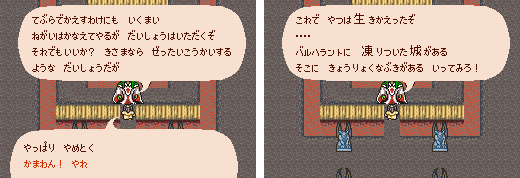
ガラハドを生き返らせるという願いを叶えると、デスは「・・・。」と暫く無言で考えてからオブシダンソードの情報を教えてくれる。
おそらくデスはこの「・・・。」において二つの理由の併せて総合的に判断した結果として冒険者に情報を教えてくれたのではないだろうか。
第一の理由は、冒険者に関心を持ち、冒険者ならば邪のオブシダンソードを上手く扱えるかもしれないと考えたからである。
ガラハドを生き返らせるという状況を細かく分ける次のと3通りある。
(i)アイスソードを殺してでも奪い取ってから生き返らせる。
(ii)死の剣・死の鎧の代償としてガラハドの命をデスに差し出してから生き返らせる。
(iii)死の剣・死の鎧の代償としてガラハドを含む複数の仲間の命をデスに差し出してからガラハドだけ生き返らせる。
の3通りである。
このような行動をとった冒険者に対してデスはどう思ったのだろうか?
(i)(ii)ならば「私欲のために他者の命を奪っておきながら、自らを代償としてでもその者を生き返らせようとする。・・・人間って・・・面白!」と某死神のように興味を持ってくれたのかもしれない。
また(iii)ならば「私欲のために何人もの命を差し出しておきながら、自らを代償としてでもある一人だけを生き返らせようとする。・・・人間って・・・怖!」と恐怖を感じたのかもしれない。
いずれにせよデスは人間の理解しがたい行動に関心を持つとともに、「人間ゆえに邪気は持たないが死者を生き返らせようとする気持ちがあれば邪のオブシダンが反応するのではないか?」、「私欲のために他者の命を奪ったが、それに対して贖罪しようとする者なら過度にオブシダンの力を引き出すことなく制御できるのではないか?」というように考えて、冒険者ならば上手くオブシダンソードを扱えると判断したのであろう。
#オブシダンソードに危険性が潜んでいる(イレギュラーが起こりうる)ことをデスは察していたが、邪気を持たない人間が扱う分にはそこまで力を引き出すことはできないと考えていた。(実際、冒険者が扱ってもイレギュラーは起こらない。)
#当然、デスはサルーインがオブシダンソードを使った場合にどのようなイレギュラーが起こりうるのかまでは把握していなかった。
そして、第二の理由は、エロールの意向を汲んだからである。
エロールの意向を汲んだといっても、もちろんエロールから直接言われたわけではない。
運命石論において述べたように、エロールはデステニィストーンの力が弱まり、邪神の復活が迫っていることを人間たちに伝えるために、AS922年にハオラーンの名で「世界のデステニィストーン」を執筆・発行して、デステニィストーンの所在地を明らかにした。
つまり、実際に効力の失われつつあるデステニィストーンを世界の表舞台に出すことで、人間たちに危機が迫っていることを伝えようとしたのである。
エロールのその警鐘活動はデスにも伝わっていたが、長い間機会が無く、邪のオブシダンは凍結湖の城に封印されたままであった。
しかし、興味深い人間が現れたことで、これを好機と思い、冒険者に託してみることにしたのである。
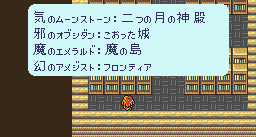
このような理由から、デスは冒険者に凍結湖の情報を与え、凍結湖の結界を解除したのである。
#心情としては、どうしても邪のオブシダンソードを託したいというわけではなく、興味深い人間だから試練(フルフル)を乗り越えられるならば持っていけ!といったところでしょう。
冒険者がデスから情報を得る場合には上述のような意図があってデスは凍結湖の結界を解除したと思われるのであるが、デスがそのような考えを持っていることなどヘイトが知る由もない。
では、ヘイトはどのような手段でデスに凍結湖の結界を消させようとしたのか?
・・・ヘイトが着目したのはデスの人物像だった。
デスは律儀・・・というか、筋の通った神である。
つまり、代償さえ支払えば、それに見合った(?)見返りをくれる神である。
#例えば、仲間1人の命に対して死の剣と死の鎧、冒険者の生命力に対してガラハドの蘇生と凍結湖の城の情報。
故に、何かしらの代償を支払うことで、その見返りとして凍結湖の結界を消させることを思いついたのである。
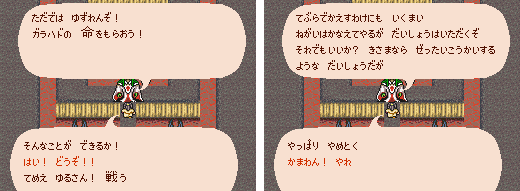
そうは言っても、先に述べた通りヘイト自ら行こうとしてもデスに謁見することすら難しい。
そこで、ヘイトは一人の人物に目をつけたのである。
凍結湖の結界を消すためにヘイトに選ばれた人物・・・それはデス教団「冥府を説く」の高位の神官であった。
今回の計画における人選では、二つの条件を満たす必要があった。
一つは冥府に行くことができることであり、もう一つはデスに代償を支払うことができることである。
(2)でも触れたが、大事典によると「冥府を説く」の信者はトマエ火山から冥府に自由に出入りすることができる(輝の章、マルディアスの神々、デス)。
また、大事典によると「冥府を説く」の信者は死後にアンデッドになって永遠の命を持つことを願っているようなので(輝の章、マルディアスの神々、デス)、その願いを叶える・・・つまり、一度死んだとしても永遠の命を持った状態で蘇らせるという餌を提示すれば進んで命を差し出すだろう。
このように、「冥府を説く」の信者は上記の二つを満たす適任だったのである。
そして、ヘイトは「冥府を説く」の高位の神官に話を持ち掛けた。
「魔の島の魔導士が魔のエメラルドの力で不老不死を実現させたという。」
「邪のオブシダンを使えば、アンデッドになって永遠の命を得るという願いも叶えられるのではないか?」
「邪のオブシダンはバルハラントの凍結湖の城にあるが、死の神の結界があって入れない。」
「死の神は代償を支払えば、願いを叶えてくれるかもしれない。」
「信者の命を捧げることで、凍結湖の結界の解除を願い出てはどうか。」
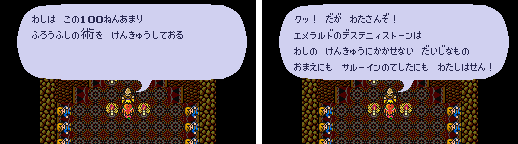
1.において述べたように、ミニオンの侵略作戦には権力があり、かつ野望を持っている人物が利用される。
そして、バルハラント侵略作戦においても、その条件は満たされているのである。
つまり、一人の命では足りないかもしれないからより多くの信者の命を代償としてささげることのできる高位の神官であり、その野望は「アンデッドになって永遠の命を得る」ということである。
#「冥府を説く」にはアンデッドになって永遠の命を得ることの他にも「デスの復活」という願いがあるが、デスとの交渉の際に「デスの復活」の話をしてしまうと復活する気のないデスとの交渉が上手くいかない可能性があるので、ヘイトが「冥府を説く」の神官に話を持ち掛けた際には「デスの復活」については意図的に触れないようにした。
その後、「冥府を説く」の高位の神官は行動に移した。
信者たちを引き連れて冥府に赴き、デスに謁見した。
「邪のオブシダンで永遠の命を得たい。どうか凍結湖の結界を解いていただきたい。」
#オブシダンソードを作ったのは昔の「冥府を説く」の信者であり、彼らがオブシダンソードが凍結湖の城に封印されたことを知っていたならば、その情報も受け継がれてきているだろうから、現在の「冥府を説く」の神官がオブシダンソードが凍結湖の城に封印されていることを知っていたとしても不思議ではない。
こうして、ヘイトの思惑通りに「冥府を説く」の信者たちの命を代償として凍結湖の結界はデスにより消し去られたのである。
以上が、冒険者の目に見えない範囲でヘイトが行っていたバルハラント侵略作戦である。
(5)神に選ばれし者
最後にもう一点、(4)における議論に関わって、何故だか理由がよく分からない謎についても言及しておく。それは、「どうしてガラハドだけデスとの交渉で生き返らせてもらえるのか?」ということである。
通り魔殺人のように「人が殺めた場合」は生き返らせることができて、強い武器の代償として「デスに命を刈り取られた場合」は生き返らせることができないのか?・・・とも考えたが、強い武器の代償としてガラハドの命を捧げた場合でもガラハドを生き返らせることができる。
そして、強い武器の代償としてガラハドも含めて複数の仲間の命を捧げたとしても、生き返らせることができるのはガラハドだけ。
何故だろうか?
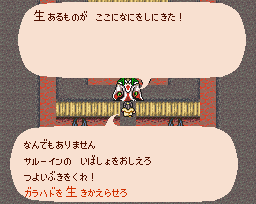
憶測であるが、これはもしかしたらエロールの仕業なのかもしれない。
「神々とてそれほど先のことが見えているわけではない・・・。」というエロールの言葉からも分かるように、少なくともエロールはそれなりに未来を見る力があるのだと思われる。
そして、その力でたまたま目に留まったのが不遇の聖騎士ガラハドである。
彼は心の清らかな人物であったが、彼の未来は・・・(多くの場合)通り魔、愉快犯によって命を落とす悲惨なものであった。
#グレイのエンディングにおいてハオラーンが「・・グレイよ。本当に見ていたよ。君のすばらしい戦いを!!」と言うように、エロールはグレイがお気に入りのようで、グレイを見ていた際にガラハドが目に留まったのであろう。
#グレイならばガラハドを2回殺して2回生き返らせるというガラハドの命を弄びまくる行為もできてしまう。
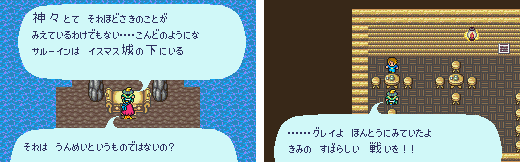
そのような気の毒すぎるガラハドに対してエロールは慈悲を与えた。
即ち、神の力で何やかんやして「ガラハドが死んだら生き返らせたくなる」というように人間の集合的無意識に仕込んだのである。
つまり、「最終的にガラハドが生存している確率」は「ガラハドが殺されないで生きている確率」+「殺されても生き返っている確率」であるから、生き返るチャンスを得ることで最終的に生存している確率をわずかでも高めているわけである。
こうして、冒険者は集合的無意識に組み込まれた「ガラハドが死んだら生き返らせたくなる」という思いによって「ガラハドを生き返らせろ」という言葉が勝手に口から飛び出ししまうのであった。
ガラハドの蘇生は言わば、ディアナ風に言うと「エロールの贈り物」なのでしょう。
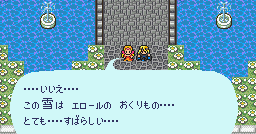
おわりに:
本稿では「憎悪」のヘイトによる南部方面侵略作戦の背景について読み解いた。ヘイトはデステニィストーンを二つ入手しうる有能なミニオンであるが、その功績は有能な部下(レッドドラゴン(L)とイフリート)と都合のいい操り人形(「冥府を説く」の高位の神官)の存在によって成し遂げられたのであった。
次稿「ミニオン論Ⅲ」では「闘争」のストライフによる東部方面侵略作戦の背景について言及する。
