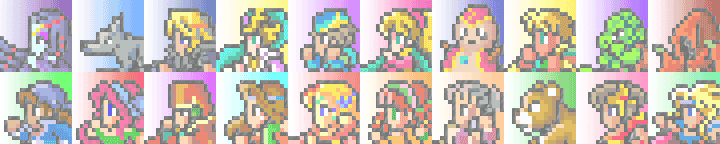
こんな所にロマサガが!
(2023年03月05日発表)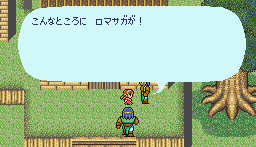
はじめに
1.別分野で見られるロマサガ1
事例1:ファミ通町内会
事例2:太蔵もて王(キング)サーガ
事例3:いぬまるだしっ
2.ロマ1の特色
おわりに
はじめに:
「こんな所にロマサガが!」ということで、ロマ1がゲームを飛び出して使用されている場面を目にすることがある。別の分野でわざわざ用いられているということは、ロマ1だからこその特色があるが故にロマ1が選ばれて用いられているはずである。そこで本稿では、筆者の手元にある別の分野の文献を事例として、それらにおいてロマ1がどのような意味として用いられているのかについて検討することを通して、ロマ1が持つ特色について言及したい。1.別分野で見られるロマサガ1
事例1:ファミ通町内会
「ファミ通町内会」とはファミコン通信~週刊ファミ通の読者投稿コーナーである。このコーナーにおいてロマ1を題材とした投稿がいくつか掲載されている。(1)お習字
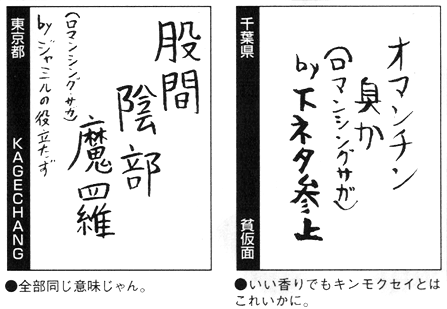
出典:ファミ通編集部責任編集(2001年10月)「ファミ通Books ファミ通町内会」. enter brain. p.16
お習字に掲載された2作品はいずれも淫猥な作品である。私自身の記憶を探ってみると、ロマ1の発売が発表された当時、小林画伯の美麗で妖艶なイラストの影響もあったかもしれないが、タイトルの「ロマンシングサガ」にとても甘ったるいような雰囲気(色気)を感じていたように思う。「ロマン(浪漫)」という響きだけでも大海原へと漕ぎ出す高揚感を感じるのに、「ロマンシング」となることで知らない世界の扉を開いてしまうような艶めかしい響きにドキドキさせられたのである。旧作の魔界塔士サガの持っていた荒廃感やサガ2の持っていた痛快観とは全く異なる色っぽいような雰囲気をロマンシングサガというタイトルに感じていたことは間違いない。おそらく上記の作品の作者の方々も、ロマンシングサガというタイトルに私が感じたような色っぽいような雰囲気を感じていたのではないだろうか。その結果、ロマンシングサガという言葉に潜在する色気に触発されて、自身に内在するリビドーを放出・表現したものが上記の作品となったのであろう。
(2)アナグラム・サム

出典:ファミ通編集部責任編集(2001年10月)「ファミ通Books ファミ通町内会」. enter brain. p.61
アナグラム(文字の並べ替え)・サムに掲載された作品・・・餓死サロンという架空の店の群馬支店ということだろうか。サロンや群馬はともかくとして、餓死とは生き物が栄養を断たれることで生命活動を維持することができなくなって死亡することである。人類の歴史を振り返ると、飢饉・大飢饉は世界各地で何度も起こっており、その都度多くの人々が餓死している。犠牲者の方々はもっと生きたかっただろうが、抗えぬ理不尽な死を突きつけられたのである。そう、ロマ1の「アルツール通り魔強盗殺人事件」のように。おそらく上記の作品の作者はロマンシングサガという言葉を題材としてアナグラムをすることで、上記の作品以外にもいろいろな作品を思いついたに違いない。(安易ではあるが、例えば筆者は「マグロが三振」や「具、3ガロン増し」を思いつきました。)それにもかかわらず、作者が最終的に上記の作品を選んだのは、上記の作品がロマ1に内在する「抗えぬ理不尽な死」というテーマを表現を変えても維持し続けていたからではないだろうか。(少なくとも、筆者が思いついた「マグロが三振」や「具、3ガロン増し」には残念ながらロマ1らしさを感じることはできない。)
事例2:太蔵もて王(キング)サーガ
「太蔵もて王サーガ」とは週刊少年ジャンプで連載していた大亜門先生の作品である。この作品の「第14章 バトルアスリーツ大運動会」において、障害物リレーに参加した主人公・太蔵(たいぞう)が自軍のリードでバトンを託されたにもかかわらず走りださず、追い上げてくる敵軍の生徒会長(女)の「あばれおっぱいを間近で見たくて待っていた」ことを敵軍の生徒会副会長に「ははは!バカじゃねーのか。そんな事のために勝負を棒に振るなんて!もてない男(ヤロー)は悲しいな!」と貶された際に太蔵が発した一言にロマ1が使用されている。
出典:大亜門(2006年3月)「ジャンプコミックス 太蔵もて王サーガ(2)」. 集英社. p.100
「男のロマン・・・ロマンシング・性(サガ)」・・・この用法はロマ1と言うよりは、GBサガ1における神の台詞「これも生き物の性(サガ)か」と同じものである。無論、GBサガ1では神に歯向かう人間の愚かさを人間の性(サガ)と言っているのに対して、太蔵の台詞は愛欲を性(サガ)と言っているという違いはあるが、いずれも人間の持つ本質、即ち性(サガ)である。先に事例1(1)で述べたように「ロマンシングサガ」というタイトルには魅惑的で淫猥な雰囲気が内在している。おそらく若き日の大亜門先生の記憶にも「ロマンシングサガ」というタイトルが魅惑的で淫猥なものとして焼き付けられていたのであろう。その結果、思春期の男子が性的欲求には抗えぬ様子を端的に表現するために想起されたのが上記の一言なのではないだろうか。
事例3:いぬまるだしっ
「いぬまるだしっ」とは週刊少年ジャンプで連載していた大石浩二先生の作品である。この作品の「第44回 導かれし丸出し」において、第43回から始まった「いぬまるだしっQUEST」の世界を冒険する旅人たまこ、僧侶すずめ、まるだしスライムが魔王フトシの「オレ様は賢いのだ。下手に冒険させてレベルを上げられる前に低いうちにつぶす。ククク・・・画期的だろう。これからキサマたちを魔王城へワープさせてやろう・・・」という思いつきで魔王城にワープさせられ、魔王城の1階がモンスターに埋めつくされている様子を見た際に、すずめが発した一言にロマ1が使用されている。
出典:大石浩二(2009年10月)「ジャンプコミックス いぬまるだしっ(3)」. 集英社. p.136
ロマ1に対する不評コメントでよく見かける「敵シンボルが多すぎる」をそのままズバリ表現したものである。きっと、大石浩二先生もロマ1の敵の多さで苦労なされた過去があったのでしょう。それ故に、「敵が多い」ことを表現するために最も適切なラベルとして想起されたのが「ロマサガ」だったのではないだろうか。
2.ロマ1の特色
1.では5つの作品に伴うロマ1の特色について考察をした。その結果、他の分野でロマ1が用いられているのは、ロマ1には以下のような特色があったからだと考えられる。(i)「敵の多さ」を象徴するゲームである。
(ii)命について考えさせられるゲームである。
(iii)人間の性(サガ)である性愛を刺激する色気・雰囲気を持つタイトル(作品名)である。
(i)と(ii)についてはロマ1をプレイすることで実感することができる特色である。ウジャウジャといる敵シンボルや主人公の選択に他者の命が委ねられている点は、ロマ1をプレイした者に強く印象付けられるのであろう。
一方で、意外だったのが(iii)である。ロマ1のゲーム内には性愛を刺激するようなイベントや台詞、仲間やモンスターのグラフィックは 一切存在しない。(後作のFF作品やロマサガ作品にはそういう要素が無いわけではない。)それにもかかわらず、今回事例とした5作品のうちの3作品が性愛絡みだったのである。そして、その原因として「タイトル(作品目)の持つ雰囲気」を指摘した。「ロマ1」や「ロマサガ」という略称では感じられないが、「ロマンシングサガ」となると途端に色気が漂い出すのである。おそらく「ロマンシング」という言葉から色気が漂っているように思う。そこで、改めて「ロマンシング」という言葉の意味について調べてみた。
■「romance」の意味
参照:英辞郎 on the WEB
[名]
1:ロマンス、〔短く激しい〕恋愛
2:〔激しいまたは理想的な相手との〕情事、性愛
3:冒険心、英雄的行為への憧れ
4:〔中世の〕騎士道物語
5:〔長編の〕冒険[伝奇・空想]物語
6:恋愛小説[映画・文学]
7:〔話や説明の〕虚飾、荒唐無稽
8:《音楽》ロマンス◆叙情的な短い楽曲
9:《Romance》=Romance language
[自動]
1:夢物語を話す[作る]
2:ロマンチックな[現実離れした]考え方[行動]をする
[他動]
1:〈話〉〔ロマンチックな方法で人に〕求愛する、〔騎士道精神にのっとって人を〕あがめる
2:〈話〉〔人と〕恋愛する、〔人と〕性的関係を持つ
なるほど納得。私自身は特に意識することなく「ロマンシング」を「現代にいながらも大航海時代の世界に冒険に繰り出す」ような意味合いとして捉えていたが、その一方で「ロマンシング」には性愛的な意味がそもそもあったのである。しかしながら、言葉の意味を知らないながらも当時の自分が「ロマンシング」という言葉に「知らない世界の扉を開いてしまうような艶めかしい響きにドキドキさせられた」ということは、やはり「ロマンシング」という言葉そのものから色気のようなものが感じられたということだろう。そして、その色気が場合によっては人の情動を駆り立てるのである。そう考えると、ゲーム内容からすると「ロマンシング」は冒険的な意味であるが、その一方でゲーム内容とは関係ない性愛的な意味が「ロマンシングサガ」というタイトルに色気を与え、潜在的に煽情的なドキドキ感を生じさせることにより、ゲームへの期待感、ドキドキワクワク感を暗黙的に増大させる効果があったということが言えるのかもしれない。
上述したように「ロマンシングサガ」というタイトル(作品名)と性愛の関係について明らかになったのでこれ以上は余談にはなるが、ついでなので「サガ」の意味についても改めて調べてみた。「サガ」というタイトル(作品名)が物語的な意味と人間の性(サガ)的な意味のダブルミーニングであるということはGBサガ1の時点で言われていたので、
■「saga」の意味(参照:英辞郎 on the WEB)
[名]
1:〔北欧文学の〕サガ、サーガ◆古ノルウェー語の散文で書かれた、中世の歴史的・神話的人物の物語
2:〔サガに似た〕英雄[冒険]物語
3:大河小説◆家族や部族の数代にわたる長編小説
4:〈話〉長ったらしい[こまごました]説明
物語的な意味の方については特にひっかかることはないが、
■「性・相(さが)」の意味(参照:コトバンク)
[名]
1:生まれつきの性質、もちまえ
2:もって生まれた運命、宿命
3:ならわし、習慣、くせ
4:良いところと悪いところ、人間の善悪、また特に欠点・短所・悪癖
人間の性(サガ)的な意味の方についてはグイグイとフックに引っかかることがあった。つまり、「ロマンシングサガ」というタイトルにおける「サガ」の人間の性(サガ)的な意味には「生まれつきの性質」という意味だけでなく「運命・宿命」や「人間の善悪」というロマ1の根幹に関わるような意味も込められていたのではないかということに気付かされたのである。GBサガが「ロマンシングサガ」という美しいタイトルに変わったことで魔界塔士サガの持っていたゴチャゴチャとした雑居感は完全に失われたと思っていたのであるが、実のところタイトルにいろいろな意味が込められていたという点については魔界塔士サガの雑居感の精神を踏襲していたと言えるだろう。
おわりに:
本稿において事例とした扱った作品はいずれもロマ1が内包する特色を表現しているすばらしい作品であった。そして、その特徴について整理することを通して、「ロマンシングサガ」は一般に「ロマサガ」と省略されて呼ばれているために見失いがちであるが、「ロマンシングサガ」というタイトル(作品名)そのものには人間の性(サガ)を刺激する不思議な魅力があるということを思い出すことができたことは大きな収穫であった。本稿では筆者の手元にある限られた事例を対象として議論したが、他にも「こんな所にロマサガが!」をご存知の方がいらっしゃいましたら情報提供いただけるとありがたいです。
